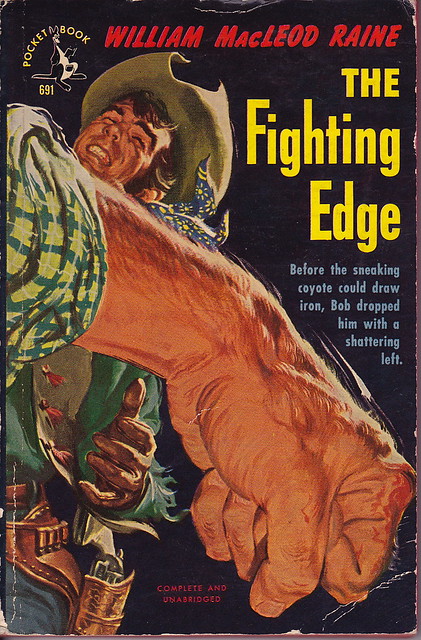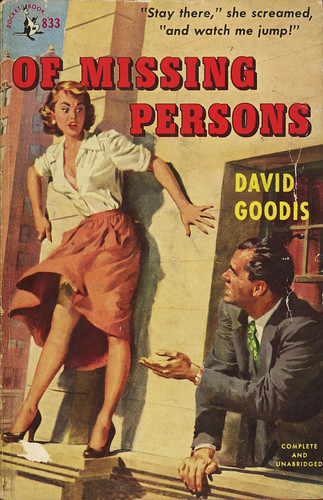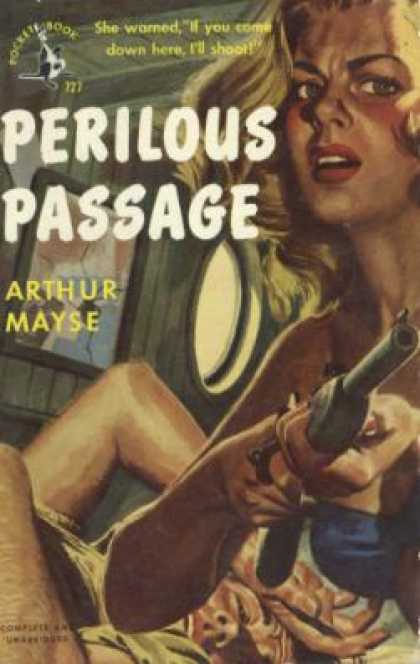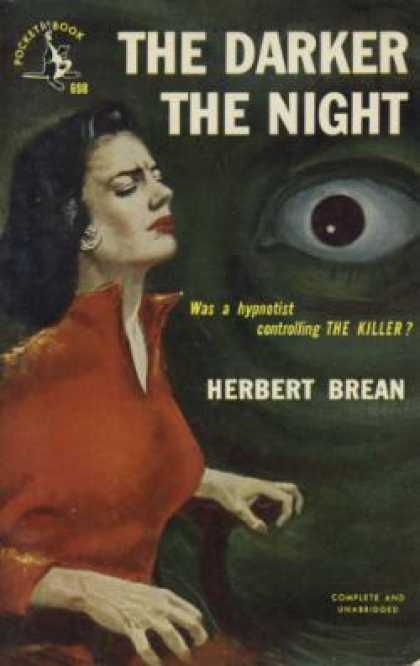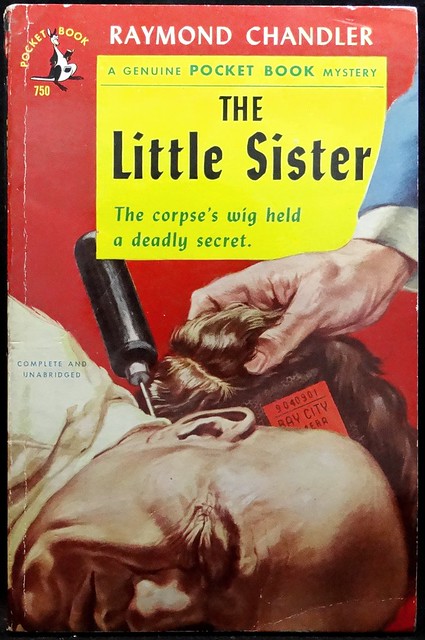山岸凉子は、1970年代の後半から1980年代の前半にかけて、非常にとんがった作品を描いていた。
私が彼女の作品を読み始めたのは、この年代の作品からで、少女漫画でありながら知的な印象を持つ作品と繊細な絵に魅了されたのが大きい。
「ストロベリー・ナイト・ナイト」も、そんな作品の一つだ。
病院で目覚めた少女が、街を散歩する。
しかし、街にはなぜか異常な光景があふれている。
車を壊す暴徒
草むらでセックスをするカップル
息子を轢き殺され狂気のうちに走り回る母親
酒を飲み小便を垂れ流し泣いている中年男
おもちゃやお菓子を店から奪う子供たち
睡眠薬を飲んで眠る人
大音量で音楽を聴く若者
冷蔵庫の食べ物をひたすら食べる中年男
車で次々と人々を轢き殺すインテリ男
ボロボロの制服を着た警官
やがて、読者は、この街が核ミサイルが落ちる直前の状況下にあることが分かる。
救いようのない世紀末の光景。
しかし、今、読むと、山岸凉子の意図は、おそらく、今まで精神的なトラブルを抱え、病院に入院していた少女が、街を散策し、様々な人々の本性を見て、安心し、その精神的な桎梏から解き放たれる姿を描くことにあったのだと思う。
その瞬間が、たとえ、壊滅寸前の街の中にあったとしても。
彼女の作品には、そんな主人公が多い。
こんなどうしようもない状況下でも、精神的な自由をまっすぐに求めるのだ。
山岸凉子の作品に惹かれるのは、これも理由の一つかもしれない。

2014年12月24日水曜日
2014年12月23日火曜日
現代世界の十大小説/池澤夏樹
タイトルが、若干、大仰すぎる気がするが、簡単に言ってしまうと、現代の世界文学の手引きのような本だ。
その世界文学も、池澤夏樹編集の世界文学全集の作品がベースになっており、これに、「百年の孤独」と「悪童日記」を加えた10の作品のあらすじと作品の特徴、背景などを説明している。
◎ 百年の孤独 / ガルシア・マルケス
◎ 悪童日記 / アゴタ・クリストフ
◎ マイトレイ / ミルチャ・エリアーデ
◎ サルガッソーの広い海 / ジーン・リース
◎ フライデーあるいは太平洋の冥界 / ミシェル・トゥルニエ
◎ 老いぼれグリンゴ / カルロス・フエンテス
◎ クーデター / ジョン・アップダイク
◎ アメリカの鳥 / メアリー・マッカーシー
◎ 戦争の悲しみ / バオ・ニン
◎ 苦海浄土 / 石牟礼 道子
これをみると、南米コロンビア、ハンガリー、ルーマニア、インド、ドミニカ、ジャマイカ、イギリス、パリ、南洋の島、パナマ、メキシコ、アメリカ、アフリカのどこかの国、フランス、ベトナム、日本と、様々な国に触れていて、いわゆる昔の世界文学全集の大半を占める欧米、ロシア文学の偏りとは対照的な構成になっている。
池澤夏樹 個人編集の世界文学全集は、「即戦力の文学」、「国境、言語を超えた普遍性」、「世界そのものを直接理解できるような資質」を持つ作品という基準で選択された。
そして、第二次世界大戦後、それまで抑圧の中にいた二つの存在である「植民地」の人々と「女性」の強い表現意欲によって書かれた作品ということらしい。
この2つの要素は、ポストコロリアリズム(植民地主義以降)、フェミニズムという言葉で説明されている。
ポストコロリアリズムと言われても、ピンとこないのが普通の日本人だと思うが、紹介された作品を読んでいくと、世界には、国境があり、出身国による階級があり、他人の前では、自分のアイデンティティを説明しなければならない場面がある。
むしろ、それが普通なのだということが分かる。
ある意味、これらの作品には、日本という国を客観的に見るための見識と教養が詰まっていると言ってもいいかもしれない。
本書の末尾でも書かれていたが、小説という媒体は、相当のことができるのだなという気がする。
その特徴を、池澤さんは、「ぼくたちが考えるたいていの問題は小説という思考のツールによって解決とは行かないまでも記述と解析ができる」と評している。
また、一つの問題について賛成・反対の両論併記ができる点と、百年という時間も扱うことが可能であるという点も。
小説という媒体は、まだまだ捨てたものではない、そんな気がしてくる。
その世界文学も、池澤夏樹編集の世界文学全集の作品がベースになっており、これに、「百年の孤独」と「悪童日記」を加えた10の作品のあらすじと作品の特徴、背景などを説明している。
◎ 百年の孤独 / ガルシア・マルケス
◎ 悪童日記 / アゴタ・クリストフ
◎ マイトレイ / ミルチャ・エリアーデ
◎ サルガッソーの広い海 / ジーン・リース
◎ フライデーあるいは太平洋の冥界 / ミシェル・トゥルニエ
◎ 老いぼれグリンゴ / カルロス・フエンテス
◎ クーデター / ジョン・アップダイク
◎ アメリカの鳥 / メアリー・マッカーシー
◎ 戦争の悲しみ / バオ・ニン
◎ 苦海浄土 / 石牟礼 道子
面白いのは、各々の作品の扉のページに、作者の顔写真と生まれた国、作品の舞台となった国が表示された世界地図が掲載されているところだ。
これをみると、南米コロンビア、ハンガリー、ルーマニア、インド、ドミニカ、ジャマイカ、イギリス、パリ、南洋の島、パナマ、メキシコ、アメリカ、アフリカのどこかの国、フランス、ベトナム、日本と、様々な国に触れていて、いわゆる昔の世界文学全集の大半を占める欧米、ロシア文学の偏りとは対照的な構成になっている。
池澤夏樹 個人編集の世界文学全集は、「即戦力の文学」、「国境、言語を超えた普遍性」、「世界そのものを直接理解できるような資質」を持つ作品という基準で選択された。
そして、第二次世界大戦後、それまで抑圧の中にいた二つの存在である「植民地」の人々と「女性」の強い表現意欲によって書かれた作品ということらしい。
この2つの要素は、ポストコロリアリズム(植民地主義以降)、フェミニズムという言葉で説明されている。
ポストコロリアリズムと言われても、ピンとこないのが普通の日本人だと思うが、紹介された作品を読んでいくと、世界には、国境があり、出身国による階級があり、他人の前では、自分のアイデンティティを説明しなければならない場面がある。
むしろ、それが普通なのだということが分かる。
ある意味、これらの作品には、日本という国を客観的に見るための見識と教養が詰まっていると言ってもいいかもしれない。
本書の末尾でも書かれていたが、小説という媒体は、相当のことができるのだなという気がする。
その特徴を、池澤さんは、「ぼくたちが考えるたいていの問題は小説という思考のツールによって解決とは行かないまでも記述と解析ができる」と評している。
また、一つの問題について賛成・反対の両論併記ができる点と、百年という時間も扱うことが可能であるという点も。
小説という媒体は、まだまだ捨てたものではない、そんな気がしてくる。
2014年12月21日日曜日
NHKスペシャルメルトダウン File.5 知られざる大量放出
東京電力福島第一原子力発電所事故で起きた放射能大量放出の検証を行った番組だ。
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/1221/index.html
放射能大量放出が起きていたのは、1号機から3号機までの原子炉が次々にメルトダウンした2011年3月11日から15日午前中までの4日間ではなく、15日午後から2週間の間だったというのだ。
最初の4日間の放出量は全体の25%程度だが、その後の2週間の放出量は75%に相当するものだったらしい。
(事故調査委員会が集中的に検証していたのも、メルトダウンが起きていた4日間だけだった)
大量放出は、3号機の格納器で起きたらしい。原因は3つある。
1点目は、メルトダウンを起こした3号機の格納器への消防車による注水が上手く行かなかったこと。
消防車からは1時間当たり30トンの水を送り込んでいたが、実際には1トン程度のわずかな水しか注水できなかったようだ。
その原因は、18カ所も水の抜け道があったこと、途中のポンプが上手く機能しなかったことがあるらしい。
さらに悪いことには、わずかな注水により、水蒸気が格納容器の中に充満し、高温の時間が長引き、燃料棒の損傷をさらに激しくしていた可能性があるということだった。(番組の実験検証による)
これが本当だとすると、わずかな注水がさらにメルトダウンを加速してしまったという衝撃の事実だ。
2点目は、3月15日に行った5回目のベントだ。
このベントで、放射性ヨウ素131が、大量に放出(全体の放出量の10%)されてしまった。
ベントとは、格納容器を保護するため、容器内の圧力を下げることを目的に、放射性物質を含む気体を水でクリーニングし、放射能の濃度を下げた上で、、外部に放出することだ。
本来であれば、水で放射性物質はクリーニングされるはずであるが、水が高温になると、その機能が働かなくなる。
さらに、今回の番組の実験検証では、1回から4回のベントを繰り返すうちに、水が配管のなかに溜まりはじめ、それに管内の大量のヨウ素が付着し、5回目のベントの蒸気が外に押し出してしまったのではないかという推測をしている。
3点目は、4号機格納プールのメルトダウンのリスクを過大評価し、上空からの放水作業を優先してしまい、地震により喪失した各原子炉を冷却するための電源の復旧工事を遅らせてしまったという人的判断のミスだ。
放射能の大量放出が収まったのは3月末頃だが、これはその頃にようやく電源が回復したことが要因だったらしい。つまり、電源の復旧がもっと早くに出来ていれば、放出も早く収まっていたということだ。
なぜ、そのような優先順位の判断になってしまったか。大きな原因としては、事故対応策の決定権が3月15日以降、現場から東電本店に設置された政府関係者も入った統合本部に移管されてしまったことだ。
4号機格納プールには水があった。そして、実は水があるらしいということは、現場では自衛隊の上空撮影の映像で把握していたらしいのだが、政府関係者は、少ない情報しか保有していないアメリカ側から、4号機には水がないに違いない、メルトダウンが起きる危険が高いと再三、脅かされていたらしい。
その結果、本来であれば、最優先されるべき電源復旧が後回しにされ、4号機格納プールへの放水が優先されてしまった。この度重なる放水で、電源復旧の工事は大幅に遅れてしまったらしい。
(3月22日にようやく電源の復旧は本格的にできた)
番組を見て、しみじみと思ったのは、何故、こんなにも対応が裏目裏目に出てしまったのだろうと不思議になるくらい、ほとんどが失敗に終わっているということだ。
しかし、想定外の緊急事態発生時に、人が出来ることは所詮この程度のことだということが実証されたという気もする。
番組でも、NHK解説員が述べていたが、原発に100%の安全はないという結論に落ち着くと思う。
今の政府は、原発再稼働にばかり力を注いでいるが、今後、本当に原発を再稼働し、その事故のリスクを軽減したいのであれば、福島の事故の全体像の検証を継続的に行うべきだ。
それがレベル7という最も深刻な事故を起こしてしまった国の責任というものだろう。
なお、一つ気になったのは、今年3月16日に放映していた同じシリーズの番組「メルトダウン File.4 放射能”大量放出”の真相」では、爆発を起こさなかった2号機から継続的に大量の放射能放出が起きていたと放映していたことだ。
http://gold-blue-lion-by-shirayukimaru.blogspot.jp/2014/03/nhk.html
(私のブログだけでは信頼性がないので以下のブログも参考まで掲載)
http://d.hatena.ne.jp/cangael/20140320/1395273547
今回のFile.5が3号機からの大量放出が75%と言っている気がするので、前回の番組とは若干、事実の説明が異なっている。これについては何らかのコメントがほしかったと思う。
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/1221/index.html
放射能大量放出が起きていたのは、1号機から3号機までの原子炉が次々にメルトダウンした2011年3月11日から15日午前中までの4日間ではなく、15日午後から2週間の間だったというのだ。
最初の4日間の放出量は全体の25%程度だが、その後の2週間の放出量は75%に相当するものだったらしい。
(事故調査委員会が集中的に検証していたのも、メルトダウンが起きていた4日間だけだった)
大量放出は、3号機の格納器で起きたらしい。原因は3つある。
1点目は、メルトダウンを起こした3号機の格納器への消防車による注水が上手く行かなかったこと。
消防車からは1時間当たり30トンの水を送り込んでいたが、実際には1トン程度のわずかな水しか注水できなかったようだ。
その原因は、18カ所も水の抜け道があったこと、途中のポンプが上手く機能しなかったことがあるらしい。
さらに悪いことには、わずかな注水により、水蒸気が格納容器の中に充満し、高温の時間が長引き、燃料棒の損傷をさらに激しくしていた可能性があるということだった。(番組の実験検証による)
これが本当だとすると、わずかな注水がさらにメルトダウンを加速してしまったという衝撃の事実だ。
2点目は、3月15日に行った5回目のベントだ。
このベントで、放射性ヨウ素131が、大量に放出(全体の放出量の10%)されてしまった。
ベントとは、格納容器を保護するため、容器内の圧力を下げることを目的に、放射性物質を含む気体を水でクリーニングし、放射能の濃度を下げた上で、、外部に放出することだ。
本来であれば、水で放射性物質はクリーニングされるはずであるが、水が高温になると、その機能が働かなくなる。
さらに、今回の番組の実験検証では、1回から4回のベントを繰り返すうちに、水が配管のなかに溜まりはじめ、それに管内の大量のヨウ素が付着し、5回目のベントの蒸気が外に押し出してしまったのではないかという推測をしている。
3点目は、4号機格納プールのメルトダウンのリスクを過大評価し、上空からの放水作業を優先してしまい、地震により喪失した各原子炉を冷却するための電源の復旧工事を遅らせてしまったという人的判断のミスだ。
放射能の大量放出が収まったのは3月末頃だが、これはその頃にようやく電源が回復したことが要因だったらしい。つまり、電源の復旧がもっと早くに出来ていれば、放出も早く収まっていたということだ。
なぜ、そのような優先順位の判断になってしまったか。大きな原因としては、事故対応策の決定権が3月15日以降、現場から東電本店に設置された政府関係者も入った統合本部に移管されてしまったことだ。
4号機格納プールには水があった。そして、実は水があるらしいということは、現場では自衛隊の上空撮影の映像で把握していたらしいのだが、政府関係者は、少ない情報しか保有していないアメリカ側から、4号機には水がないに違いない、メルトダウンが起きる危険が高いと再三、脅かされていたらしい。
その結果、本来であれば、最優先されるべき電源復旧が後回しにされ、4号機格納プールへの放水が優先されてしまった。この度重なる放水で、電源復旧の工事は大幅に遅れてしまったらしい。
(3月22日にようやく電源の復旧は本格的にできた)
番組を見て、しみじみと思ったのは、何故、こんなにも対応が裏目裏目に出てしまったのだろうと不思議になるくらい、ほとんどが失敗に終わっているということだ。
しかし、想定外の緊急事態発生時に、人が出来ることは所詮この程度のことだということが実証されたという気もする。
番組でも、NHK解説員が述べていたが、原発に100%の安全はないという結論に落ち着くと思う。
今の政府は、原発再稼働にばかり力を注いでいるが、今後、本当に原発を再稼働し、その事故のリスクを軽減したいのであれば、福島の事故の全体像の検証を継続的に行うべきだ。
それがレベル7という最も深刻な事故を起こしてしまった国の責任というものだろう。
なお、一つ気になったのは、今年3月16日に放映していた同じシリーズの番組「メルトダウン File.4 放射能”大量放出”の真相」では、爆発を起こさなかった2号機から継続的に大量の放射能放出が起きていたと放映していたことだ。
http://gold-blue-lion-by-shirayukimaru.blogspot.jp/2014/03/nhk.html
(私のブログだけでは信頼性がないので以下のブログも参考まで掲載)
http://d.hatena.ne.jp/cangael/20140320/1395273547
今回のFile.5が3号機からの大量放出が75%と言っている気がするので、前回の番組とは若干、事実の説明が異なっている。これについては何らかのコメントがほしかったと思う。
2014年12月18日木曜日
半分は表紙が目的だった 100冊のペーパーバックスにアメリカを読む/片岡義男
片岡義男が、買い集めた大量のペーパーバックス*(Paper backs)の中から100冊選び、その個性的な表紙を写真に撮ったものを左ページに掲載し、右ページに短い文を添えた本だ。
*安価な紙に印刷され、ハードカバーの様に皮や布や厚紙による表紙を用いていない形態の本
この本で取り上げられているペーパーバックスは、アメリカのペーパーバック専門出版社であるポケット・ブックス社の1940年代から1960年代半ばまでのものだが、今、私たちが書店で目にするペーパーバックスとは全然趣きが違う。
絵が生々しいというか、毒々しく描かれていて、見る者の注意を引きつけることに最大の意識が置かれているのを感じる。
片岡義男は、「一冊ずつみな違うとは、一冊ずつ商業主義が発揮され、その結果としてどの表紙もみな個性的だった。アメリカのペーパーバックの表紙が、たとえばいまでもドイツの文学作品のペーパーバックスがそうであるように、商業主義のいっさいない、きわめて真面目でそっけないものだったら、おそらく僕はペーパーバックスを買うことはしなかったはずだ」と述べている。
本書で取り上げられていた表紙をちょっとだけ紹介
*安価な紙に印刷され、ハードカバーの様に皮や布や厚紙による表紙を用いていない形態の本
この本で取り上げられているペーパーバックスは、アメリカのペーパーバック専門出版社であるポケット・ブックス社の1940年代から1960年代半ばまでのものだが、今、私たちが書店で目にするペーパーバックスとは全然趣きが違う。
絵が生々しいというか、毒々しく描かれていて、見る者の注意を引きつけることに最大の意識が置かれているのを感じる。
片岡義男は、「一冊ずつみな違うとは、一冊ずつ商業主義が発揮され、その結果としてどの表紙もみな個性的だった。アメリカのペーパーバックの表紙が、たとえばいまでもドイツの文学作品のペーパーバックスがそうであるように、商業主義のいっさいない、きわめて真面目でそっけないものだったら、おそらく僕はペーパーバックスを買うことはしなかったはずだ」と述べている。
本書で取り上げられていた表紙をちょっとだけ紹介
インパクトがある絵です。
こんな拳で殴られたら、痛そう。。。
ヒッチコックの映画の場面にありそうな絵柄
女性の胸元と膝元がセクシーです。
こちらも、映画のワンシーンのようだ。
She warned "if you come down here, I'll shoot!"
「キャビンに入ってきたら撃つわよ!」という科白が表紙上に印刷されている
目が怖い
チャンドラーのリトルシスター(かわいい女)
かつらと氷かきがインパクトがある
こちらもチャンドラーのロング・グッドバイ(長いお別れ)
ダンサーズのテラスの外、ロールスロイスに乗ったテリー・レノックスとシルヴィアか。
2014年12月17日水曜日
爆弾をかかえたアナーキストのように
爆弾をかかえたアナーキストのように冬がやってきた。
Winter came in like an anarchist with bomb.
エド・マクベインの87分署シリーズ3作目「麻薬密売人」の書き出しの文章が、あまりにもぴったりの一日。
皆様、体をご自愛ください。
Winter came in like an anarchist with bomb.
エド・マクベインの87分署シリーズ3作目「麻薬密売人」の書き出しの文章が、あまりにもぴったりの一日。
皆様、体をご自愛ください。
2014年12月15日月曜日
衆議院選挙結果を受けて
今回の選挙結果は、予想どおりとはいえ、自公政権に、法案の再可決や、憲法改正の発議に必要な、3分の2の定数を超える議席を与えるという結果になったことに、あらためて、げんなりとしてしまった。
政治資金の使途で散々騒がれた議員に、早々に当確が出るのにも驚いた。
(あれは、やはり観劇等でお世話になった利害関係者が全面的にバックアップした結果なのだろうか。常識では考えられない。)
本当に経済さえ、金さえ儲ければ、憲法を改正させてよいのか、平和主義を捨てて戦争ができる国になってよいのか、あれだけひどい原発事故が起こりながら、しかもその事故が収束せず、原因究明と対策もおろそかで、いまだに避難している人々が大勢いる中、全国の原発を次々に再稼働させてよいのか、金より大事なものがあるんじゃないのか、そういう疑念がふつふつと湧いてくる。
本当に、この国は危ないんじゃないか。
あらためて、そう思わされた選挙結果だった。
そういう中で、明確な民意が感じられたのは、自民が全ての選挙区で敗北した沖縄県だけだった。
明確な民意とは、いつまでアメリカの言いなりになって沖縄に基地負担をさせるのか、ということについての明確な拒否の意思表示だ。
原発再稼働に反対して当然の地域で自民が勝利しているのと比較すると際立っている。
唯一、沖縄に明るいきざしを見た。
それが今回の選挙に対する感想です。
政治資金の使途で散々騒がれた議員に、早々に当確が出るのにも驚いた。
(あれは、やはり観劇等でお世話になった利害関係者が全面的にバックアップした結果なのだろうか。常識では考えられない。)
本当に経済さえ、金さえ儲ければ、憲法を改正させてよいのか、平和主義を捨てて戦争ができる国になってよいのか、あれだけひどい原発事故が起こりながら、しかもその事故が収束せず、原因究明と対策もおろそかで、いまだに避難している人々が大勢いる中、全国の原発を次々に再稼働させてよいのか、金より大事なものがあるんじゃないのか、そういう疑念がふつふつと湧いてくる。
本当に、この国は危ないんじゃないか。
あらためて、そう思わされた選挙結果だった。
そういう中で、明確な民意が感じられたのは、自民が全ての選挙区で敗北した沖縄県だけだった。
明確な民意とは、いつまでアメリカの言いなりになって沖縄に基地負担をさせるのか、ということについての明確な拒否の意思表示だ。
原発再稼働に反対して当然の地域で自民が勝利しているのと比較すると際立っている。
唯一、沖縄に明るいきざしを見た。
それが今回の選挙に対する感想です。
2014年12月14日日曜日
街場の戦争論/内田 樹 その2
本書では、日本は主権国家ではなく、アメリカの従属国であるという事実を明確に述べている。
一つは、重要政策について、アメリカの許可なくして自主的に決定できないこと、そして、もっと重要なことは、従属国である事実それ自体を隠ぺいしていることを指摘している。
戦後70年間で、日本の従属的環境は変化していないけれど、従属的マインドは変化してきているという。
1960年代までの政治家は、自分たちは敗戦国民であり、アメリカに面従腹背する以外に生きる道がないというリアルな現実認識があった。
しかし、戦後三代、対米従属を続けているうちに、対米従属それ自体が、不本意なことでも、屈辱的なことでもなくなってきてしまった。
そして、本書「街場の戦争論」では、従属国の政治目標は、「主権の回復」しかなく、そのためには「独立とはどのような状態なのか」を考えないといけない、と述べている。
また、その手がかりは、敗戦以前の、日本がまだ主権国家だった時の日本人の心の中にしかない、彼らが何を感じ、どんな風に思考していたのかを遡及的に探ることが「主権回復」のためのさしあたりもっとも確実で、もっとも筋の通った処方ではないかと述べている。
一つは、重要政策について、アメリカの許可なくして自主的に決定できないこと、そして、もっと重要なことは、従属国である事実それ自体を隠ぺいしていることを指摘している。
戦後70年間で、日本の従属的環境は変化していないけれど、従属的マインドは変化してきているという。
1960年代までの政治家は、自分たちは敗戦国民であり、アメリカに面従腹背する以外に生きる道がないというリアルな現実認識があった。
しかし、戦後三代、対米従属を続けているうちに、対米従属それ自体が、不本意なことでも、屈辱的なことでもなくなってきてしまった。
「アメリカに従属的であればあるほど個人においては日々の生活が快適になる。」これが従属マインドの完成ということなんだと思います。そして、日本人の対米従属の心理を説明している。
強者によって奴隷の地位に落とされるという事実をまっすぐに見つめているかぎり主体性は揺るがない。ところが、その立場にしだいに慣れてくると、自分は自主的にこのような立場を選んだのであると思うようになる。そしてついには従属しているという事実そのものがおのれの主体性と自由を基礎づけているという倒錯したロジックを平然と語るようになる。そのとき主体性は根こそぎ破壊される。日本人は今そうなっている。私は、このくだりを読んでいて、久々に、林達夫の著書「共産主義的人間」にある、1950年に書かれた小文「新しき幕開け」を思い出した。
私はあの八月十五日全面降伏の報をきいたとき、文字通り滂沱として涙をとどめ得なかった。…私の心眼は日本の全過去と全未来をありありと見てとってしまったのである。「日本よ、さらば」、それが私の感慨であり、心の心棒がそのとき音もなく真二つに折れてしまった。
…日本のアメリカ化は必至なものに思われた。新しき日本とはアメリカ化される日本のことだろう――
その時から早くも五年、私の杞憂は不幸にして悉く次から次へと適中した。その五年間最も驚くべきことの一つは、日本の問題がOccupied Japan問題であるという一番明瞭な、一番肝心な点を伏せた政治や文化に関する言動が圧倒的に風靡していたことである。この Occupied抜きのJapan議論ほど間の抜けた、ふざけたものはない。終戦の5年後にして、このような風潮がすでにあったことが分かる文章だが、内田氏が指摘していることと同じだと思う。
そして、本書「街場の戦争論」では、従属国の政治目標は、「主権の回復」しかなく、そのためには「独立とはどのような状態なのか」を考えないといけない、と述べている。
また、その手がかりは、敗戦以前の、日本がまだ主権国家だった時の日本人の心の中にしかない、彼らが何を感じ、どんな風に思考していたのかを遡及的に探ることが「主権回復」のためのさしあたりもっとも確実で、もっとも筋の通った処方ではないかと述べている。
2014年12月13日土曜日
街場の戦争論/内田 樹
内田樹の街場シリーズを読むと気づかされることが多いが、今回も例外ではなかった。
安倍政権は「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と考えている、というこの一言で、安倍政権と日本国民の実態が、とてもよく理解できた。
株式会社が最優先すること、それは利益である。
→アベノミクス
利益を上げるために、経営者の視点からみて、できるだけ低賃金で高能力の人材と、使いやすい労働制度を求める。
→グローバル人材の教育推進、残業代ゼロ法案、労働者派遣法改正
より多くの利益を求めるため、効率性を重視する。その効率性を阻害するものを排除する。
→議論と手続を重んじる民主制、立憲主義を否定し、独裁制にする
(意思決定が速く経営が上手いワンマン社長のイメージ)
→特定秘密保護法案の強行採決(事実上の憲法21条(表現・思想の自由)の廃絶)、
集団的自衛権行使を可能とする閣議決定(事実上の憲法9条の廃絶)
株式会社は有限責任
→倒産した会社(大日本帝国)が負っている負債(戦争責任)を引き継がない
(戦争をしたのは私たちではなく先行世代であるという自民党の政治家の発言)
(本書でも述べられている通り、国家はまさに無限責任でなければならない)
考えを同じくするグローバル企業(輸出企業)を優遇する
→法人税減税法案、原発再稼働
そしてそういうビジネスマン的な考えに慣れた(サラリーマンとして飼いならされた)国民の過半数が、企業の収益の最大化のためなら、自分たちの安全や健康、思想や自由を犠牲に差し出してもかまわないと考えているという説明は、実に明快だ。
それが、最近の新聞報道にあった圧倒的な自公優勢の選挙結果の予想なのだろう。
本書では、内田氏が、安倍政権の日本の今後を以下のとおり予測している。
・独裁的な政体
・平和主義外交の終わり
本書冒頭の「私たちが今いるのは、負けた戦争と、これから起こる次の戦争にはさまれた戦争間期ではないか」という内田氏の予感が、現実のものとならないことを心から願う。
週刊プレイボーイ掲載の『街場の戦争論』についてのインタビュー
http://blog.tatsuru.com/2014/12/10_1617.php
安倍政権は「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と考えている、というこの一言で、安倍政権と日本国民の実態が、とてもよく理解できた。
株式会社が最優先すること、それは利益である。
→アベノミクス
利益を上げるために、経営者の視点からみて、できるだけ低賃金で高能力の人材と、使いやすい労働制度を求める。
→グローバル人材の教育推進、残業代ゼロ法案、労働者派遣法改正
より多くの利益を求めるため、効率性を重視する。その効率性を阻害するものを排除する。
→議論と手続を重んじる民主制、立憲主義を否定し、独裁制にする
(意思決定が速く経営が上手いワンマン社長のイメージ)
→特定秘密保護法案の強行採決(事実上の憲法21条(表現・思想の自由)の廃絶)、
集団的自衛権行使を可能とする閣議決定(事実上の憲法9条の廃絶)
株式会社は有限責任
→倒産した会社(大日本帝国)が負っている負債(戦争責任)を引き継がない
(戦争をしたのは私たちではなく先行世代であるという自民党の政治家の発言)
(本書でも述べられている通り、国家はまさに無限責任でなければならない)
考えを同じくするグローバル企業(輸出企業)を優遇する
→法人税減税法案、原発再稼働
そしてそういうビジネスマン的な考えに慣れた(サラリーマンとして飼いならされた)国民の過半数が、企業の収益の最大化のためなら、自分たちの安全や健康、思想や自由を犠牲に差し出してもかまわないと考えているという説明は、実に明快だ。
それが、最近の新聞報道にあった圧倒的な自公優勢の選挙結果の予想なのだろう。
本書では、内田氏が、安倍政権の日本の今後を以下のとおり予測している。
・独裁的な政体
・平和主義外交の終わり
本書冒頭の「私たちが今いるのは、負けた戦争と、これから起こる次の戦争にはさまれた戦争間期ではないか」という内田氏の予感が、現実のものとならないことを心から願う。
週刊プレイボーイ掲載の『街場の戦争論』についてのインタビュー
http://blog.tatsuru.com/2014/12/10_1617.php
安倍さんたちが目指しているのは、北朝鮮とシンガポールを合わせたような国だと思います。政治的には北朝鮮がモデルです。市民に政治的自由がなく、強権的な支配体制で、自前の核戦力があって国際社会に対して強面ができる国になりたいと思っている。経済的な理想はシンガポールでしょう。国家目標が経済成長で、あらゆる社会制度が金儲けしやすいように設計されている国にしたい。
2014年12月8日月曜日
絵本についての、僕の本/片岡義男
冒頭の片岡義男の絵本に関する説明がいい。
絵本とは、ごく簡単に言うなら、現実にはどこを探しても存在していない世界のことだ。それは想像力によって頭の中に作られていく世界だ。一冊の絵本という具体物とはまったく別に、その絵本をきっかけにして、僕の想像力は刺激を受け、その刺激によって、頭のなか以外のどこにもない世界を、作っていく。
幼い子供は、自分の頭のなかに想像力というものを作らなければいけないことを、本能的に知っているのだと僕は思う。身のまわりにあるものをとおして、幼児は必死に想像力を育てる。この本能的な必死さを、すっかり失ってしまった人たちが、いわゆる大人と呼ばれる人たちなのだろう。
本書で紹介されている本は、すべて英語圏の絵本というところが、片岡義男らしいと言えば、それまでだが、若干残念ではある。
面白いのは、片岡が絵本について、ただ単に可愛い、愛らしい、楽しい、愉快な夢のような世界を提示するだけのものではなく、社会の基本的な理念に沿って、子供たちを厳しく教育していくという教科書的な役割を重視している点だ。
ABC、文章の構成、数の数え方などを教えるのはもちろん、子供たちが個人的な主観の世界から抜け出て、社会のなかで普遍的に機能する価値観や理念を、しっかりと身につけるために、絵本の役割はあるという考え方が述べられている。
本書は、片岡が趣味でコレクション的に集めた絵本を、オシャレな感じでまとめただけの本のように見えるが、実は日本の教育の現状と、理念がない社会について、質の高い絵本を豊富に生み出し続けている英語圏社会と比較し警鐘を鳴らしている、とても硬派な本なのだと思う。
2014年12月7日日曜日
12月14日 衆議院選挙について
読売新聞12月4日の朝刊では、自公300超す勢いとの見出しが新聞の一面に出ていた。
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/news2/20141203-OYT1T50109.html
他の新聞社も、ほぼ同じ予想結果を掲載している。
朝日新聞 自民300議席超える勢い
http://www.asahi.com/articles/ASGD376BZGD3UZPS01L.html
毎日新聞 自民300議席超す勢い
http://mainichi.jp/select/news/20141204k0000e010124000c.html
日本経済新聞 自民、300議席うかがう
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H4I_T01C14A2MM8000/
現在は、自民党、公明党の与党の議席数を合わせると、326議席。
今度の衆議院選挙後の総議席数が475なので、その3分の2にあたる317議席を自公が獲得すれば、参議院で法案を否決しても、衆議院で再議決すれば、法律を成立することができることになる。
普通、選挙序盤でこのような報道をすると、その反動で、野党に投票する傾向になると言われるが、自民党支持の姿勢を鮮明に打ち出している読売新聞が、このような記事を一面に掲載した意図を考えると、そのような揺り戻しは起こらず、自公が勝利するのは手堅いと見越しているからなのかもしれない。
振り返れば、特定秘密保護法(12月10日施行)の強行採決、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、国会での十分な議論のプロセスを経ずに、日本国憲法の基本理念である平和主義、国民の知る権利を脅かすような安倍政権の危険な一面が見えた2年間だった。
そもそも、今回の衆議院選挙は、消費税増税を延期することで、安倍政権が推し進める経済政策 アベノミクスの信を問うというのが建前らしいが、読売新聞の読み通り、今回、自公が300を超すような議席を獲得できる結果になれば、間違いなく、安倍政権は、「国民の信を得た」という姿勢で、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制の整備、さらには、憲法9条の改正、原発再稼働、沖縄の辺野古埋め立てなどを、今まで以上に強引に推し進めることになるのだろう。
そう予想する人は少なくないはずだから、安倍政権への反対、牽制のため、今回の選挙で、少なくとも自民党の議席数は減るだろうと私は思っていたのだが、全くの見込み違いだったらしい。
党首討論で安倍首相がボードに書いていた
この道しか無い
安倍首相の発言を見ると、「この道」には、単にアベノミクスだけではなく、安全保障法制も含んだ今まで安倍政権が推し進めてきた主要な政策という意味合いも込められているようだ。
「この道」の先に、果たして何があるのか、よくよく考えて投票する
そう、私に思わせてくれた世論調査の結果だった。
*哲学者 内田 樹さんの共同通信のインタビュー
http://blog.tatsuru.com/2014/12/05_0858.php
――安倍政権はグローバル企業の収益増大のことしか考えていない。そのためには「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と信じている。――
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/news2/20141203-OYT1T50109.html
他の新聞社も、ほぼ同じ予想結果を掲載している。
朝日新聞 自民300議席超える勢い
http://www.asahi.com/articles/ASGD376BZGD3UZPS01L.html
毎日新聞 自民300議席超す勢い
http://mainichi.jp/select/news/20141204k0000e010124000c.html
日本経済新聞 自民、300議席うかがう
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H4I_T01C14A2MM8000/
現在は、自民党、公明党の与党の議席数を合わせると、326議席。
今度の衆議院選挙後の総議席数が475なので、その3分の2にあたる317議席を自公が獲得すれば、参議院で法案を否決しても、衆議院で再議決すれば、法律を成立することができることになる。
普通、選挙序盤でこのような報道をすると、その反動で、野党に投票する傾向になると言われるが、自民党支持の姿勢を鮮明に打ち出している読売新聞が、このような記事を一面に掲載した意図を考えると、そのような揺り戻しは起こらず、自公が勝利するのは手堅いと見越しているからなのかもしれない。
振り返れば、特定秘密保護法(12月10日施行)の強行採決、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、国会での十分な議論のプロセスを経ずに、日本国憲法の基本理念である平和主義、国民の知る権利を脅かすような安倍政権の危険な一面が見えた2年間だった。
そもそも、今回の衆議院選挙は、消費税増税を延期することで、安倍政権が推し進める経済政策 アベノミクスの信を問うというのが建前らしいが、読売新聞の読み通り、今回、自公が300を超すような議席を獲得できる結果になれば、間違いなく、安倍政権は、「国民の信を得た」という姿勢で、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制の整備、さらには、憲法9条の改正、原発再稼働、沖縄の辺野古埋め立てなどを、今まで以上に強引に推し進めることになるのだろう。
そう予想する人は少なくないはずだから、安倍政権への反対、牽制のため、今回の選挙で、少なくとも自民党の議席数は減るだろうと私は思っていたのだが、全くの見込み違いだったらしい。
党首討論で安倍首相がボードに書いていた
この道しか無い
安倍首相の発言を見ると、「この道」には、単にアベノミクスだけではなく、安全保障法制も含んだ今まで安倍政権が推し進めてきた主要な政策という意味合いも込められているようだ。
「この道」の先に、果たして何があるのか、よくよく考えて投票する
そう、私に思わせてくれた世論調査の結果だった。
*哲学者 内田 樹さんの共同通信のインタビュー
http://blog.tatsuru.com/2014/12/05_0858.php
――安倍政権はグローバル企業の収益増大のことしか考えていない。そのためには「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と信じている。――
2014年11月30日日曜日
アメリカに生きる彼女たち/片岡義男
1949年から1995年までのアメリカの雑誌広告に描かれた女性像の変遷を考察している本だ。
広告は、言ってしまえば、人々の購買意欲、欲望を煽り立てる力を持たなければならない。そして、その有効な道具として、女性の美しさが様々な姿で表現されていることが実感できる。
・1949年
日本がまだ戦後の復興中の頃、アメリカは人類史上初めての異常事態ともいうべき、豊かさと力を持った。広告の中で、いろどりを添える女性らしい女性たちが広告に描かれている(この頃はまだ絵)。
・1950年代
この年代の広告において、女性は、人間関係の中、主役として機能している姿が多く描かれていると片岡義男は観察している。この「人間関係」ということばに関する片岡の説明が面白い。
この頃から、写真が使われているが、有色人種の女性の登場はない。
・1960年代
家庭において、主役的な触媒として機能することを、社会システムから期待されていた女性たちがファミリー・ポートレートとして多く描かれている。
・1970年代
働く自立した女性たちが広告の前面に描かれる存在となる。印象に残ったのは、ウィンストンの煙草の広告。女性がカメラを真っ直ぐに見据えながら、笑顔もみせず、きりっとした感じで箱から煙草を一本抜き出す姿が描かれている。
黒人の女性の広告が現れる。
・1980年代
女性の身体、肉体が生に表現されるようになる。社会の構造、家庭、人のあり方という堅牢な枠組みが溶けはじめ、解体され、身体に視点がフォーカスされる。印象に残ったのは、女性の脚の美しさを描いている広告だ。彼女の傍には、その脚に見とれる男性が配置されている。男性の欲望が見えることで、その脚が引き出す欲望が増幅されている。
・1990年代
1980年代に完成された美意識が継続している。
是非はともかく、アメリカ陸軍の女性隊員を応募する広告にさえ、完成された美しさがある。
本書に収められている広告の中には、芸術的と評してもおかしくない完成度の高い作品もある。
雑誌をあまり読まない私なので正確なことは言えないが、日本の雑誌広告とは、女性の美しさを活かしたシンプルな訴求力、ウィットという点において、比べ物にならないほど、レベルが高いように思った。
広告は、言ってしまえば、人々の購買意欲、欲望を煽り立てる力を持たなければならない。そして、その有効な道具として、女性の美しさが様々な姿で表現されていることが実感できる。
・1949年
日本がまだ戦後の復興中の頃、アメリカは人類史上初めての異常事態ともいうべき、豊かさと力を持った。広告の中で、いろどりを添える女性らしい女性たちが広告に描かれている(この頃はまだ絵)。
・1950年代
この年代の広告において、女性は、人間関係の中、主役として機能している姿が多く描かれていると片岡義男は観察している。この「人間関係」ということばに関する片岡の説明が面白い。
ペプシコーラの広告八点が描く理想のなかに浮かび上がるもっとも大切なものとは、いったいなにだろうか。それは、関係だ。人と人との、関係だ。人間関係、と日本語で言うと、際限なくわずらわしい、人をどこまでも落ち込ませる、この世のしがらみでしかない。日本における関係は、そのなかに人を閉じ込める。アメリカでは、関係は人を解放する。…あるひとりの人のポテンシャルをフルに引き出すために、関係はある。あるひとりの人にかかわる評価として、もっとも大切なのは、その人がどのような関係を持っているのか、どのような関係を作り得るのか、という能力だ。…アメリカでは転職や転居が多い、としばしば言われている。新しい可能性を求めて移動するわけだが、新しい可能性とは、要するにいまよりもっといい関係のことであり、そのような関係のなかに自分を置き直すことによって、自分の機能を高めることが、移動の最重要な目的となっている。個人主義に基づく自由と民主が、女性たちの全体に、ディテールに現れている。
この頃から、写真が使われているが、有色人種の女性の登場はない。
・1960年代
家庭において、主役的な触媒として機能することを、社会システムから期待されていた女性たちがファミリー・ポートレートとして多く描かれている。
・1970年代
働く自立した女性たちが広告の前面に描かれる存在となる。印象に残ったのは、ウィンストンの煙草の広告。女性がカメラを真っ直ぐに見据えながら、笑顔もみせず、きりっとした感じで箱から煙草を一本抜き出す姿が描かれている。
黒人の女性の広告が現れる。
・1980年代
女性の身体、肉体が生に表現されるようになる。社会の構造、家庭、人のあり方という堅牢な枠組みが溶けはじめ、解体され、身体に視点がフォーカスされる。印象に残ったのは、女性の脚の美しさを描いている広告だ。彼女の傍には、その脚に見とれる男性が配置されている。男性の欲望が見えることで、その脚が引き出す欲望が増幅されている。
・1990年代
1980年代に完成された美意識が継続している。
是非はともかく、アメリカ陸軍の女性隊員を応募する広告にさえ、完成された美しさがある。
本書に収められている広告の中には、芸術的と評してもおかしくない完成度の高い作品もある。
雑誌をあまり読まない私なので正確なことは言えないが、日本の雑誌広告とは、女性の美しさを活かしたシンプルな訴求力、ウィットという点において、比べ物にならないほど、レベルが高いように思った。
2014年11月29日土曜日
古事記 池澤夏樹 訳/日本文学全集 01
池澤夏樹が現代語訳した古事記を読んでみた。
私は、古事記というと日本最古の書物という程度の知識しかなかったが、本書の作られた背景と、その構成は興味深かった。
古事記が作られた最大の理由は、「みなみなの家に伝わる帝紀と旧辞は今では事実を離れてずいぶんと嘘が混じっている」と天武天皇が言い、それがきっかけで、元明天皇の命令により、官僚の太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が、口頭で伝承されていた記録を統合して整理し、文書化したものだということだ。
帝紀は、天皇や豪族の系譜を指し、旧辞は、物語的なものを指すらしい。
そして、古事記は、命令どおり、帝紀と旧辞的なもので構成されており、池澤夏樹の解説では、さらに分かりやすく、大きく3つの要素「系譜」、「神話・伝説」、「歌謡」と説明されている。
古事記の「系譜」は、非常に政治的な匂いがするまとめられ方をしている。
天照大御神(アマテラス)を中心する神々の系統の中央に天皇と子孫たちを置き、地方豪族たちの祖先もその系統に組み込み、神々の威信を利用して、中央集権国家としての統一感を得る。
その作業のために登場する神々だけで312名もいるらしい。
そして、「神話・伝説」については、神々(イザナキとイザナミ)がセックスして、島々(四国・九州地方)と数々の神々が生まれる様子が、明け透け(女性器の名称や、ゲロ・ウンコ・オシッコなど)に書かれていて面白い。
また、天岩戸の神隠れ、スサノヲ伝説、八俣のオロチ、稲羽の白兎、ヤマトタケルの冒険など、なじみのある話が幾つも収められていて、古事記の文学的な面白さが感じられる。
*山岸涼子のマンガを読んでいた人であれば、これらの物語や神々・皇族・豪族の名前について、幾つも読んだことがあるという実感を覚えると思う。
最後の「歌謡」については、私にとっては、万葉集以前にも、こんなにも歌が謡われていたのだなという程度の印象しかなかったが、当時は、言葉というのは音読し、読み聞かせるものだったという証左なのかもしれない。
古事記は、上・中・下巻の3部構成になっているが、上巻は、日本が形作られる神々の世界が中心に描かれており、出雲の神々がアマテラス率いる中央の神々に制圧される話が印象深かった。
中巻は、初代神武天皇から十五代応神天皇までの時代を描いているが、やはり、ヤマトタケルの話が印象深い。
下巻は、十六代仁徳天皇から三十三代推古天皇までを描いている。この下巻から神話性に代わって、儒教的なモラル観が描かれており、話が常識的なものになっている印象を覚える。
意外だったのは、聖徳太子や推古天皇のあたりの話が、さらっと触れる程度で終わっているところだった。
総じていうと、玉石混淆という印象が強く残ったが、現代語の感覚に近い形で、物語を蘇えらせた訳者の池澤夏樹の努力は相当なものだと思う。
私は、古事記というと日本最古の書物という程度の知識しかなかったが、本書の作られた背景と、その構成は興味深かった。
古事記が作られた最大の理由は、「みなみなの家に伝わる帝紀と旧辞は今では事実を離れてずいぶんと嘘が混じっている」と天武天皇が言い、それがきっかけで、元明天皇の命令により、官僚の太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が、口頭で伝承されていた記録を統合して整理し、文書化したものだということだ。
帝紀は、天皇や豪族の系譜を指し、旧辞は、物語的なものを指すらしい。
そして、古事記は、命令どおり、帝紀と旧辞的なもので構成されており、池澤夏樹の解説では、さらに分かりやすく、大きく3つの要素「系譜」、「神話・伝説」、「歌謡」と説明されている。
古事記の「系譜」は、非常に政治的な匂いがするまとめられ方をしている。
天照大御神(アマテラス)を中心する神々の系統の中央に天皇と子孫たちを置き、地方豪族たちの祖先もその系統に組み込み、神々の威信を利用して、中央集権国家としての統一感を得る。
その作業のために登場する神々だけで312名もいるらしい。
そして、「神話・伝説」については、神々(イザナキとイザナミ)がセックスして、島々(四国・九州地方)と数々の神々が生まれる様子が、明け透け(女性器の名称や、ゲロ・ウンコ・オシッコなど)に書かれていて面白い。
また、天岩戸の神隠れ、スサノヲ伝説、八俣のオロチ、稲羽の白兎、ヤマトタケルの冒険など、なじみのある話が幾つも収められていて、古事記の文学的な面白さが感じられる。
*山岸涼子のマンガを読んでいた人であれば、これらの物語や神々・皇族・豪族の名前について、幾つも読んだことがあるという実感を覚えると思う。
最後の「歌謡」については、私にとっては、万葉集以前にも、こんなにも歌が謡われていたのだなという程度の印象しかなかったが、当時は、言葉というのは音読し、読み聞かせるものだったという証左なのかもしれない。
古事記は、上・中・下巻の3部構成になっているが、上巻は、日本が形作られる神々の世界が中心に描かれており、出雲の神々がアマテラス率いる中央の神々に制圧される話が印象深かった。
中巻は、初代神武天皇から十五代応神天皇までの時代を描いているが、やはり、ヤマトタケルの話が印象深い。
下巻は、十六代仁徳天皇から三十三代推古天皇までを描いている。この下巻から神話性に代わって、儒教的なモラル観が描かれており、話が常識的なものになっている印象を覚える。
意外だったのは、聖徳太子や推古天皇のあたりの話が、さらっと触れる程度で終わっているところだった。
総じていうと、玉石混淆という印象が強く残ったが、現代語の感覚に近い形で、物語を蘇えらせた訳者の池澤夏樹の努力は相当なものだと思う。
2014年11月25日火曜日
「日本語の外へ」 「自分と自分以外」/片岡義男
片岡義男の「日本語の外へ」の第2部 日本語の章に書かれている英語と日本語の比較は、私が読んだ本の中では、もっとも、日本語という言語機能に痛烈な批判を投げかけている文章だと思う。
そこで批判されている日本語とは、文学における日本語ではなく、実社会、さらには国際社会において、他者との対立を怖がらず、主体と行動、そして責任を明確にする個人の考えの発信力のことで、これが日本語には決定的に欠けているという痛烈な批判だ。
私は読んでいて、あまりに不安になってしまい、日本語の良さを再確認したくて、丸谷才一の文章読本を改めて読み直したほどだった。
そんな片岡が書いたエッセイ集「自分と自分以外」にも、耳の痛い話が書いてあった。
「私は作家になりたいと思います」という言い方の中にある「と思います」という日本語。
日本語をそのまま英訳してみると分かるのだが、
I think that I would like to become an author. という、あまり見かけない不自然な英文になる。
主語と動詞が二重になっており、煩わしいし、英語世界の人たちからみると、「なりたい」という意思が弱められた文章のように感じる。
おそらく、普通に英訳される際は、「I think」がなくなり、I would like to become an author. だけになるのだろう。
しかし、上記の文章にかぎらず、「と思います」という日本語は、普通の日本人であれば、よく使う言い回しである。
このエッセイでは、日本人がそのような言い回しを使う理由を次のように説明している。
自分が普段使っている言葉や言い回しを、外国語を通して、日本語の外から比較検討してみると、日本語の特徴、その背景にある日本人の姿が現れてくる。
このエッセイは、それに気づかせてくれました。
そこで批判されている日本語とは、文学における日本語ではなく、実社会、さらには国際社会において、他者との対立を怖がらず、主体と行動、そして責任を明確にする個人の考えの発信力のことで、これが日本語には決定的に欠けているという痛烈な批判だ。
私は読んでいて、あまりに不安になってしまい、日本語の良さを再確認したくて、丸谷才一の文章読本を改めて読み直したほどだった。
そんな片岡が書いたエッセイ集「自分と自分以外」にも、耳の痛い話が書いてあった。
「私は作家になりたいと思います」という言い方の中にある「と思います」という日本語。
日本語をそのまま英訳してみると分かるのだが、
I think that I would like to become an author. という、あまり見かけない不自然な英文になる。
主語と動詞が二重になっており、煩わしいし、英語世界の人たちからみると、「なりたい」という意思が弱められた文章のように感じる。
おそらく、普通に英訳される際は、「I think」がなくなり、I would like to become an author. だけになるのだろう。
しかし、上記の文章にかぎらず、「と思います」という日本語は、普通の日本人であれば、よく使う言い回しである。
このエッセイでは、日本人がそのような言い回しを使う理由を次のように説明している。
・自分の断定的な主張を相手に直接ぶつけることを避け、自分の主張によって相手が困ることのないように配慮した言い方が、「と思います」である。
・はっきり主張することを避けて自己責任をあらかじめ軽減しておく工夫であり、この軽減された責任というものが、誰にとっても暗黙の了解という領域を作っている。このような領域がいたるところに配置されていないと、日本人の言語生活は成立しない。
・作家になりたいと言うだけでは、自分の胸のうちが十分に表現されない。「と思います」を文末につけ、初めて、自分の胸のうちが自分のものとして、言いあらわされる気がする。3つ目の理由は、話す人にとっては、それなりに納得できるものなのかもしれませんが、聞く側からすると、若干独りよがりのような印象を受けるし、分かりづらい。
自分が普段使っている言葉や言い回しを、外国語を通して、日本語の外から比較検討してみると、日本語の特徴、その背景にある日本人の姿が現れてくる。
このエッセイは、それに気づかせてくれました。
2014年11月24日月曜日
It's A Man's Man's Man's World
高倉健が出てくる映画は、ほとんど見なかったけれど、不思議とこのCMだけは覚えている。
喧嘩でやられそうな男を、見捨てられずに、つい助けにゆく。
それだけなのだが、子供ごころに、カッコいい男だなと思った。
リアリティを感じさせながら、この役を他に誰がやれるのだろうと思うと、そうそう思いつかないところに、高倉健の魅力があるのかもしれない。
Dr.Johnが歌うハードボイルドな"It's A Man's Man's Man's World"が、その雰囲気を引き立たせている。
He's lost in the wilderness.
He's lost in bitterness.
まるで、高倉健のための歌のように感じてしまう。
喧嘩でやられそうな男を、見捨てられずに、つい助けにゆく。
それだけなのだが、子供ごころに、カッコいい男だなと思った。
リアリティを感じさせながら、この役を他に誰がやれるのだろうと思うと、そうそう思いつかないところに、高倉健の魅力があるのかもしれない。
Dr.Johnが歌うハードボイルドな"It's A Man's Man's Man's World"が、その雰囲気を引き立たせている。
He's lost in the wilderness.
He's lost in bitterness.
まるで、高倉健のための歌のように感じてしまう。
2014年11月23日日曜日
キャンディを撮った日/片岡義男
僕の感じ方によれば、キャンディはけっしておいしいものではない。こんな感想をキャンディに対して持った作家が書いたキャンディの本。
基本的にはどれもみなひどく甘く、香りが少しずつ違っているだけだ。
味覚として好きなキャンディはほとんどない
きれいな写真に写るキャンディはおもちゃのように現実感がない。
それらは、きれいだけれども、装飾品のように時に毒々しい色をし、時に気持ち悪い。
少なくとも口に入れるものではないのではないか、そんな思いがよぎる。
僕にとって、キャンディとは観察の対象であり、指先でさまざまに触れてみるものだった。…キャンディは見て楽しむ道具だ。キャンディで僕はどれほど遊んだろう。どれだけのキャンディの包装をはがし、そのままにしたことか。…僕にとって観察の対象たり得るとは、たいていのキャンディはそれぞれに奇妙である、ということだ。
片岡義男という作家の本は、上記の文章におけるキャンディという言葉を、アメリカという言葉に置き換えてみると、すべて理解できてしまうのではないか。
この無機質な、まるでキャンディの匂いがするような本を、片岡の著作のかたまりに投げて、ふと、そう思う。
2014年11月3日月曜日
Coming soon / Original Love
Original Love 田島貴男の歌を週に一度は聴く。
駅に向かうとき、ジムで体を動かすとき、もっぱら体を動かしている時に聴いているのだが、死んでいない、同時代の同年代の人の曲を楽しめるというのは、やはり素直にうれしい。
自分が好きな音楽や小説を集めると、圧倒的に80年代以下になってしまうので、一時期は、何故、もっと早く生まれなかったのだろうと真剣に自分の生年月日を悔やんだ時期もあった。
そんなわたしが、田島貴男や一十三十一、ポール・ウェラーの音楽をリアルに聴くことができたのは、やはりうれしい。
自分でも圧倒的に活字で物を考えるタイプだと思っているが、音楽は、気持ちをふわっともちあげてくれるところが素敵だ。
それは、目の前に素敵な女の子がふっと現れる瞬間に似ている。妙に世界がきらきら輝くのだ。
活字でもそんな事はたまにあるが、音楽の即効性には敵わない。
田島貴男の音楽は、常に変化を求めている。
前作の曲作りを無視して、あるいは壊して、新しい音楽を探す姿勢を感じる。
田島自身、あまり、ファンが何を期待しているのか、考えていないのだと思う。
実際、彼の音楽を聴いて、何度か裏切られた気持ちになったことがあった。
でも、自分のすきなアーティストの作品は、そうそう嫌いになれないというのが実感だ。
聴いているうちに、いずれ好きになってしまう。
実際、何年か後にそれを好きになり、過去の自分の感覚を疑ったことが何回かある。
新しいシーズンが来る♪
2011年に聴いたその気持ちをふわっと持ち上げる曲を、今も飽きずに聴いている。
駅に向かうとき、ジムで体を動かすとき、もっぱら体を動かしている時に聴いているのだが、死んでいない、同時代の同年代の人の曲を楽しめるというのは、やはり素直にうれしい。
自分が好きな音楽や小説を集めると、圧倒的に80年代以下になってしまうので、一時期は、何故、もっと早く生まれなかったのだろうと真剣に自分の生年月日を悔やんだ時期もあった。
そんなわたしが、田島貴男や一十三十一、ポール・ウェラーの音楽をリアルに聴くことができたのは、やはりうれしい。
自分でも圧倒的に活字で物を考えるタイプだと思っているが、音楽は、気持ちをふわっともちあげてくれるところが素敵だ。
それは、目の前に素敵な女の子がふっと現れる瞬間に似ている。妙に世界がきらきら輝くのだ。
活字でもそんな事はたまにあるが、音楽の即効性には敵わない。
田島貴男の音楽は、常に変化を求めている。
前作の曲作りを無視して、あるいは壊して、新しい音楽を探す姿勢を感じる。
田島自身、あまり、ファンが何を期待しているのか、考えていないのだと思う。
実際、彼の音楽を聴いて、何度か裏切られた気持ちになったことがあった。
でも、自分のすきなアーティストの作品は、そうそう嫌いになれないというのが実感だ。
聴いているうちに、いずれ好きになってしまう。
実際、何年か後にそれを好きになり、過去の自分の感覚を疑ったことが何回かある。
新しいシーズンが来る♪
2011年に聴いたその気持ちをふわっと持ち上げる曲を、今も飽きずに聴いている。
2014年11月2日日曜日
ザ・チョイス/エリヤフ・ゴールドラット
本書は、エリヤフ・ゴールドラットが、娘との対話の中で、人はいかに充実した人生を送ることができるかを考察したプロセスを物語にした本である。
娘の視点で物語は進むのだが、実際にこれを書いたのは、父親であるエリヤフであることを思うと、ちょっと不思議な印象を受ける。
その教訓を以下に記載してみる。
・人はもともと善良である。
・すべての対立は解消できる。
・ものごとは、そもそもシンプルである。
・どんな状況でも著しく改善できる。
・どんな人でも充実した人生を達成することができる。
・常にwin-winのソリューションがある。
どうでしょう。なるほどと思う人はどれぐらいいるだろうか?
少なくとも私は、すぐに腑に落ちませんでした。
しかし、メモ帳に、これらの教訓を書き写して、本書で気になったセンテンスを書き加えて、しばし考察してみると、なるほどと思うところがあった。
上記の箴言を裏返してみると、どうだろう。
・人(取引相手と考えてみる)は、こちらの立場を考えず、利己的で、邪悪なものだ。
・対立は当たり前で仕方がないものだ。これを解決することはできず、妥協点を見出すしかない。
・現実は複雑である。
・人は変化を好まない。だから、自分がいくら頑張ってもその改善には限界がある。
・取引はwin-loseが基本で、どちらかが妥協するしかない。
この裏・箴言は、ほとんど、「大人の常識」といってもいいものではないだろうか。
ゴールドラットは、このような常識が、人が真実(原因と結果の関係)を明晰に考えることの障害になっているという。
現状の課題をブレイクスルー(打破)するためには、常識を一旦捨てる柔軟性が必要なのは間違いない。そう考えると、まさに常識を逆にゆく、一見、性善説と楽天主義の極みのような上記の箴言に、真実味を感じとることができる。
娘の視点で物語は進むのだが、実際にこれを書いたのは、父親であるエリヤフであることを思うと、ちょっと不思議な印象を受ける。
その教訓を以下に記載してみる。
・人はもともと善良である。
・すべての対立は解消できる。
・ものごとは、そもそもシンプルである。
・どんな状況でも著しく改善できる。
・どんな人でも充実した人生を達成することができる。
・常にwin-winのソリューションがある。
どうでしょう。なるほどと思う人はどれぐらいいるだろうか?
少なくとも私は、すぐに腑に落ちませんでした。
しかし、メモ帳に、これらの教訓を書き写して、本書で気になったセンテンスを書き加えて、しばし考察してみると、なるほどと思うところがあった。
上記の箴言を裏返してみると、どうだろう。
・人(取引相手と考えてみる)は、こちらの立場を考えず、利己的で、邪悪なものだ。
・対立は当たり前で仕方がないものだ。これを解決することはできず、妥協点を見出すしかない。
・現実は複雑である。
・人は変化を好まない。だから、自分がいくら頑張ってもその改善には限界がある。
・取引はwin-loseが基本で、どちらかが妥協するしかない。
この裏・箴言は、ほとんど、「大人の常識」といってもいいものではないだろうか。
ゴールドラットは、このような常識が、人が真実(原因と結果の関係)を明晰に考えることの障害になっているという。
現状の課題をブレイクスルー(打破)するためには、常識を一旦捨てる柔軟性が必要なのは間違いない。そう考えると、まさに常識を逆にゆく、一見、性善説と楽天主義の極みのような上記の箴言に、真実味を感じとることができる。
2014年10月26日日曜日
洋食屋から歩いて5分/片岡義男
エッセイとは、「形式にとらわれず,個人的観点から物事を論じた散文」のことを言うらしいが、やはり、作者個人の趣味嗜好が強く感じられる文章だと思う。
雑誌に掲載されている一文を読むだけであれば、大抵の文章は読み切ることはできると思うが、単行本としてまとめられたもの全てを読み切るには、興味を引く内容が相当な程度、収められていなければならない。
私の場合、かなり飽きっぽいので、つまらない内容が2つ、3つ続くと、すぐに読むのをやめてしまうのだが、片岡義男のこの本は読み切ることができた。
いかにも片岡義男らしい作品(コーヒーやハワイ、風船ガムの話)もあるが、こんな人なのかという意外なテーマ(料理本、居酒屋、弁当、俳句などの日本的な内容)もあった。
もっとも心に残ったのは、チャンドラーの翻訳でも知られる田中小実昌(たなか こみまさ)に、新宿の地下道で、「なんだ、テディじゃないか」と声をかけられ(片岡は「テディ片岡」というペンネームを過去に使っていた)、紀伊国屋に行き、船橋のストリップ・ショーを見に行き、ふたたび新宿に戻り、全盛期の頃と思われるゴールデン街を徹夜で飲み歩く「コーヒーに向けてまっ逆さま」だった。
よけいな表現が削ぎおとされていて、読んでいて不潔な印象を受けないところは、海老沢泰久の文章と似ている。
最後の「真夜中にセロリの茎が」も、不思議な味わいがある。
「真夜中のセロリの茎」という同じ題名で4回、短編小説を書くことになった話で、片岡がその小説のあらすじも含めて、なぜ書き直すことになったか、その理由を説明するのだが、片岡が間違いだと感じた部分が少なくとも私にはピンと来ない(書き直した内容のほうがちょっと現実離れした展開になる)。
また、片岡が4回目に書き直そうと思い立った直接の原因となる3回目に書き直した小説は、片岡が思い込んでいた物語とは全く違った内容だったことを読者に指摘されたというエピソードも、何とも不思議な話である。
まるで、丸谷才一の短編小説「樹影譚」の主人公である作家が、樹の影をテーマにした短編小説をナボコフが書いていたと思い込んでいた話のようだ。
雑誌に掲載されている一文を読むだけであれば、大抵の文章は読み切ることはできると思うが、単行本としてまとめられたもの全てを読み切るには、興味を引く内容が相当な程度、収められていなければならない。
私の場合、かなり飽きっぽいので、つまらない内容が2つ、3つ続くと、すぐに読むのをやめてしまうのだが、片岡義男のこの本は読み切ることができた。
いかにも片岡義男らしい作品(コーヒーやハワイ、風船ガムの話)もあるが、こんな人なのかという意外なテーマ(料理本、居酒屋、弁当、俳句などの日本的な内容)もあった。
もっとも心に残ったのは、チャンドラーの翻訳でも知られる田中小実昌(たなか こみまさ)に、新宿の地下道で、「なんだ、テディじゃないか」と声をかけられ(片岡は「テディ片岡」というペンネームを過去に使っていた)、紀伊国屋に行き、船橋のストリップ・ショーを見に行き、ふたたび新宿に戻り、全盛期の頃と思われるゴールデン街を徹夜で飲み歩く「コーヒーに向けてまっ逆さま」だった。
よけいな表現が削ぎおとされていて、読んでいて不潔な印象を受けないところは、海老沢泰久の文章と似ている。
最後の「真夜中にセロリの茎が」も、不思議な味わいがある。
「真夜中のセロリの茎」という同じ題名で4回、短編小説を書くことになった話で、片岡がその小説のあらすじも含めて、なぜ書き直すことになったか、その理由を説明するのだが、片岡が間違いだと感じた部分が少なくとも私にはピンと来ない(書き直した内容のほうがちょっと現実離れした展開になる)。
また、片岡が4回目に書き直そうと思い立った直接の原因となる3回目に書き直した小説は、片岡が思い込んでいた物語とは全く違った内容だったことを読者に指摘されたというエピソードも、何とも不思議な話である。
まるで、丸谷才一の短編小説「樹影譚」の主人公である作家が、樹の影をテーマにした短編小説をナボコフが書いていたと思い込んでいた話のようだ。
2014年10月18日土曜日
クリティカルチェーン/エリヤフ・ゴールドラット
半世紀ぶりとなる日本国産のジェット機が完成した、という今日のニュースを見て、それはすごいと思いつつも、計画からすでに4年遅れている、という点も気になった。
ちょうど、この本(副題:なぜ、プロジェクトは、予定どおりに進まないのか?)を読み終わったところだったので、よけい、そう感じたのかもしれない。
この本では、MBAのビジネススクールで行われるプロジェクト・マネジメントの教室が主な舞台なのだが、その講師が定義する「プロジェクト」の定義が分かりやすい。
この本は、その原因について、以下の問題点を指摘している。
・ステップ毎の余裕時間の積み増し
計画を立てるときに、プロジェクト全体をスケジュールどおりに終わらせるには、各ステップがそれぞれ定められた期日までに作業を終えるしかないと当然のことのように考えてしまう。そして、ステップ毎に、「まず大丈夫」という余裕時間を積み増して見積ってしまう。
・学生症候群
期限までに時間的な余裕があるとつい他の事に手が出て、結局ぎりぎりまで作業に着手しない傾向をいう。ぎりぎりまで着手しないから結局、予定の期限には間に合わなくなる。
・掛け持ち作業の弊害
複数のプロジェクトを担当し、優先順位が不明確だといずれのプロジェクトにも「均等に」時間を割かなければならなくなるため、ひとつに集中し終了させるのに比べ、段取りのロスや待ち時間のために所要時間が大幅に延びる。
・依存関係
作業同士が依存している場合、ひとつの先行作業が遅れるとそれが後続の作業に波及してしまう。
そして、これらの問題点を解消するためには、
・期限は設けず、作業期間のみを提示し、作業が回ってきたらすぐに着手し、終わればすぐに申告する。
・個人の時間見積もりは余裕を持たず、「厳しそうだが、やればできる」時間にする。削った余裕はプロジェクト全体の余裕として集中する。
・複数のプロジェクトが集中しているリソース(特定の作業を行う人と考えると分かりやすい)に対しては、事前のスケジューリングの段階で、仕事の優先順位を明確にし、リソースの競合(掛け持ち作業)に陥らないようなスケジュールを作成する。
などの革新的な手法を提案している。
物語の中で、下請業者に、期限を約束させず、利益を上乗せすることで短縮した作業期間を約束させるという、本当?と疑いたくなってしまう交渉の場面が出てくるが、それなりの合理性が感じられるので、一度は実際に試してみたい、と思わせるものがある。
ビジネスに携わる人であれば、誰しも興味を持ちそうな課題を取り上げ、物語の中で革新的な問題解決の手法を説明するエリヤフ・ゴールドラットの小説。
私にとっては、まさかの4冊目の読了となった。
ちょうど、この本(副題:なぜ、プロジェクトは、予定どおりに進まないのか?)を読み終わったところだったので、よけい、そう感じたのかもしれない。
この本では、MBAのビジネススクールで行われるプロジェクト・マネジメントの教室が主な舞台なのだが、その講師が定義する「プロジェクト」の定義が分かりやすい。
目標を達成するために、どの作業をどういう順で行わなければならないのか、あるいはどの作業をいつ始めていつ終わらせたらいいのかタイムチャートを作ったことはありませんか。もしそのようなチャートを使って仕事をした経験があるのなら、プロジェクトを経験したことがあるということです。その「プロジェクト」が、何故、ほとんど、期限までに終わらないのか。
この本は、その原因について、以下の問題点を指摘している。
・ステップ毎の余裕時間の積み増し
計画を立てるときに、プロジェクト全体をスケジュールどおりに終わらせるには、各ステップがそれぞれ定められた期日までに作業を終えるしかないと当然のことのように考えてしまう。そして、ステップ毎に、「まず大丈夫」という余裕時間を積み増して見積ってしまう。
・学生症候群
期限までに時間的な余裕があるとつい他の事に手が出て、結局ぎりぎりまで作業に着手しない傾向をいう。ぎりぎりまで着手しないから結局、予定の期限には間に合わなくなる。
・掛け持ち作業の弊害
複数のプロジェクトを担当し、優先順位が不明確だといずれのプロジェクトにも「均等に」時間を割かなければならなくなるため、ひとつに集中し終了させるのに比べ、段取りのロスや待ち時間のために所要時間が大幅に延びる。
・依存関係
作業同士が依存している場合、ひとつの先行作業が遅れるとそれが後続の作業に波及してしまう。
そして、これらの問題点を解消するためには、
・期限は設けず、作業期間のみを提示し、作業が回ってきたらすぐに着手し、終わればすぐに申告する。
・個人の時間見積もりは余裕を持たず、「厳しそうだが、やればできる」時間にする。削った余裕はプロジェクト全体の余裕として集中する。
・複数のプロジェクトが集中しているリソース(特定の作業を行う人と考えると分かりやすい)に対しては、事前のスケジューリングの段階で、仕事の優先順位を明確にし、リソースの競合(掛け持ち作業)に陥らないようなスケジュールを作成する。
などの革新的な手法を提案している。
物語の中で、下請業者に、期限を約束させず、利益を上乗せすることで短縮した作業期間を約束させるという、本当?と疑いたくなってしまう交渉の場面が出てくるが、それなりの合理性が感じられるので、一度は実際に試してみたい、と思わせるものがある。
ビジネスに携わる人であれば、誰しも興味を持ちそうな課題を取り上げ、物語の中で革新的な問題解決の手法を説明するエリヤフ・ゴールドラットの小説。
私にとっては、まさかの4冊目の読了となった。
2014年10月13日月曜日
なにを買ったの?文房具。/片岡義男
前作の 文房具を買いにと同じコンセプトの本なので、特に読むまでもないかなと思ったが、出だしの「一本の鉛筆からすべては始まる」の文章にさそわれて、つい読んでしまった。
こんな文章だ。
それらに関する文章も印象的なものが多い。
一眼レフカメラにマクロ・レンズを付けて撮影した片岡自身、その快楽に勝てず、つい、もう一冊書いてしまったという本だろう。
こんな文章だ。
いま僕は一本の鉛筆を手にしている。ひとり静かに、落ち着いた気持ちで、指先に一本の鉛筆を。
…孤独な僕は、I think better with a pencil in may hand.というワンセンテンスを思い出す。鉛筆を手にしていると自分はより良く考えることができる、という意味だ。ずっと以前にどこかで読み、それ以来いまも忘れずにいる。本書でも、前作同様、さまざまな文房具を紹介してゆくが、片岡自身の思い入れは、やはり、作家としての仕事道具である鉛筆、鉛筆削り、消しゴム、手帳、ノートブックに比重が高くなっていると思う。
それらに関する文章も印象的なものが多い。
学校の勉強を始めるために、まず鉛筆を削った。削り終えたら勉強を始めなくてはいけないから、何本もの鉛筆をゆっくり丁寧に削った。…削っていくあいだの子供の気持ちは、大げさに言うなら、覚悟の醸成だったのではなかったか。学校の勉強は嫌だが、嫌だ、というその気持ちや態度の克復が、じつは勉強だった。また、
内ポケットから手帳を取り出し、この鉛筆を背中から抜き、指先で手帳のページを繰り、芯を舌の先でなめ、なにごとかを書き込んでいく大人を、僕が子どもの頃にはしばしば見かけた。平凡ではあるがそれなりに誠実な大人なのではないかと、子供心にも多少の感銘を受けたりもしたが、すでに長いことこのような大人を見ていない。平凡でなおかつ誠実な大人が、日本から消えたからか。あるいは、
消しゴムは、じつは、まったく新たな可能性、というものの権化なのだ。…正しくないものを、いまだ不充分なものなどを、消し去ることによって、そこにより正しい試みを、消しゴムは用意する。消しゴムによって消されたあとには、広大な可能性の地平が出現しているのだが、多くの人はその事実に気づかない。本書には、多くの文房具の写真が使われているが、黒いケント紙のうえで、太陽の光を気持ちよく浴びて、上品に佇んでいる色彩ゆたかな文房具のすがたを見るのは心地よい。
一眼レフカメラにマクロ・レンズを付けて撮影した片岡自身、その快楽に勝てず、つい、もう一冊書いてしまったという本だろう。

2014年10月12日日曜日
英語で日本語を考える/片岡義男
片岡義男が、日本語の“ひと言”を、英語に翻訳するプロセス――言葉の変換術――をまとめた本だ。
あらためて思ったのは、翻訳とは、単に日本語の単語を英単語に置き換える作業ではなく、日本語の文章を一旦、要素レベルに分解し、重要なものを抽出し、それに近い英語らしい表現に作り変えていくということだ。
たとえば、以下のような例文がある。
そして、片岡義男が、この本の冒頭で述べているとおり、このような英語能力の習得の基本となるべき最重要なものは、日本語の能力なのだと思う。
たぶん、その能力がないと、日本語からの意味の抽出、別のことばへの置き換えが出来ないだろう。
あらためて思ったのは、翻訳とは、単に日本語の単語を英単語に置き換える作業ではなく、日本語の文章を一旦、要素レベルに分解し、重要なものを抽出し、それに近い英語らしい表現に作り変えていくということだ。
たとえば、以下のような例文がある。
「こういう話になってくると、誰が悪い誰がいけないなんて言ってみても、始まらないんですよ。みんなどこかでつながっているわけですから」について、
「こういう話」と「になってくる」のふたつの部分は、いっきに細かく砕いて意味だけにすると、「この状況では」という意味でしかない。
ここまで砕くと、そこから英語へは、“In a situation like this”とほぼ直訳できる。
「始まらないんですよ」も、意味だけを抽出すると、そのことに意味はない、というような内容であることが、すぐに分かる。
意味はない、という言い方が持つ範囲の広さを、意味の核に向けてさらに絞り込んでいくと、なんら有効な視点にはなり得ない、というようなことだと判明する。“pointless”という便利な言葉がある。これを使えばいい。
「誰が悪い誰がいけないなんて言ってみても」という日常的な語法は、「責められるべきは誰なのか判明させようとしても」という程度まで砕く…そしてこの内容をとにかく最短距離で言おうとすると、次のようになる。
“try to figure out who's to blame”
「みんなどこかでつながっているわけですから」という言いかたは、…「ぜんたいはひとつの環である」とまで砕くと、それをそのまま、“it's a circle”と言えば、英語らしい英語になる。
課題の日本語の文例ぜんたいは、次のような英語にまとまる。
“In a situation like this, it's pointless to figure out who's to blame. It's a circle.”この作業プロセスをみると、日本語の要素となる骨の部分だけ抜き取り、それを英作文する作業に近いような印象を受ける。
そして、片岡義男が、この本の冒頭で述べているとおり、このような英語能力の習得の基本となるべき最重要なものは、日本語の能力なのだと思う。
たぶん、その能力がないと、日本語からの意味の抽出、別のことばへの置き換えが出来ないだろう。
2014年10月11日土曜日
日本語と英語 その違いを楽しむ/片岡義男
本書でもっとも面白いと感じたのは、片岡義男が十五歳のときに「源氏物語」を読んで衝撃を受けたというエピソードだ。
彼は、「源氏物語」の出だしのフレーズ「いずれのおんときにか」というわずか10文字がまったく理解できない事実に愕然とし、後年、「源氏物語」の英訳を読み、該当する文章「In the reign certain emperor」(ある天皇の統治下で)の、あまりのわかりやすさに、強い衝撃を受けた。
本書は、この片岡義男の原体験「源氏物語の影」に基づき書き留められた日本語と英語の比較言語学的エッセイだ。
片岡義男が愛用しているインデックス・カードに書き留められつづけた日本語と英語の数々のフレーズ。
ほとんどが日常的に使われている常套句といっていいものだが、そのありふれたフレーズから、日本語と英語の違いを浮き上がらせる。
たとえば、
「住所氏名をご記入の上この葉書をご返送いただければ当社の新刊や特典、催物などの情報をお届けいたします。」と、
“We invite you to return this card with your name and address so that we can keep your informed of our new publications, special offers and events.”。
この2つの文章に関して、片岡義男は、こんな風に分析する。
(日本語の文章は、)「ご返送いただければ」という、自分のところに葉書が返送されてきたあとの状態を想定している。
すでにそうなっている状態のなかに自分も身を置くのが、日本の人たちはなによりも好きなのだろう。
(しかし)葉書が返送されるからには、返送する側は返送というアクションをとるのだし、返送を促すための訴えかけというアクションを、返送を求めるほうはおこなうのだが。
英語の例文を見ると、この両方の動詞がごく当然のこととして、あるべきところにある。
返送を促すための訴えかけをおこなうのは、出版社の人たち、つまりこの短文の主語となるべき We という人たちだ。
だから、Weが主語になり、そのWeが引き受ける動詞はinviteだ。そして相手に促す返送というアクションは、returnという明確な動詞が引き受ける。
なるほどと思う。こういう日常の常套句を比べてみると、確かに日本語と英語はまるで違う。
片岡義男は、日本語について、こう分析する。
主語がIやYouなら、それらは主語にならないし、IやYouの思考や行動を引き受けて言いあらわす動詞も、必要ないから姿をあらわさない。
動詞が働きかける目的語その他、主語からの一連の構造的なつながりはそこになく、そのかわりに、いつのまにかそうなっている状態、というものが言いあらわされる。
そして、片岡義男は、日本語について、主語が不在ということは、主語の主語たるゆえんである思考も隠れ、結果、思考に基づく行動も隠れ、思考と行動を放棄しているという。
片岡義男の考えとしては、日常生活で用いられる常套句にこそ、言語の性質が現れ、その言語の性質が、日本語を話す人の、あるいは英語を話す人の思考や行動に大きな影響を及ぼしているということなのかもしれない。
片岡義男の言い方は、時に日本語のそういった性質をとらえ、日本人と日本の社会を批判しているようにも思えるが、語気はそれほど鋭くない(ように私は感じる)。
この本の副題のように、何故こんなにも違うのか、まさに、その違いを楽しんでいるのだと思う。
彼は、「源氏物語」の出だしのフレーズ「いずれのおんときにか」というわずか10文字がまったく理解できない事実に愕然とし、後年、「源氏物語」の英訳を読み、該当する文章「In the reign certain emperor」(ある天皇の統治下で)の、あまりのわかりやすさに、強い衝撃を受けた。
本書は、この片岡義男の原体験「源氏物語の影」に基づき書き留められた日本語と英語の比較言語学的エッセイだ。
片岡義男が愛用しているインデックス・カードに書き留められつづけた日本語と英語の数々のフレーズ。
ほとんどが日常的に使われている常套句といっていいものだが、そのありふれたフレーズから、日本語と英語の違いを浮き上がらせる。
たとえば、
「住所氏名をご記入の上この葉書をご返送いただければ当社の新刊や特典、催物などの情報をお届けいたします。」と、
“We invite you to return this card with your name and address so that we can keep your informed of our new publications, special offers and events.”。
この2つの文章に関して、片岡義男は、こんな風に分析する。
(日本語の文章は、)「ご返送いただければ」という、自分のところに葉書が返送されてきたあとの状態を想定している。
すでにそうなっている状態のなかに自分も身を置くのが、日本の人たちはなによりも好きなのだろう。
(しかし)葉書が返送されるからには、返送する側は返送というアクションをとるのだし、返送を促すための訴えかけというアクションを、返送を求めるほうはおこなうのだが。
英語の例文を見ると、この両方の動詞がごく当然のこととして、あるべきところにある。
返送を促すための訴えかけをおこなうのは、出版社の人たち、つまりこの短文の主語となるべき We という人たちだ。
だから、Weが主語になり、そのWeが引き受ける動詞はinviteだ。そして相手に促す返送というアクションは、returnという明確な動詞が引き受ける。
なるほどと思う。こういう日常の常套句を比べてみると、確かに日本語と英語はまるで違う。
片岡義男は、日本語について、こう分析する。
主語がIやYouなら、それらは主語にならないし、IやYouの思考や行動を引き受けて言いあらわす動詞も、必要ないから姿をあらわさない。
動詞が働きかける目的語その他、主語からの一連の構造的なつながりはそこになく、そのかわりに、いつのまにかそうなっている状態、というものが言いあらわされる。
そして、片岡義男は、日本語について、主語が不在ということは、主語の主語たるゆえんである思考も隠れ、結果、思考に基づく行動も隠れ、思考と行動を放棄しているという。
片岡義男の考えとしては、日常生活で用いられる常套句にこそ、言語の性質が現れ、その言語の性質が、日本語を話す人の、あるいは英語を話す人の思考や行動に大きな影響を及ぼしているということなのかもしれない。
片岡義男の言い方は、時に日本語のそういった性質をとらえ、日本人と日本の社会を批判しているようにも思えるが、語気はそれほど鋭くない(ように私は感じる)。
この本の副題のように、何故こんなにも違うのか、まさに、その違いを楽しんでいるのだと思う。
2014年10月2日木曜日
文房具を買いに/片岡義男
片岡義男が、さまざまな文房具(ほとんどが外国製)の写真を撮り、その文房具についての解説とともに、彼のその文房具に対する考え、思いが語られているエッセイだと思う。
たとえば、モールスキンの手帳について
手帳をほとんど書かない自分からみると、“手帳の中に自分がいる”と感じるまで、書き込む人は、私から見れば、異次元に住んでいる人のようだ。
たまに、びっしりと書き込んだ手帳を持っている人を見ることがあるが、同じような心持ちなのだろうか。
この文章を読んで、一日に使うページ数の説明なんて、どうでもいいと思う人もいるかもしれない。
しかし、この本は、さまざまな文房具について、
手帳、鉛筆、鉛筆クリップ、電子辞書、封筒、パステル、ボールペン、ステイプラー、サインペン、消しゴム、香料としてのチューインガム、ポスト・イット、糊、鋏、ノートブック、スケジュール帳、インデックス・カード、リーガル・パッド、ロディアのパッド、クレール・フォンテーヌのノートブック、ライティング・パッド、置き時計、輪ゴム、クリップ、修正テープ、シール、電卓、AIR MAILのレイベル、切手、モイスナー、宛先レイベル、押しピン、テープ・ライター、ワン・ホール・パンチ、定規、クレヨン・ボックス、写真機、白墨、黒板消し、コンパス
について、片岡義男が、その形状を写真に撮り、その作り、色、寸法、特徴について、執拗に語り続ける。
ひとつの文房具の紹介が終わると、切れ目なく、次から次へと、新たな文房具が現れる。
片岡義男が机に座っていて、彼の目の前の机にある文房具を次から次へと取り出し、説明しているかのように、ひとつづきに説明が流れる。
その律儀ともいえる細かな描写に、若干疲れる読者もいるのではないかと思う。
たとえば、村上春樹が、安西水丸の絵とともに、シェービング・クリームの缶について書いた軽いタッチのエッセイとは、まるで違う空気が流れている。
一言でいうと、男くさいのだ。例えば、女性はメモ帳について、以下のような文章は、まず書かないだろう。
たとえば、モールスキンの手帳について
モールスキンの手帳ノートブックは百九十二ページだ。ひと月で一冊を使いきるとして、一日分として平均して六ページのスペースを割り当てることができる。そしてひと月の半分ほどは、一日分を七ページにすることが可能だ。単純に日割りにするとそうなる。日ごとに変化はあっていい。ただし、ひと月に一冊というペースは、守りたいと思う。一冊を二年も三年も使うようでは、この手帳の良さを生かしきることができないはずだから。一年で十二冊。十二冊の黒い表紙のモールスキンのページに、自分の筆跡でびっしりと書き込まれたさまざまな事柄が、自分にとっての一年なのだ。その十二冊のなかに、その年の自分がいる。少なくともその痕跡くらいは、どのページにも雄弁に残っている。手帳について、ここまで熱く思いを語る人もいるのだな、と若干ほほえましい気分になる。
手帳をほとんど書かない自分からみると、“手帳の中に自分がいる”と感じるまで、書き込む人は、私から見れば、異次元に住んでいる人のようだ。
たまに、びっしりと書き込んだ手帳を持っている人を見ることがあるが、同じような心持ちなのだろうか。
この文章を読んで、一日に使うページ数の説明なんて、どうでもいいと思う人もいるかもしれない。
しかし、この本は、さまざまな文房具について、
手帳、鉛筆、鉛筆クリップ、電子辞書、封筒、パステル、ボールペン、ステイプラー、サインペン、消しゴム、香料としてのチューインガム、ポスト・イット、糊、鋏、ノートブック、スケジュール帳、インデックス・カード、リーガル・パッド、ロディアのパッド、クレール・フォンテーヌのノートブック、ライティング・パッド、置き時計、輪ゴム、クリップ、修正テープ、シール、電卓、AIR MAILのレイベル、切手、モイスナー、宛先レイベル、押しピン、テープ・ライター、ワン・ホール・パンチ、定規、クレヨン・ボックス、写真機、白墨、黒板消し、コンパス
について、片岡義男が、その形状を写真に撮り、その作り、色、寸法、特徴について、執拗に語り続ける。
ひとつの文房具の紹介が終わると、切れ目なく、次から次へと、新たな文房具が現れる。
片岡義男が机に座っていて、彼の目の前の机にある文房具を次から次へと取り出し、説明しているかのように、ひとつづきに説明が流れる。
その律儀ともいえる細かな描写に、若干疲れる読者もいるのではないかと思う。
たとえば、村上春樹が、安西水丸の絵とともに、シェービング・クリームの缶について書いた軽いタッチのエッセイとは、まるで違う空気が流れている。
一言でいうと、男くさいのだ。例えば、女性はメモ帳について、以下のような文章は、まず書かないだろう。
…横罫は淡いブルーで二十二本。間隔はここでもまだ七ミリだ。そして左の端から二十五ミリの位置に、淡い赤で縦罫が二本、二ミリ間隔で垂直に引いてある。この罫のありかたがジュニア・リーガル・ルール(罫)と呼ばれている。しかし、この文章は、その後、以下のように続いていて、ひとつの文明批評になっているところも面白い。
リーガル・パッドのリーガルとは、罫線のありかたよりもはるかに、物事のとらえかた、ものの考えかた、論理の展開のさせかたなどを、意味する。自分の論理を強めたり補完したりする可能性のあるものは、ひとつ残らず書き出して列挙し、それらを作戦的にいろんな方向から観察し、取捨選択しつつ修正をほどこし、論理の筋道を作り、それに沿って論理を組み上げていく。そしてその論理によって、いかなるかたちにせよ、自分を勝利に導いていく。リーガル・マインドの基本はこれであり、これはアメリカ社会のあらゆる細部にまで、徹底して浸透している。
2014年10月1日水曜日
片岡義男という存在
片岡義男という人は、私にとっては、ずっと謎の存在だった。
1980年代、角川文庫の棚一列を埋めつくしていた彼の作品。
数多くの映画化された作品。
たぶん、一度はページを開いたことはあると思う。
でも、読まなかった。
おそらくだけれど、自分の好みの文章ではないものを感じたからなのだと思う。
彼の作品は、生存している小説家としてはめずらしく、青空文庫で読める。
そして、短編「私とキャッチ・ボールをしてください」を読んで、やはり、彼の小説を、数冊読むことはないと感じる。
その昔(1988年)、NHKのドラマで、「ハートブレイクなんてへっちゃら」という単発のドラマが放映された。
気障な作家が女性にからむ4話のショートオムニバスみたいな作品なのだが、1話(バイクに乗った女の子をお月見にナンパする話)と4話(酔っぱらった洞口依子さんと、なんかグダグダになる話)だけ、おぼろげに記憶に残っている。
唯一、触れた彼の作品(原作)だったが、不思議と原作を読もうという気にならなかった。
そうして、時間が経ち、ここ十年ばかり、本屋で並ぶ新刊で、よく彼の本が目に留まるようになった。
文房具の本や、ペーパーブックの表紙の本や、英語や翻訳についての本。
手にとって読むうちに、不思議な印象を覚えた。
まるで、翻訳文みたいな、若干ぎこちない日本語。
でも、小説よりいい。というか、テーマに不思議となじんでいる。
そう、思いながらも、やはり、これらの本も本格的に読まないで素通りしてきた。
ここまで縁がないなら、そのまま行けばいいのだが、最近、「文房具を買いに」を、まともに読んでいる。
村上春樹の9つ上の1940年生まれ。
原爆投下のキノコ雲も目撃している。
同期は何と、唐十郎、志茂田景樹、ル・クレジオ、立花隆、C・W・ニコル、池内紀。
そして、不思議な気持ちになる。この人は、日本の文学界において何者なんだろうと。
「文房具を買いに」の感想を書きたかったのだが、片岡義男という存在が、私の中では予想以上に膨らんでいて、まず、これを吐き出す作業が必要だった。
1980年代、角川文庫の棚一列を埋めつくしていた彼の作品。
数多くの映画化された作品。
たぶん、一度はページを開いたことはあると思う。
でも、読まなかった。
おそらくだけれど、自分の好みの文章ではないものを感じたからなのだと思う。
彼の作品は、生存している小説家としてはめずらしく、青空文庫で読める。
そして、短編「私とキャッチ・ボールをしてください」を読んで、やはり、彼の小説を、数冊読むことはないと感じる。
その昔(1988年)、NHKのドラマで、「ハートブレイクなんてへっちゃら」という単発のドラマが放映された。
気障な作家が女性にからむ4話のショートオムニバスみたいな作品なのだが、1話(バイクに乗った女の子をお月見にナンパする話)と4話(酔っぱらった洞口依子さんと、なんかグダグダになる話)だけ、おぼろげに記憶に残っている。
唯一、触れた彼の作品(原作)だったが、不思議と原作を読もうという気にならなかった。
そうして、時間が経ち、ここ十年ばかり、本屋で並ぶ新刊で、よく彼の本が目に留まるようになった。
文房具の本や、ペーパーブックの表紙の本や、英語や翻訳についての本。
手にとって読むうちに、不思議な印象を覚えた。
まるで、翻訳文みたいな、若干ぎこちない日本語。
でも、小説よりいい。というか、テーマに不思議となじんでいる。
そう、思いながらも、やはり、これらの本も本格的に読まないで素通りしてきた。
ここまで縁がないなら、そのまま行けばいいのだが、最近、「文房具を買いに」を、まともに読んでいる。
村上春樹の9つ上の1940年生まれ。
原爆投下のキノコ雲も目撃している。
同期は何と、唐十郎、志茂田景樹、ル・クレジオ、立花隆、C・W・ニコル、池内紀。
そして、不思議な気持ちになる。この人は、日本の文学界において何者なんだろうと。
「文房具を買いに」の感想を書きたかったのだが、片岡義男という存在が、私の中では予想以上に膨らんでいて、まず、これを吐き出す作業が必要だった。
2014年9月30日火曜日
続 日本人の英語/マーク・ピーターセン
日本や外国の映画や小説のセリフを取り上げ、日本語の感覚と英語の感覚を、エッセイ風に語る内容が主です。
正直、前作の冠詞・定冠詞のようなインパクトはないが、読んでいると、それなりに役立つ内容は書いてあると思います。
個人的には、著者が日本の学生と、J.D.サリンジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」( A Perfect Day for Bananafish )の読み合わせをした際の話が興味深かった。
シーモアの妻ミュリエルが、母親と電話で話をしているときに、シーモアが自分のことをこう呼んでいると説明した部分
He calls me Miss Spiritual Tramp of 1948," the girl said, and giggled.
"Tramp"の持つ意味は、身持ちの悪い女(あばずれ・無節操)・売春婦
野崎孝 訳では、以下のとおり
「1948年度のミス精神的ルンペンですって」 娘はそう言うとくすくす笑い出した。
(ルンペンということばも、どれだけ分かる人がいるだろう。もはや死語ですね。浮浪者とか、乞食の意味です)
この台詞は、キリスト教徒である著者からみると、人間として侮辱されたに等しいほど、相当にきつい言葉であり、読者からすると、夫がここまで妻を痛烈に批判する言葉は、読んでいて、ドキッとしなければならない部分であるというのが著者の印象であったが、日本の学生たちは普通にスルーしてしまったらしい。
著者曰く、このシーモアが妻に対して持った軽蔑は、信仰の厚いキリスト教徒であれば、共感できるものらしい。
しかし、私自身、(原文と野崎孝 訳のギャップもあるとは思うが) この台詞に強い印象を覚えた記憶がない。
仮に、Trampの訳語を、“ルンペン”から“あばずれ”、”無節操”に変えても、シーモア特有の皮肉めいたことばという程度の印象しか、やはり持てないような気がする。
わたし自身、言われたら、ちょっとムッとするかもしればいが、ミュリエル同様、なかなか面白い表現だと笑ってしまうかもしれない。
宗教性によって言葉が与えるインパクトも変わるんだ。そう実感しました。
それ以外で印象に残ったのは、細々とした実用的な知識です。以下、箇条書き。
・The Japanese/個人差を認めなくてよいとする態度
The Japanese have to learn the importance of a level playing field in international trade.
ここでのThe Japaneseは、一人も例外なく、全ての日本人を指す意味らしく、アメリカ人が日本人を評して言う際に、このようなことを言うらしい。
一方、アメリカ人自身については、以下のように、そう思わない人もいるという多様性の余地を残した表現をしている。
Americans believe in giving everyone an equal opportunity to succeed.
・英語にもある漢語と大和言葉
ラテン系は、漢語っぽい。造語的。
アングロサクソン系は、大和言葉っぽくて人間くさい。
例えば、
ラテン系 アングロサクソン系
submit/~を提出する turned in/~を出しました
reconsider/~を再考する take it over/~を考え直す
enter/入りたまえ Come on in/さあ、どうぞ、どうぞ
・hear(耳に入る受け身の聞く)とlisten(自ら収集する聴く)
・see(経験的な見る)とlook(一応目を通す視る・看る)とwatch(何をして過ごしていたかという観る)
・found(ただ出会った)とdiscover(探していたから見つかった)
・使役動詞made/let/had/get
madeは強制的な意味(無理やり~をさせる)
letは~をすることを許す(~をさせてあげる)
hadはビジネス的な意味あい(~してもらう)
got someone to do(説得して~をしてもらった)
・やさしいにもいろいろな表現
nice(一般的なやさしい)
good(物理的に物惜しみしない)
kind(一般的な美徳)
gentle(特別な愛情を感じる)
正直、前作の冠詞・定冠詞のようなインパクトはないが、読んでいると、それなりに役立つ内容は書いてあると思います。
個人的には、著者が日本の学生と、J.D.サリンジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」( A Perfect Day for Bananafish )の読み合わせをした際の話が興味深かった。
シーモアの妻ミュリエルが、母親と電話で話をしているときに、シーモアが自分のことをこう呼んでいると説明した部分
He calls me Miss Spiritual Tramp of 1948," the girl said, and giggled.
"Tramp"の持つ意味は、身持ちの悪い女(あばずれ・無節操)・売春婦
野崎孝 訳では、以下のとおり
「1948年度のミス精神的ルンペンですって」 娘はそう言うとくすくす笑い出した。
(ルンペンということばも、どれだけ分かる人がいるだろう。もはや死語ですね。浮浪者とか、乞食の意味です)
この台詞は、キリスト教徒である著者からみると、人間として侮辱されたに等しいほど、相当にきつい言葉であり、読者からすると、夫がここまで妻を痛烈に批判する言葉は、読んでいて、ドキッとしなければならない部分であるというのが著者の印象であったが、日本の学生たちは普通にスルーしてしまったらしい。
著者曰く、このシーモアが妻に対して持った軽蔑は、信仰の厚いキリスト教徒であれば、共感できるものらしい。
しかし、私自身、(原文と野崎孝 訳のギャップもあるとは思うが) この台詞に強い印象を覚えた記憶がない。
仮に、Trampの訳語を、“ルンペン”から“あばずれ”、”無節操”に変えても、シーモア特有の皮肉めいたことばという程度の印象しか、やはり持てないような気がする。
わたし自身、言われたら、ちょっとムッとするかもしればいが、ミュリエル同様、なかなか面白い表現だと笑ってしまうかもしれない。
宗教性によって言葉が与えるインパクトも変わるんだ。そう実感しました。
それ以外で印象に残ったのは、細々とした実用的な知識です。以下、箇条書き。
・The Japanese/個人差を認めなくてよいとする態度
The Japanese have to learn the importance of a level playing field in international trade.
ここでのThe Japaneseは、一人も例外なく、全ての日本人を指す意味らしく、アメリカ人が日本人を評して言う際に、このようなことを言うらしい。
一方、アメリカ人自身については、以下のように、そう思わない人もいるという多様性の余地を残した表現をしている。
Americans believe in giving everyone an equal opportunity to succeed.
・英語にもある漢語と大和言葉
ラテン系は、漢語っぽい。造語的。
アングロサクソン系は、大和言葉っぽくて人間くさい。
例えば、
ラテン系 アングロサクソン系
submit/~を提出する turned in/~を出しました
reconsider/~を再考する take it over/~を考え直す
enter/入りたまえ Come on in/さあ、どうぞ、どうぞ
・hear(耳に入る受け身の聞く)とlisten(自ら収集する聴く)
・see(経験的な見る)とlook(一応目を通す視る・看る)とwatch(何をして過ごしていたかという観る)
・found(ただ出会った)とdiscover(探していたから見つかった)
・使役動詞made/let/had/get
madeは強制的な意味(無理やり~をさせる)
letは~をすることを許す(~をさせてあげる)
hadはビジネス的な意味あい(~してもらう)
got someone to do(説得して~をしてもらった)
・やさしいにもいろいろな表現
nice(一般的なやさしい)
good(物理的に物惜しみしない)
kind(一般的な美徳)
gentle(特別な愛情を感じる)
2014年9月29日月曜日
チェンジ・ザ・ルール!/エリヤフ・ゴールドラット
「IT投資によるテクノロジー装備だけでは、利益向上にはつながらない。なぜなら、何もルールが変わっていないからだ」というのが、本書のテーマといっていい。
IT投資をして、企業にどんなメリットがあるのか、突きつめていえば、「利益がどれだけ増えるのか」という疑問に答えるのは、意外と難しいのかもしれない。
本書でも、ERPソフト開発企業のCEOとグループ会社のシステム・インテグレーター企業のCEOが、突然、顧客から問いただされる。お宅のソフトを導入して、結局、利益はいくら増えたのか?と。
二人のCEOは、「企業活動が一元把握できる」、「決算レポートの作成が大幅に短縮できて、コストや作業が大幅に削減できた」、「トランザクションの処理コストが減った」ことなどを主張するが、顧客は納得しない。
この点について、本書に面白い記述がある。
企業のトップマネジメントが何を考えているか、知る由もない社員たちは、コンピュータシステムの専門用語を使って話し、
中間管理職のマネージャーは、生産性向上、コスト削減、リードタイム短縮といった用語を使って話し、
トップマネジメントは、純利益や投資収益率というような用語を使って話す。
この三階層の人々は、各々、別の用語を使っていて、実はお互いの用語が理解できていない。
特に社員や中間管理職は自分のフィールドの用語を別の用語に変換しなければならないという話だ。
二人のCEOは、自分たちのことばでは顧客を納得させることができず、数多くの導入効果(インボイスの印刷ミスの削減まで)を20個拾い上げたが、結局、顧客に説明できそうなものは3個だけだった。
この事をきっかけに、ERPソフト企業のCEOは、自分たちのソフトを使って本当に業績改善を実現できた企業は、ごく一部の企業であることに気づき、最も改善した一社のCEOに話を聞く。
そして、本当に利益を上げるためには、ソフトを導入するだけではなく、「古いルール」を見直さなければならないことに気づく。
「古いルール」とは、分かりやすく言うと、「部分最適化ルール」と呼ばれるもので、まだ必要なデータや情報が全て用意されていない状態で、意思決定をしなければならなかった際に活用されていたルールの事だ。
ERPソフトというものは、企業活動の全体最適化を目指すものだから、必然的に「古いルール」は適合しなくなり、最大の制約条件になってしまう。
この「古いルール」を取っ払って、新しいルールに変更することは、一般的には、ERPソフト企業、SIerの役割ではない。そして、言うほど簡単なことではない。
本書でも、顧客から、現場の幹部社員を説得することを、ERPソフト企業のCEOが頼まれることになる。
CEOは、顧客の批判的な幹部社員に対し、現状のルールを変更しないことによって生じた現実の問題を認識させ、新しいルール(基準)を自分たちに検討させ、決定させるように、巧みに誘導する。
ERPソフト企業のCEOは、これを契機に、「単なるテクノロジーを売るという考え方から、バリューを売る」という経営方針にシフトし、顧客の業務に踏み込んだ提案を行うことで、次第にシュリンクしてゆく売上を倍増しようと決意する。
これは、ちまたで言われている“ソリューション(解決方法)”の提供と同じ意味だろう。
日本のIT業界でも、“ソリューション”ということばが氾濫しているが、この本のような目覚ましい利益改善を行った事例はごく稀な事なのではないかと思う。
そして、このような働きを見せたERPソフト企業に、顧客は、さらに大きな仕事のチャンスを与えることになる。
ゴールドラットの本は、最初に興味本位で読み始めたが、意外と面白い。
本書では、今や懐かしい“西暦2000年問題”が話題として出てくる。
2002年当時の本ではあるが、今読んでも、大きな差異はない。
それは、この本がIT投資の本質を捉えているからだと思う。
IT投資をして、企業にどんなメリットがあるのか、突きつめていえば、「利益がどれだけ増えるのか」という疑問に答えるのは、意外と難しいのかもしれない。
本書でも、ERPソフト開発企業のCEOとグループ会社のシステム・インテグレーター企業のCEOが、突然、顧客から問いただされる。お宅のソフトを導入して、結局、利益はいくら増えたのか?と。
二人のCEOは、「企業活動が一元把握できる」、「決算レポートの作成が大幅に短縮できて、コストや作業が大幅に削減できた」、「トランザクションの処理コストが減った」ことなどを主張するが、顧客は納得しない。
この点について、本書に面白い記述がある。
企業のトップマネジメントが何を考えているか、知る由もない社員たちは、コンピュータシステムの専門用語を使って話し、
中間管理職のマネージャーは、生産性向上、コスト削減、リードタイム短縮といった用語を使って話し、
トップマネジメントは、純利益や投資収益率というような用語を使って話す。
この三階層の人々は、各々、別の用語を使っていて、実はお互いの用語が理解できていない。
特に社員や中間管理職は自分のフィールドの用語を別の用語に変換しなければならないという話だ。
二人のCEOは、自分たちのことばでは顧客を納得させることができず、数多くの導入効果(インボイスの印刷ミスの削減まで)を20個拾い上げたが、結局、顧客に説明できそうなものは3個だけだった。
この事をきっかけに、ERPソフト企業のCEOは、自分たちのソフトを使って本当に業績改善を実現できた企業は、ごく一部の企業であることに気づき、最も改善した一社のCEOに話を聞く。
そして、本当に利益を上げるためには、ソフトを導入するだけではなく、「古いルール」を見直さなければならないことに気づく。
「古いルール」とは、分かりやすく言うと、「部分最適化ルール」と呼ばれるもので、まだ必要なデータや情報が全て用意されていない状態で、意思決定をしなければならなかった際に活用されていたルールの事だ。
ERPソフトというものは、企業活動の全体最適化を目指すものだから、必然的に「古いルール」は適合しなくなり、最大の制約条件になってしまう。
この「古いルール」を取っ払って、新しいルールに変更することは、一般的には、ERPソフト企業、SIerの役割ではない。そして、言うほど簡単なことではない。
本書でも、顧客から、現場の幹部社員を説得することを、ERPソフト企業のCEOが頼まれることになる。
CEOは、顧客の批判的な幹部社員に対し、現状のルールを変更しないことによって生じた現実の問題を認識させ、新しいルール(基準)を自分たちに検討させ、決定させるように、巧みに誘導する。
ERPソフト企業のCEOは、これを契機に、「単なるテクノロジーを売るという考え方から、バリューを売る」という経営方針にシフトし、顧客の業務に踏み込んだ提案を行うことで、次第にシュリンクしてゆく売上を倍増しようと決意する。
これは、ちまたで言われている“ソリューション(解決方法)”の提供と同じ意味だろう。
日本のIT業界でも、“ソリューション”ということばが氾濫しているが、この本のような目覚ましい利益改善を行った事例はごく稀な事なのではないかと思う。
そして、このような働きを見せたERPソフト企業に、顧客は、さらに大きな仕事のチャンスを与えることになる。
ゴールドラットの本は、最初に興味本位で読み始めたが、意外と面白い。
本書では、今や懐かしい“西暦2000年問題”が話題として出てくる。
2002年当時の本ではあるが、今読んでも、大きな差異はない。
それは、この本がIT投資の本質を捉えているからだと思う。
2014年9月28日日曜日
NHKスペシャル シリーズ東日本大震災 私たちの町が生まれた ~集団移転・3年半の記録~
東日本大震災で、津波によって壊滅的な被害を蒙った宮城県岩沼市の、新しい街づくりの試行錯誤が紹介されていて、とても興味深い内容でした。
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0927/
被害にあった多くのひとたちは、仮設住宅での生活を余儀なくされたが、市が用意した海から離れた内陸の田んぼ約20ヘクタールを約2メートルかさ上げして造成した土地に、ようやく、自分の家を持つことができるようになった。
震災から3年半、人口1,000人を超える被災者の集団移転としては、異例の速さらしい。
番組では、その秘密を探っていたが、岩沼市では、震災発生直後に避難者を同じ集落ごとに同じ避難所に集まるよう指示していたらしい。
この恐ろしいほど、先見的な指示を出した前市長は、阪神淡路大震災のサポートを経験した際に、気心が分かった人々の助けがあることが、いかに困難を乗り越えることに大きな役割を果たすかということに気づいていた。
これにより、多くの住民は、震災直後も、仮設住宅に移ってからも、同じコミュニティ、結びつきを壊さず、生活することができた。
その後の岩沼市の対応もすばらしく、街のデザインを住民に押しつけることなく、街づくりの専門家を招き、グループに分かれ、住民ひとりひとりの意見や希望を出し合い、模造紙に付箋で貼りつけ、共通するキーワードを探し出し、それをもとに街のデザインを白地図に描き、模型を作り、自分たちがどのような街づくりを望んでいるのか、少しずつ明らかにしていく作業を行っていた。
街を囲むように防風林のイグネを植える
住宅を通る道は不自然な直線道路ではなく緩やかなカーブを道路にする
人々が集まる公園は、子どもたちが遊びやすい環境にするために芝生を植える
多くの老人が住む公営災害住宅は人々とのコミュニケーションが分断されないように置く
さまざまな意見や配慮がなされた理想的な街のかたちが見えてきた。
この作業を行う検討委員会は20回を超える回数をかけて行ったという。
しかし、この一見遠回りにみえる方法が、多くの住民の合意形成を速やかにまとめることに繋がったらしい。
ここまでの岩沼市の対応は、ほぼ満点だが、現実はそうもいかないらしく、残念ながら、市が最終的に住民たちに提示した街づくりの案では、イグネは街路樹に、芝生の公園は、土の公園に変わってしまった。ほかの地区とのバランスや予算が取れないというのが大きな理由らしい。
しかし、この後の住民の対応が素晴らしい。
彼らは、妥協せず、市に頼らずに、自分たちの負担で、イグネと芝生を植えることを決断し、実行したのだ。
番組の最後は、150人近くの老若男女が公園に芝生を植える場面が映っていたが、自分たちの住む街に、これほどの思いと力を結集し注ぐことができるなんて、何かドラマをみているような気持ちになった。
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0927/
被害にあった多くのひとたちは、仮設住宅での生活を余儀なくされたが、市が用意した海から離れた内陸の田んぼ約20ヘクタールを約2メートルかさ上げして造成した土地に、ようやく、自分の家を持つことができるようになった。
震災から3年半、人口1,000人を超える被災者の集団移転としては、異例の速さらしい。
番組では、その秘密を探っていたが、岩沼市では、震災発生直後に避難者を同じ集落ごとに同じ避難所に集まるよう指示していたらしい。
この恐ろしいほど、先見的な指示を出した前市長は、阪神淡路大震災のサポートを経験した際に、気心が分かった人々の助けがあることが、いかに困難を乗り越えることに大きな役割を果たすかということに気づいていた。
これにより、多くの住民は、震災直後も、仮設住宅に移ってからも、同じコミュニティ、結びつきを壊さず、生活することができた。
その後の岩沼市の対応もすばらしく、街のデザインを住民に押しつけることなく、街づくりの専門家を招き、グループに分かれ、住民ひとりひとりの意見や希望を出し合い、模造紙に付箋で貼りつけ、共通するキーワードを探し出し、それをもとに街のデザインを白地図に描き、模型を作り、自分たちがどのような街づくりを望んでいるのか、少しずつ明らかにしていく作業を行っていた。
街を囲むように防風林のイグネを植える
住宅を通る道は不自然な直線道路ではなく緩やかなカーブを道路にする
人々が集まる公園は、子どもたちが遊びやすい環境にするために芝生を植える
多くの老人が住む公営災害住宅は人々とのコミュニケーションが分断されないように置く
さまざまな意見や配慮がなされた理想的な街のかたちが見えてきた。
この作業を行う検討委員会は20回を超える回数をかけて行ったという。
しかし、この一見遠回りにみえる方法が、多くの住民の合意形成を速やかにまとめることに繋がったらしい。
ここまでの岩沼市の対応は、ほぼ満点だが、現実はそうもいかないらしく、残念ながら、市が最終的に住民たちに提示した街づくりの案では、イグネは街路樹に、芝生の公園は、土の公園に変わってしまった。ほかの地区とのバランスや予算が取れないというのが大きな理由らしい。
しかし、この後の住民の対応が素晴らしい。
彼らは、妥協せず、市に頼らずに、自分たちの負担で、イグネと芝生を植えることを決断し、実行したのだ。
番組の最後は、150人近くの老若男女が公園に芝生を植える場面が映っていたが、自分たちの住む街に、これほどの思いと力を結集し注ぐことができるなんて、何かドラマをみているような気持ちになった。
2014年9月22日月曜日
理科系の作文技術/木下是雄
物理学者である著者が、理科系の研究者・技術者・学生のために、論文・レポート・説明書・ビジネスレターの書き方や、学会講演のコツなどを説明した文章読本。
本書では、理科系の文書の特徴は、読者に伝えるべき内容が、事実と意見にかぎられていて、心情的要素を含まないことにあると述べている。
そして、そのような性質をもった理科系の文書を書くときの心得として、
・主題について述べるとき事実と意見を十分に精選し、
・それらを、事実と意見とを峻別しながら、順序よく、明快・簡潔に記述する
ことと要約している。
これは、特に理科系の仕事をしていなくとも、ビジネス文書を書く人であれば、誰にでも役立つ心得と言っていい。
文章には、poetryを含んだ文学的な文章と、論理性と簡潔明快を必要とする実務的な文章の2種類があるが、一般の人が社会生活で読み書きを求められる文章はどちらかといえば、圧倒的に後者だ。
しかし、日本の国語教育が上記の必要性に対応しているかは、あやしい。
以前、丸谷才一氏が、日本の大学入試試験の国語の問題が、あまりにも文学趣味に偏向していることを批判していたが、本書においても、日本の学校における作文教育は文学に偏向している点を指摘している。
本書で述べられている数々の文章作成の技術の中で、わたしにとって参考になった点は、以下のとおりでした。
・重点先行主義
書き出しの文章を読めばその文書に述べてある最も重要なポイントがわかるようにする
・はっきりと言い切る姿勢
「であろう」「思われる」「ほぼ」「約」「ほど」「ぐらい」「たぶん」「ような」「らしい」といった類の言葉をできるだけ削る
・まぎれもない文を
一義的にしか読めない文、意味が二通りにとれない、誤解されない文を書く
・受け身の文を避ける
「と思われる」「と考えられる」といった受け身の文は、単に「と思う」「と考える」という能動態の文に変えたほうが、文章が短くなり読みやすくなるとともに、主体が「わたし」であることが明白になる
このほかにも、学会講演のコツ――プレゼンテーションの極意が書かれていて、三十年前の本ではあるが、今読んでも役に立つ内容が書かれていると思った。
意外と、自分は文章を書く技術に自信があると自負している文科系の人にこそ、最適な本かもしれない。
本書では、理科系の文書の特徴は、読者に伝えるべき内容が、事実と意見にかぎられていて、心情的要素を含まないことにあると述べている。
そして、そのような性質をもった理科系の文書を書くときの心得として、
・主題について述べるとき事実と意見を十分に精選し、
・それらを、事実と意見とを峻別しながら、順序よく、明快・簡潔に記述する
ことと要約している。
これは、特に理科系の仕事をしていなくとも、ビジネス文書を書く人であれば、誰にでも役立つ心得と言っていい。
文章には、poetryを含んだ文学的な文章と、論理性と簡潔明快を必要とする実務的な文章の2種類があるが、一般の人が社会生活で読み書きを求められる文章はどちらかといえば、圧倒的に後者だ。
しかし、日本の国語教育が上記の必要性に対応しているかは、あやしい。
以前、丸谷才一氏が、日本の大学入試試験の国語の問題が、あまりにも文学趣味に偏向していることを批判していたが、本書においても、日本の学校における作文教育は文学に偏向している点を指摘している。
遠足についての作文は、「どこに行って何をし、何を見たか」がどれほど正確に、簡潔に書けているかによってではなく、書いたこどもの、またその仲間の心情の動きがどれだけ生き生きと描かれているかによって評価される。この本の著者は、上記の作文教育の必要性を認めながらも、「正確に情報をつたえ、筋道を立てて意見を述べることを目的とする作文の教育――つまり仕事の文書の文章表現の基礎になる教育」 の必要性を述べている。
本書で述べられている数々の文章作成の技術の中で、わたしにとって参考になった点は、以下のとおりでした。
・重点先行主義
書き出しの文章を読めばその文書に述べてある最も重要なポイントがわかるようにする
・はっきりと言い切る姿勢
「であろう」「思われる」「ほぼ」「約」「ほど」「ぐらい」「たぶん」「ような」「らしい」といった類の言葉をできるだけ削る
・まぎれもない文を
一義的にしか読めない文、意味が二通りにとれない、誤解されない文を書く
・受け身の文を避ける
「と思われる」「と考えられる」といった受け身の文は、単に「と思う」「と考える」という能動態の文に変えたほうが、文章が短くなり読みやすくなるとともに、主体が「わたし」であることが明白になる
このほかにも、学会講演のコツ――プレゼンテーションの極意が書かれていて、三十年前の本ではあるが、今読んでも役に立つ内容が書かれていると思った。
意外と、自分は文章を書く技術に自信があると自負している文科系の人にこそ、最適な本かもしれない。
2014年9月21日日曜日
終物語 中/西尾維新
本書は、猫物語(白)の事件と同時期に、阿良々木暦と神原駿河が巻き込まれていた別の事件の物語だ。
吸血鬼である忍野忍(キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード)の最初の眷属であった"初代怪異殺し"が復活し、忍野忍に復縁を迫るという、ある意味、男女関係のもつれみたいなものが物語の根本なのだが、吸血鬼化した彼が復活することで、"この街"の安定が乱れるのを阻止するため、臥煙伊豆湖とバンパイア・ハーフのエピソードが、"初代怪異殺し"の完全復活を阻止しようと、阿良々木暦と神原駿河に仕事を依頼するところからはじまる。
猫物語(白)で謎だった以下の事柄
羽川が野宿をしようとした学習塾跡のビルが、なぜかボロボロになっていたこと、
ビルが火事になった時の様子、
阿良々木が神原に依頼したこと、
猫物語(白)で、羽川翼が遭遇していた臥煙伊豆湖とエピソードが当時、何をしていたか、
羽川翼の自撮り写真を阿良々木が受け取った際の状況、
阿良々木が羽川翼に駆けつけた際、なぜ、彼の服がボロボロになっていたか等
が、明かされる。
正直なところ、物語としては、忍野忍と神原駿河の喧嘩の場面、阿良々木が神原に頼まれて買ったBLの本と、臥煙伊豆湖似の熟女写真集が、それぞれ、エピソードと臥煙の手元に渡ってしまったしまったというオチ以外は、今一つという印象だった。
特に、"初代怪異殺し"という男と、忍の関係が、どんなものだったか、リアリティを感じるほど、深く語られておらず、平板で奥行きがないと感じたせいだと思う。
でも、たぶん、アニメだったら、そこそこ面白いものができると思う。
吸血鬼である忍野忍(キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード)の最初の眷属であった"初代怪異殺し"が復活し、忍野忍に復縁を迫るという、ある意味、男女関係のもつれみたいなものが物語の根本なのだが、吸血鬼化した彼が復活することで、"この街"の安定が乱れるのを阻止するため、臥煙伊豆湖とバンパイア・ハーフのエピソードが、"初代怪異殺し"の完全復活を阻止しようと、阿良々木暦と神原駿河に仕事を依頼するところからはじまる。
猫物語(白)で謎だった以下の事柄
羽川が野宿をしようとした学習塾跡のビルが、なぜかボロボロになっていたこと、
ビルが火事になった時の様子、
阿良々木が神原に依頼したこと、
猫物語(白)で、羽川翼が遭遇していた臥煙伊豆湖とエピソードが当時、何をしていたか、
羽川翼の自撮り写真を阿良々木が受け取った際の状況、
阿良々木が羽川翼に駆けつけた際、なぜ、彼の服がボロボロになっていたか等
が、明かされる。
正直なところ、物語としては、忍野忍と神原駿河の喧嘩の場面、阿良々木が神原に頼まれて買ったBLの本と、臥煙伊豆湖似の熟女写真集が、それぞれ、エピソードと臥煙の手元に渡ってしまったしまったというオチ以外は、今一つという印象だった。
特に、"初代怪異殺し"という男と、忍の関係が、どんなものだったか、リアリティを感じるほど、深く語られておらず、平板で奥行きがないと感じたせいだと思う。
でも、たぶん、アニメだったら、そこそこ面白いものができると思う。
これで、ついに全部読み切ってしまった。
しかし、なんと、続・終物語という本が、今月、出版されたらしい(どんな内容なんだろう)。
話がずれてしまうが、どんな内容なんだろうと言えば、本書に出てくる 山本周五郎の小説「美少女一番乗り」も、とても気になる(題名がすごい)。
しかし、なんと、続・終物語という本が、今月、出版されたらしい(どんな内容なんだろう)。
話がずれてしまうが、どんな内容なんだろうと言えば、本書に出てくる 山本周五郎の小説「美少女一番乗り」も、とても気になる(題名がすごい)。
2014年9月20日土曜日
実践 日本人の英語/マーク・ピーターセン
この本は、日本人が書きがちな、ちょっとおかしな英文、下手な英文を見本にして、何が悪いのか、何が野暮ったいのかを分かりやすく説明している本なのだが、一読して、ことごとく、自分が書いてきた英文が見本になっているのではないかと錯覚をおかしてしまう程、私にはぴったりの本だった。
200ページ程の薄い岩波新書だが、以下、私がためになった点を羅列してみよう。
・「AのB」を表現するときは、カンマやin、toで代用し、of の多用を減らすことができる
・副詞(only,just)は、文頭でなく、修飾する語の直前に置く
・practicallyは、「実際には」「実用的に」より「ほとんど~も同然」の意味が一般的であること
・接続詞(because, and, since, as, so, for)は、因果関係の強弱でいうと、soがbecauseやsinceより因果関係が強く、andが緩いつながりには最適であること
・as,forは、文章などフォーマルな場面で用いるのに適していること
・so と veryの使い方
・As a resultは強い因果関係がある場合のみ
・becauseは、通常、単独の文章でなく、従属節でしか用いないこと
・I think は、意見を述べる場面でもないのに使用すると不自然になる
・however, for example, of course, consequently,obviously等の副詞・副詞句も、文頭に置かず、文中に置くほうが洗練された文章になること
・「等」は、and so on より、 etc. のほうがよく、もしくは、such...as、includingを使う方法もある
・今日(こんにち)は、These days より、At present, Nowのほうがいい
・分詞構文は、becauseの代わりになること
以上である。
特に接続詞について、私は、上記とは、ほぼ正反対の感覚で使用していた(soを緩い感覚で使っていた)ので、非常に勉強になりました。
読んでいて思ったのは、しかし、結局、自分が伝えたいことがなにかをよく考え、整理してから、文章を書くことが重要なのだという当たり前のことでした。
この本の中でも、「当たり前のこと」、「子供でも知っていること」を、冒頭の文章に書くことは、特に英語圏の読者には、誰のために、こんな当たり前の事を書いているのだろう?と、印象を害することになってしまう点を指摘している。
最も、読者に伝えたいことは何なのか、頭の中で吟味してから、一文を書く。
これは、日本語の文章でも同じことだと思う。
200ページ程の薄い岩波新書だが、以下、私がためになった点を羅列してみよう。
・「AのB」を表現するときは、カンマやin、toで代用し、of の多用を減らすことができる
・副詞(only,just)は、文頭でなく、修飾する語の直前に置く
・practicallyは、「実際には」「実用的に」より「ほとんど~も同然」の意味が一般的であること
・接続詞(because, and, since, as, so, for)は、因果関係の強弱でいうと、soがbecauseやsinceより因果関係が強く、andが緩いつながりには最適であること
・as,forは、文章などフォーマルな場面で用いるのに適していること
・so と veryの使い方
・As a resultは強い因果関係がある場合のみ
・becauseは、通常、単独の文章でなく、従属節でしか用いないこと
・I think は、意見を述べる場面でもないのに使用すると不自然になる
・however, for example, of course, consequently,obviously等の副詞・副詞句も、文頭に置かず、文中に置くほうが洗練された文章になること
・「等」は、and so on より、 etc. のほうがよく、もしくは、such...as、includingを使う方法もある
・今日(こんにち)は、These days より、At present, Nowのほうがいい
・分詞構文は、becauseの代わりになること
以上である。
特に接続詞について、私は、上記とは、ほぼ正反対の感覚で使用していた(soを緩い感覚で使っていた)ので、非常に勉強になりました。
読んでいて思ったのは、しかし、結局、自分が伝えたいことがなにかをよく考え、整理してから、文章を書くことが重要なのだという当たり前のことでした。
この本の中でも、「当たり前のこと」、「子供でも知っていること」を、冒頭の文章に書くことは、特に英語圏の読者には、誰のために、こんな当たり前の事を書いているのだろう?と、印象を害することになってしまう点を指摘している。
最も、読者に伝えたいことは何なのか、頭の中で吟味してから、一文を書く。
これは、日本語の文章でも同じことだと思う。
2014年9月15日月曜日
ザ・ゴール 2 思考プロセス/エリヤフ・ゴールドラット
前作で閉鎖寸前の工場を立て直した工場長 アレックスは、本作では、多角化事業の副社長(グループ子会社の統括責任者)に出世している。
しかし、このグループ子会社の経営が、投資した分に対するリターンが足りないということから、親会社の取締役会で、グループ子会社3社の売却が決定される。
その3社とは、前作でアレックスの部下であったボブとステーシー、そして、アレックスの考えをよく理解しているピートが社長として経営している子会社であった。
会社を買収しておいて、親会社として何ら支援せず、経営が悪くなったら、即、売却という、いかにもありそうなグループ企業におけるM&Aの話なのだが、売却を推し進めるジムとブランドンという極めてドライな社外取締役の存在もリアリティがある。
アレックスは、売却までの6ヵ月の間に、これら3社の業績を急激に改善させ、なんとか、売却の決定を覆そうとするため、彼の経営手法の師匠であるジョナ(物理学者)から教わった思考プロセスを用いて、この難題を切り抜けようとする。
・現状問題構造ツリー
・雲(Cloud)
・未来問題構造ツリー
・前提条件ツリー
・移行ツリー
これらが、その思考プロセスを実行するツールとして紹介される。物語中でも、アレックスの子供たちからのちょっとした要求に対する解決策として簡単な事例が、さらには、社外取締役に自分の考えを理解を説得するために書いた複雑な事例が紹介されていたが、正直、これを自分が使いこなせるのは難しいという印象でした。
でも、社外取締役が、いつしか、アレックスの説得に耳を貸してしまうように、何も考えないで経験と勘に頼る経営手法よりは、魅力的で、はるかに好感を持てました。
*この思考プロセスについて、webでも検索すると、たくさんの紹介記事を見ることが出来ます。
私が最も感心したのは、M&Aで売却しようとする企業を、as-is(あるがままの姿)で、売るのではなく、しっかりとした経営手法を持たせ、やれるとこるとまで業績を回復し、買い手にとっても魅力的な企業に改良させてから、高値と好条件で売却するというwin-winのスタンスである。
(日本の場合、業績が落ち込んだ子会社を投げ売りするのに近いのが実情ではないでしょうか? もっとも、この本に出てくるほど、子会社が業績を回復してしまったら、たぶん売却の話自体、消えてしまうのでしょうね)
新たな売却先で活躍することを想像し、(株式譲渡契約をチェックしていると思われる)弁護士に対して、「あの弁護士、何をグズグズしてるんだ!」と愚痴るボブの姿は、ある意味、成功したM&Aの理想的な姿を描いているのかもしれませんね。
しかし、このグループ子会社の経営が、投資した分に対するリターンが足りないということから、親会社の取締役会で、グループ子会社3社の売却が決定される。
その3社とは、前作でアレックスの部下であったボブとステーシー、そして、アレックスの考えをよく理解しているピートが社長として経営している子会社であった。
会社を買収しておいて、親会社として何ら支援せず、経営が悪くなったら、即、売却という、いかにもありそうなグループ企業におけるM&Aの話なのだが、売却を推し進めるジムとブランドンという極めてドライな社外取締役の存在もリアリティがある。
アレックスは、売却までの6ヵ月の間に、これら3社の業績を急激に改善させ、なんとか、売却の決定を覆そうとするため、彼の経営手法の師匠であるジョナ(物理学者)から教わった思考プロセスを用いて、この難題を切り抜けようとする。
・現状問題構造ツリー
・雲(Cloud)
・未来問題構造ツリー
・前提条件ツリー
・移行ツリー
これらが、その思考プロセスを実行するツールとして紹介される。物語中でも、アレックスの子供たちからのちょっとした要求に対する解決策として簡単な事例が、さらには、社外取締役に自分の考えを理解を説得するために書いた複雑な事例が紹介されていたが、正直、これを自分が使いこなせるのは難しいという印象でした。
でも、社外取締役が、いつしか、アレックスの説得に耳を貸してしまうように、何も考えないで経験と勘に頼る経営手法よりは、魅力的で、はるかに好感を持てました。
*この思考プロセスについて、webでも検索すると、たくさんの紹介記事を見ることが出来ます。
私が最も感心したのは、M&Aで売却しようとする企業を、as-is(あるがままの姿)で、売るのではなく、しっかりとした経営手法を持たせ、やれるとこるとまで業績を回復し、買い手にとっても魅力的な企業に改良させてから、高値と好条件で売却するというwin-winのスタンスである。
(日本の場合、業績が落ち込んだ子会社を投げ売りするのに近いのが実情ではないでしょうか? もっとも、この本に出てくるほど、子会社が業績を回復してしまったら、たぶん売却の話自体、消えてしまうのでしょうね)
新たな売却先で活躍することを想像し、(株式譲渡契約をチェックしていると思われる)弁護士に対して、「あの弁護士、何をグズグズしてるんだ!」と愚痴るボブの姿は、ある意味、成功したM&Aの理想的な姿を描いているのかもしれませんね。
2014年9月9日火曜日
ザ・ゴール/エリヤフ・ゴールドラット
今日、NHKのニュースで、走行距離が長い電気自動車の販売を開始したテスラモーターズのイーロン マスク氏のインタビューが放映されていた。
彼は、アップルの亡くなったジョブス氏のような力を持った次世代の経営者として注目されている人物らしく、彼が手がけるビジネスは、電気自動車だけでなく、太陽光エネルギー、宇宙ビジネスなど、とても幅が広い。
そのマスク氏が、このようなイノベーションを起こせているのは、自分が学んだ物理学の考え方が活きているのだと思う。物理学の物の見方は常識にとらわれることなく真実を見定めることができるから、とコメントしているのを見て、エリヤフ・ゴールドラット氏が書いた「ザ・ゴール」のことが、ふと頭を過った。
この「ザ・ゴール」では、不採算を理由に工場閉鎖を迫られた主人公の工場長アレックスが、彼の恩師である物理学者 ジョナの助言を得て、工場の生産現場の諸問題を、それまでの常識的な考えにとらわれることなく、科学的な分析に基づき解明してゆき、わずか3ヶ月の間に、工場の経営を立て直したという物語だ。
まず、企業の究極の目的は、金を儲け続けること、と潔く認めてしまうところが良い。
企業価値の提供とか、社会貢献とかより、よほど分かりやすい。
そして、その目的の達成のためには、①スループット(製品の販売を通じてお金を作り出す割合。)を増やすか、②在庫を減らすか、③業務費用(経費)を減らすという3つの方法しかない。
重要度は、番号のとおり、スループットが一番重要。
工場のスループットを最大化するためには、実際に顧客に売れるアウトプットを最大にすればよいのだが、実際には、その工程のどこかで、制約条件(ボトルネック)があり、このボトルネックの生産能力で、工場の生産量が決まってしまう。
よって、このボトルネックに改善努力を集中して、その生産能力を最大に引き上げる必要がある。
だから、ボトルネック工程の前には常に適切な在庫を用意し、ボトルネックが無動状態に陥ることがないようにしなければならない。(ボトルネック工程の停止は工場全体の停止を意味する)
面白いのは、ボトルネック工程の前に置く在庫以外の在庫を作り出す非ボトルネック工程では、無動が発生してもよいという考え方だ。つまり、作業員や機械を遊ばせておいてもよいということ。
非ボトルネック工程で人や機械をたくさん働かせても、工場の生産性は向上せず、むしろ、余剰在庫を作り出すだけで、目的に反することになってしまうことになるらしい。
工場の生産管理は、工程とアウトプットするものが明確なだけに、案外、科学な解法が馴染みやすいものなのかもしれない。
全く興味がない分野だったが、常識的な考えを一旦捨てて、科学的な見地からみると、思いもしないところに原因があることが分かるというプロセスは、なかなか面白いものだと思う。
彼は、アップルの亡くなったジョブス氏のような力を持った次世代の経営者として注目されている人物らしく、彼が手がけるビジネスは、電気自動車だけでなく、太陽光エネルギー、宇宙ビジネスなど、とても幅が広い。
そのマスク氏が、このようなイノベーションを起こせているのは、自分が学んだ物理学の考え方が活きているのだと思う。物理学の物の見方は常識にとらわれることなく真実を見定めることができるから、とコメントしているのを見て、エリヤフ・ゴールドラット氏が書いた「ザ・ゴール」のことが、ふと頭を過った。
この「ザ・ゴール」では、不採算を理由に工場閉鎖を迫られた主人公の工場長アレックスが、彼の恩師である物理学者 ジョナの助言を得て、工場の生産現場の諸問題を、それまでの常識的な考えにとらわれることなく、科学的な分析に基づき解明してゆき、わずか3ヶ月の間に、工場の経営を立て直したという物語だ。
まず、企業の究極の目的は、金を儲け続けること、と潔く認めてしまうところが良い。
企業価値の提供とか、社会貢献とかより、よほど分かりやすい。
そして、その目的の達成のためには、①スループット(製品の販売を通じてお金を作り出す割合。)を増やすか、②在庫を減らすか、③業務費用(経費)を減らすという3つの方法しかない。
重要度は、番号のとおり、スループットが一番重要。
工場のスループットを最大化するためには、実際に顧客に売れるアウトプットを最大にすればよいのだが、実際には、その工程のどこかで、制約条件(ボトルネック)があり、このボトルネックの生産能力で、工場の生産量が決まってしまう。
よって、このボトルネックに改善努力を集中して、その生産能力を最大に引き上げる必要がある。
だから、ボトルネック工程の前には常に適切な在庫を用意し、ボトルネックが無動状態に陥ることがないようにしなければならない。(ボトルネック工程の停止は工場全体の停止を意味する)
面白いのは、ボトルネック工程の前に置く在庫以外の在庫を作り出す非ボトルネック工程では、無動が発生してもよいという考え方だ。つまり、作業員や機械を遊ばせておいてもよいということ。
非ボトルネック工程で人や機械をたくさん働かせても、工場の生産性は向上せず、むしろ、余剰在庫を作り出すだけで、目的に反することになってしまうことになるらしい。
工場の生産管理は、工程とアウトプットするものが明確なだけに、案外、科学な解法が馴染みやすいものなのかもしれない。
全く興味がない分野だったが、常識的な考えを一旦捨てて、科学的な見地からみると、思いもしないところに原因があることが分かるというプロセスは、なかなか面白いものだと思う。
2014年9月8日月曜日
日本人の英語/マーク・ピーターセン
英文メールを作成する際、よく悩むのは、 a と the の選択である。
本書では、冒頭で、いきなり、不定冠詞の問題について解説している。
Last night, I ate a chicken in the backyard.
昨夜、鶏を1羽 [捕まえて、そのまま] 裏庭で食べ [てしまっ] た。
原因は、 a chicken (ある1羽の鶏)と書いてしまったこと。
正しくは、 chicken(鶏肉)。
日本人的な感覚では、まず名詞があって、その名詞が特定か、不特定か、可算か不可算かを考えて、aとtheを選択して付ける。
しかし、ネィティブは、まず、a を選択し、その次に名詞を探すという驚くべき思考プロセスが以下のように述べられている。
もし食べ物として伝えたいものが、一つの形の決まった、単位性を持つ物ならば、
"I ate a...a...a hotdog!"(あるいはa sandwich, a rice ballなど)と、
aを繰り返しつつ、思い出しながら名詞を探していくことになる。
もし食べた物として伝えたいものが単位性もない、何の決まった形もない、材料的な物ならば、おそらく
"I ate uh...uh...meat!"(あるいはFrench bread,riceなど)と思い出していうであろう。
つまり、aというのは、その有無が一つの論理的プロセスの根幹となるものであって、名詞につくアクセサリーのようなものではないということだ。また、定冠詞のtheについては、日本人が余計なtheを付けたがる傾向があることを指摘している。
The international understanding is a commonly import problem in both the West and the Japan.
という文章は、読むほうからすると"The international understanding"って何?
特定の「国際理解」を指しているのか?
しかし、その後の説明が何もない…という疑問をいだいてしまうらしい。
正しい文章は、以下のとおり。
International understanding is an issue of wide importance to both Japan and the West.
(国際理解は日本にとっても西洋にとっても様々な面で重要な問題である)
英語の「the感覚」を養うためには、正しい文章を読んで、読んで、読むこと(read,read,read)が何よりで、文脈の中で、その意味が具体的にどういうふうに限定されてきているかを丹念に分析しながら読むのが、もっとも効果的であるとのこと。
また、
a、the、ゼロ冠詞の使い分けに関してのルールは、結局のところ一つしかないと言ってもよいと思う。それは「冠詞の使用不使用は文脈がすべて」という結論だ。
近道はないというのが、真実なのだろう。
本書は、1988年初版の本でありながら、文章も簡潔で、例文も今読んでも耐えられる内容になっている。
a と the の使い方で、よく戸惑う方には、お勧めの本だ。
2014年9月7日日曜日
終物語 下/西尾維新
「終物語 中」を飛ばして、いきなり本書を読んでしまった。
実質、最終話を思わせる内容だったため、やはり、こういうシリーズものは、順番通りに読んでいったほうがよいと今さらながらに思った。
ということで、ここは、私が初めて知った単語の意味など述べて、お茶を濁すことにしよう。
実質、最終話を思わせる内容だったため、やはり、こういうシリーズものは、順番通りに読んでいったほうがよいと今さらながらに思った。
ということで、ここは、私が初めて知った単語の意味など述べて、お茶を濁すことにしよう。
- デペイズマン dépaysement
人を異なった生活環境に置くこと、転じて「居心地の悪さ、違和感、生活環境の変化、気分転換」を意味するフランス語。
シュルレアリスムの手法の1つでもあり、意外な組み合わせを行うことによって、受け手を驚かせ、途方にくれさせるという意味もあるらしい。
羽川 翼が、失踪した忍野メメを捜索するため、世界旅行に旅立ち、その旅の合間に、戦場ヶ原 ひたぎに、電話で、その探し方に間違いがあったという趣旨で語った言葉である。
羽川は、忍野メメという怪異の専門家がいそうな場所ばかり探していたのだが、実は、専門家であれば、絶対に行かない場所にいたのである。
- ジェットセッター jet-setter
自家用ジェット機で好きな時にどこにでも行ってしまう富裕層や、世界を頻繁に旅するビジネスマンのように、ジェット機に乗り世界中を駆け巡る人のことを言うらしい。
羽川翼が、忍野メメを、上記の絶対にいなさそうな場所から、日本に連れ戻してくるにあたり、某機関に自分の頭脳を売り、ジェット機をチャーターして戻って来たということを、後日、阿良々木 暦に述懐した際に使った言葉である。
阿良々木 暦同様、「頭脳を売り」という言葉に、不穏な空気を感じるが、ビットコインの採掘みたいに、ある種の知能を、切り売りしてお金に換金するという仕組みは、実は世の中ですでに出来上がっていることなのかもしれない。
しかし、羽川翼が、なんだか、スーパーウーマン的な存在に仕立て上げられてしまったところは、若干、残念な印象を受ける。
2014年9月5日金曜日
眠る人々/池澤夏樹
池澤夏樹が出した電子書籍を色々買ってみたが、「あれ、これって前に読んだ本にでてるの?」と気づいたのは、読んだ後に、インターネットで作品を検索した時だった。
「骨は珊瑚、眼は真珠」に収められた九つの短編。
表題作と「最後の一羽」だけは、記憶に残っていたが、他の七編は、まるっきり記憶がなかった。
しかし、そのせいで、新作を読むみたいに改めて、これらの作品を楽しむことができた。
いずれも、池澤夏樹らしい短編が並んでいて、今読んでも、ほとんど違和感を感じない。
まだ、この頃はセックスとか男女関係の描写が少ないなと思うぐらい。
しかし、一つだけ違和感を感じた作品があった。
今回、取り上げた「眠る人々」だ。
物語は、三十代ぐらいの男女の2組のカップルが山にある別荘に泊まった時の話で、
一組目は、舞台装置の製作を仕事にしている遼と、料理が上手い厚子のカップル。
二組目は、輸入家具、食器などの販売をしている慎介と、草花に詳しい美那のカップル。
二組のカップルは仲が良く、仕事も順調で、幸わせで成功している人生と言ってよいのだが、遼は、この幸せな状態が続いていくことに漠然とした不安を感じている。
その漠然とした不安を象徴しているのが、彼が見る水の中で眠るたくさんの人々の夢と、彼が時折遭遇するUFOの存在だ。
遼は、自分かの悩みを率直に、三人に話すが、誰にも理解されない。
「骨は珊瑚、眼は真珠」に収められた九つの短編。
表題作と「最後の一羽」だけは、記憶に残っていたが、他の七編は、まるっきり記憶がなかった。
しかし、そのせいで、新作を読むみたいに改めて、これらの作品を楽しむことができた。
いずれも、池澤夏樹らしい短編が並んでいて、今読んでも、ほとんど違和感を感じない。
まだ、この頃はセックスとか男女関係の描写が少ないなと思うぐらい。
しかし、一つだけ違和感を感じた作品があった。
今回、取り上げた「眠る人々」だ。
物語は、三十代ぐらいの男女の2組のカップルが山にある別荘に泊まった時の話で、
一組目は、舞台装置の製作を仕事にしている遼と、料理が上手い厚子のカップル。
二組目は、輸入家具、食器などの販売をしている慎介と、草花に詳しい美那のカップル。
二組のカップルは仲が良く、仕事も順調で、幸わせで成功している人生と言ってよいのだが、遼は、この幸せな状態が続いていくことに漠然とした不安を感じている。
その漠然とした不安を象徴しているのが、彼が見る水の中で眠るたくさんの人々の夢と、彼が時折遭遇するUFOの存在だ。
遼は、自分かの悩みを率直に、三人に話すが、誰にも理解されない。
彼は、別荘の近くに建っている送電線の鉄塔の下まで行き、ぼんやりと空を見上げ、現れたUFOに、自分の悩みを語りかける という物語だ。
まず、めぐまれた生活に身を任せながら、このままで本当に良いのか?という漠然と不安を抱いているという、言ってしまえば、よくありがちな中途半端なスタンスの登場人物は、池澤夏樹の小説では見かけないタイプである。
そして、彼は、その不安と、不安を感じる自分を、深く追及しない。これからも不安を感じながら幸せに生きてゆくということを、UFOに対して、語りかけるだけだ。
この“消極的幸福主義”も、あまり魅力を感じない。
しかし、この小説が書かれたのは1991年。
まだ、バブル崩壊も、阪神淡路大震災も、オウムの事件も、ニューヨーク同時多発テロも、東日本大震災も、原発事故も起きていない。
おそらく、今の池澤夏樹であれば、このような小説を書くことはないだろう。
二十三年も経つと世の中も変わる。
もし、この小説に続編があるならば、おそらく、遼の生き方も、二組のカップルの生き方も大きく変わっていたに違いない。
2014年9月4日木曜日
十二の遍歴の物語/ガルシア・マルケス
ガルシア・マルケスが、「族長の秋」を書き終えた翌年1976年から1982年の間に書いた短編小説集。
その小説が完成する前、ガルシア・マルケスは、子供が使っていた学校用のノートに六十四のテーマを書き込んでいた。
しかし、そのノートを紛失してしまい、何とか三十の物語を再構成した。
さらに、そこから駄目になったテーマをふるい落とし、十八にしぼり、書き進める中で、六つがゴミ箱ゆきになった。
そうして残った十二編を、ガルシア・マルケスは、
「あとに残ったものはしかし、もっと長く生きられる息吹を得たようだった」と評している。
これらの短編小説は、ガルシア・マルケスがヨーロッパの都市 バルセロナ、ジュネーブ、ローマ、パリを巡った旅行の後に、もう一度書き直された。
そのせいか、ガルシア・マルケスが書く、いつもの南米の空気とは異なったヨーロッパの雰囲気を感じる。スタイリッシュというか、物語に抑制が利いているせいか、普通の小説家が書く小説のように感じるのだ。
ただ、ガルシア・マルケス特有の要素は、どの作品にも濃くあらわれている。
例えば、亡命した政治家を優しく世話してあげる夫婦を描いた「大統領閣下、よいお旅を」
あるいは、眠る女性への興味を描いた「眠れる美女の飛行」
超現実の世界を描いた「聖女」、「八月の亡霊」
ファンタジックな「光は水のよう」
老人の性愛を描いた「悦楽のマリア」
理不尽な運命を描いた「電話をかけに来ただけなの」、「雪の上に落ちたお前の血の跡」
1980年前後に、こんな小説をガルシア・マルケスがコツコツ書いていたのだ。
そう思うと、これらの小説の不思議な色に浸されて、記憶にあった80年代の様相や色合いが何となく変わってしまったような気分になる。
その小説が完成する前、ガルシア・マルケスは、子供が使っていた学校用のノートに六十四のテーマを書き込んでいた。
しかし、そのノートを紛失してしまい、何とか三十の物語を再構成した。
さらに、そこから駄目になったテーマをふるい落とし、十八にしぼり、書き進める中で、六つがゴミ箱ゆきになった。
そうして残った十二編を、ガルシア・マルケスは、
「あとに残ったものはしかし、もっと長く生きられる息吹を得たようだった」と評している。
これらの短編小説は、ガルシア・マルケスがヨーロッパの都市 バルセロナ、ジュネーブ、ローマ、パリを巡った旅行の後に、もう一度書き直された。
そのせいか、ガルシア・マルケスが書く、いつもの南米の空気とは異なったヨーロッパの雰囲気を感じる。スタイリッシュというか、物語に抑制が利いているせいか、普通の小説家が書く小説のように感じるのだ。
ただ、ガルシア・マルケス特有の要素は、どの作品にも濃くあらわれている。
例えば、亡命した政治家を優しく世話してあげる夫婦を描いた「大統領閣下、よいお旅を」
あるいは、眠る女性への興味を描いた「眠れる美女の飛行」
超現実の世界を描いた「聖女」、「八月の亡霊」
ファンタジックな「光は水のよう」
老人の性愛を描いた「悦楽のマリア」
理不尽な運命を描いた「電話をかけに来ただけなの」、「雪の上に落ちたお前の血の跡」
1980年前後に、こんな小説をガルシア・マルケスがコツコツ書いていたのだ。
そう思うと、これらの小説の不思議な色に浸されて、記憶にあった80年代の様相や色合いが何となく変わってしまったような気分になる。
2014年9月1日月曜日
海街diary6 四月になれば彼女は/吉田秋生
海街シリーズも6巻目かと思う。
最近、分厚い本ばかり読んでいたので、買った時の本の薄さに久々にびっくりしたが、一読して、とても面白かったし、作品のレベルは下がっていないと思った。
この物語は、意外と人の死に伴う相続のもめごととか、わりと生々しい話に触れている機会が多いのだが、
海猫食堂のおばさんが癌で亡くなる際、おばさんが、不義理の弟には法定相続分だけにして、食堂を手伝い、病気の自分を世話してくれた人たちに対して、残りの全財産を遺贈しようとしたが、相続のアドバイザーをしていた信用金庫の課長が、「あなたの善意があなたの大切な人を傷つけるかもしれない」と諭し、20万円程度の遺贈に抑えたというエピソードは、なるほど、そういうものなのかと考えさせられた。
さらに、その後のおばさんの言葉も。
「死んだ後のことは正直考えてなかったわ 先に死んでいく者の願うことは すべてかなえられると思うのは やっぱり傲慢よね」
こういうのは、法制度だけ理解しても分からない大人の言葉ですね。
こんな大人の対応をする信用金庫の課長に惹かれ、ついに恋を意識し始めた佳乃の邪悪なオーラがいい。(他が、みんな、いい人ばっかりだから)
すずの進路がどうなるのかということも含め、次巻も楽しみ。
最近、分厚い本ばかり読んでいたので、買った時の本の薄さに久々にびっくりしたが、一読して、とても面白かったし、作品のレベルは下がっていないと思った。
この物語は、意外と人の死に伴う相続のもめごととか、わりと生々しい話に触れている機会が多いのだが、
海猫食堂のおばさんが癌で亡くなる際、おばさんが、不義理の弟には法定相続分だけにして、食堂を手伝い、病気の自分を世話してくれた人たちに対して、残りの全財産を遺贈しようとしたが、相続のアドバイザーをしていた信用金庫の課長が、「あなたの善意があなたの大切な人を傷つけるかもしれない」と諭し、20万円程度の遺贈に抑えたというエピソードは、なるほど、そういうものなのかと考えさせられた。
さらに、その後のおばさんの言葉も。
「死んだ後のことは正直考えてなかったわ 先に死んでいく者の願うことは すべてかなえられると思うのは やっぱり傲慢よね」
こういうのは、法制度だけ理解しても分からない大人の言葉ですね。
こんな大人の対応をする信用金庫の課長に惹かれ、ついに恋を意識し始めた佳乃の邪悪なオーラがいい。(他が、みんな、いい人ばっかりだから)
すずの進路がどうなるのかということも含め、次巻も楽しみ。
2014年8月31日日曜日
池澤夏樹が始めた電子書籍
池澤夏樹が株式会社ボイジャーと組んで、自身の作品の電子書籍化を本格的に始めたらしい。
http://dotplace.jp/archives/10786
この記者会見の記事を読むと、ボイジャーの電子書籍ビジネスは、作家の報酬の取り分が、紙の本と比較して格段に高いことが分かる。
紙の本は、通常、作家の取り分は10%
しかし、このボイジャーの電子書籍では、30~40%になるらしい。
これは、作家にとっては大きなインセンティブになるだろう。
もう一つ、目を引いたのは、Romancer(ロマンサー)という出版方法の仕組みである。
https://romancer.voyager.co.jp/
・作家は、自分が書いたWord、PDF等のデータを、Romancerのサイトにアップロードするだけで、簡単に電子書籍が作れる。
・EPUB 3という電子書籍のマスターデータを、作家自身が保持することができ、色んな電子出版会社に提供できる。
・アプリをダウンロードしなくても、Webベースで作品を閲覧することができる。
紙の本の出版を思えば、非常に簡便でオープンな方法と言えよう。
また、既存の出版社に対し、電子書籍の売上の10%を支払うというボイジャーの方針も、ある意味すごい。
日本の出版契約では、出版会社が、その本の独占出版権を持つという契約が一般的である。
つまり、契約を締結すると、以後、その出版会社の承諾を得ない限り、作家本人であっても、出版できないことになってしまう。
池澤夏樹は、記者会見で、紙の出版では、このような出版会社との契約もあり、丸谷才一の全集ですら、全12巻しかまとめることができなかったことを嘆いている。(本当は30巻ぐらいの著作のボリュームがあるらしい)
ボイジャーの戦略の上手いところは、既存の出版会社を敵に回さず、お宅にもフィーを支払うから、電子出版させてくださいよという有効な妥結案を提示しているところだ。
このようなボイジャーの戦略上手も、彼が電子書籍化に踏み切った大きな理由らしい。
日経の記事では、「従来の出版市場が縮小を続ける一方で、電子出版は5年後に3000億円超に成長するとの予測がある」とのこと。
池澤夏樹作品の電子書籍化は、その流れを象徴するような出来事だと感じた。
*最初、池澤夏樹の電子出版した短編小説の感想を書こうと思っていたが、この電子書籍ビジネスの話の方が、思ったよりインパクトが大きいことに気づいた。
http://dotplace.jp/archives/10786
この記者会見の記事を読むと、ボイジャーの電子書籍ビジネスは、作家の報酬の取り分が、紙の本と比較して格段に高いことが分かる。
紙の本は、通常、作家の取り分は10%
しかし、このボイジャーの電子書籍では、30~40%になるらしい。
これは、作家にとっては大きなインセンティブになるだろう。
もう一つ、目を引いたのは、Romancer(ロマンサー)という出版方法の仕組みである。
https://romancer.voyager.co.jp/
・作家は、自分が書いたWord、PDF等のデータを、Romancerのサイトにアップロードするだけで、簡単に電子書籍が作れる。
・EPUB 3という電子書籍のマスターデータを、作家自身が保持することができ、色んな電子出版会社に提供できる。
・アプリをダウンロードしなくても、Webベースで作品を閲覧することができる。
紙の本の出版を思えば、非常に簡便でオープンな方法と言えよう。
また、既存の出版社に対し、電子書籍の売上の10%を支払うというボイジャーの方針も、ある意味すごい。
日本の出版契約では、出版会社が、その本の独占出版権を持つという契約が一般的である。
つまり、契約を締結すると、以後、その出版会社の承諾を得ない限り、作家本人であっても、出版できないことになってしまう。
池澤夏樹は、記者会見で、紙の出版では、このような出版会社との契約もあり、丸谷才一の全集ですら、全12巻しかまとめることができなかったことを嘆いている。(本当は30巻ぐらいの著作のボリュームがあるらしい)
ボイジャーの戦略の上手いところは、既存の出版会社を敵に回さず、お宅にもフィーを支払うから、電子出版させてくださいよという有効な妥結案を提示しているところだ。
このようなボイジャーの戦略上手も、彼が電子書籍化に踏み切った大きな理由らしい。
日経の記事では、「従来の出版市場が縮小を続ける一方で、電子出版は5年後に3000億円超に成長するとの予測がある」とのこと。
池澤夏樹作品の電子書籍化は、その流れを象徴するような出来事だと感じた。
*最初、池澤夏樹の電子出版した短編小説の感想を書こうと思っていたが、この電子書籍ビジネスの話の方が、思ったよりインパクトが大きいことに気づいた。
2014年8月27日水曜日
終物語 上/西尾維新
終物語 上巻は、主人公である阿良々木暦が、「友達を作ると人間強度が下がる」と言うようになったきっかけとなる高校1年生の時の事件、遡って、彼が数学が得意科目となるきっかけとなった中学1年生の時の事件、さらに遡って、阿良々木暦を敵視する複雑な家庭環境の女の子が抱えた事件を、敵か味方か定かでない忍野扇と、彼女と仲が悪い羽川翼がホームズ役となり、阿良々木暦をワトソン役にして、何があったのかを解明していく推理小説仕立ての内容になっている。
忍野扇と、猫物語以降の羽川翼が、互いの推理力で対決するくだりは、読んでいて面白いものがあったが、やはり推理小説仕立てであって、推理小説とは言えないものだった。
そう思う一番の理由は、ほとんどの謎が、まるで痴呆のように記憶を喪失した阿良々木暦が語っていない部分に、真実が隠されているというオチになっているからだ。
この本で、阿良々木暦は怖いくらい重要な過去について記憶を喪失している。
それはたとえ故意でなかったとしても、彼が無意識に真実から目を背けた結果なのだろう。
そして、それはつまり、重要な真実から目をそらした結果、怪異に憑りつかれ、あるいは怪異を生み出してきた羽川、戦場ヶ原、八九寺、神原、千石といった少女たちと、いつも、彼女たちを助けていた阿良々木暦は実は同じ状況にあったということを意味する。
忍野扇と、猫物語以降の羽川翼が、互いの推理力で対決するくだりは、読んでいて面白いものがあったが、やはり推理小説仕立てであって、推理小説とは言えないものだった。
そう思う一番の理由は、ほとんどの謎が、まるで痴呆のように記憶を喪失した阿良々木暦が語っていない部分に、真実が隠されているというオチになっているからだ。
この本で、阿良々木暦は怖いくらい重要な過去について記憶を喪失している。
それはたとえ故意でなかったとしても、彼が無意識に真実から目を背けた結果なのだろう。
そして、それはつまり、重要な真実から目をそらした結果、怪異に憑りつかれ、あるいは怪異を生み出してきた羽川、戦場ヶ原、八九寺、神原、千石といった少女たちと、いつも、彼女たちを助けていた阿良々木暦は実は同じ状況にあったということを意味する。
2014年8月25日月曜日
コレラの時代の愛/ガルシア・マルケス
こんな恋愛小説は、読んだことがない。
なぜなら、主人公の船会社の社長 フロレンティーノ・アリーサと、その初恋の人である有名な医者の未亡人 フェルミーナ・ダーサは、七十歳を過ぎた、死に近い老人なのだから。
物語のはじまりも変わっている。
主人公ではなく、フェルミーナ・ダーサの夫 フベナル・ウルビーノ博士の一日から始まり、彼が事故で死に、フロレンティーノ・アリーサが、夫を亡くしたフェルミーナ・ダーサに愛を誓うところまでを最初に描く。
それは、フロレンティーノ・アリーサが、未亡人 フェルミーナ・ダーサに愛を告白するまで待った、五十一年九ヵ月と四日目だった。
そして、物語は、フロレンティーノ・アリーサとフェルミーナ・ダーサの出会いの時に遡る。
お金はあるが、マフィアのように怪しいビジネスに手を染めている父親を持つ美しい少女フェルミーナ・ダーサと、船会社事業を創設した男の内縁の子として母親に育てられたフロレンティーノ・アリーサ。
二人の出会いと別れ。
そして、フェルミーナ・ダーサの結婚。
数多くの女性と関係しながらも、フロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサを想う心だけは失わずにいた。
そして、決して不幸ではない二人の別々の人生をたどりながら、無情にも年月は過ぎてゆき、物語は最初の場面へと戻ってゆく。
この物語の面白さは、何といっても、主人公がラブレターでもって、相手に愛情を伝えるシーンが多いことだろう。
恋愛への情熱を燃やすフロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサには出せない手紙の思いを持て余し、街の代書屋として、数々のカップルのラブレターを無料で代書するサービスをはじめる。
ある日、内気な感じの女の子が、受け取ったばかりの、答えを返さずにはいられないラブレターに返事を書いてもらえないかと、フロレンティーノ・アリーサに震えながら頼みにくる。
フロレンティーノ・アリーサは、その手紙が自分が前日の午後に書いたものだということに気づく。
彼は、女の子が受けた感動と年齢にふさわしい文体を使い、自分が書いた手紙に対する返事を書いてあげる。
少しずつ、フロレンティーノ・アリーサに惹かれてゆくフェルミーナ・ダーサだったが、この物語は二人の隠しきれない老いと、それに気づいている当人同士のひそかな困惑をつつみ隠さず描く。
そういった目にしたくないものまで含めて、人を愛せるだろうかと疑ってしまうくらい。
フロレンティーノ・アリーサの最後の言葉が素敵だ。
こんなにカッコいいエンディングを誰が想像しただろう。
なぜなら、主人公の船会社の社長 フロレンティーノ・アリーサと、その初恋の人である有名な医者の未亡人 フェルミーナ・ダーサは、七十歳を過ぎた、死に近い老人なのだから。
物語のはじまりも変わっている。
主人公ではなく、フェルミーナ・ダーサの夫 フベナル・ウルビーノ博士の一日から始まり、彼が事故で死に、フロレンティーノ・アリーサが、夫を亡くしたフェルミーナ・ダーサに愛を誓うところまでを最初に描く。
それは、フロレンティーノ・アリーサが、未亡人 フェルミーナ・ダーサに愛を告白するまで待った、五十一年九ヵ月と四日目だった。
そして、物語は、フロレンティーノ・アリーサとフェルミーナ・ダーサの出会いの時に遡る。
お金はあるが、マフィアのように怪しいビジネスに手を染めている父親を持つ美しい少女フェルミーナ・ダーサと、船会社事業を創設した男の内縁の子として母親に育てられたフロレンティーノ・アリーサ。
二人の出会いと別れ。
そして、フェルミーナ・ダーサの結婚。
数多くの女性と関係しながらも、フロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサを想う心だけは失わずにいた。
そして、決して不幸ではない二人の別々の人生をたどりながら、無情にも年月は過ぎてゆき、物語は最初の場面へと戻ってゆく。
この物語の面白さは、何といっても、主人公がラブレターでもって、相手に愛情を伝えるシーンが多いことだろう。
恋愛への情熱を燃やすフロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサには出せない手紙の思いを持て余し、街の代書屋として、数々のカップルのラブレターを無料で代書するサービスをはじめる。
ある日、内気な感じの女の子が、受け取ったばかりの、答えを返さずにはいられないラブレターに返事を書いてもらえないかと、フロレンティーノ・アリーサに震えながら頼みにくる。
フロレンティーノ・アリーサは、その手紙が自分が前日の午後に書いたものだということに気づく。
彼は、女の子が受けた感動と年齢にふさわしい文体を使い、自分が書いた手紙に対する返事を書いてあげる。
そして、彼は、自分自身を相手に熱に浮かされた手紙をやり取りする羽目になり、やがて、そのカップルは結婚する。
夫婦は、ひとり目の子供が生まれたとき、偶然、自分たちのために手紙を書いてくれた代書屋が同じ人物であることが分かる。
彼らは、揃って、フロレンティーノ・アリーサを訪ね、名付け親になってくれないかと頼む。
彼らは、揃って、フロレンティーノ・アリーサを訪ね、名付け親になってくれないかと頼む。
(いい話ですね)
やがて、フロレンティーノ・アリーサは、数々のラブレターのテンプレートを一冊の本にまとめる。しかし、出版のお金がなかった。
やがて、彼に経済的な余力が出来たとき、悲しいことにその頃にはラブレターを書く人間はいなくなっていた。(これも皮肉が利いている)
やがて、彼に経済的な余力が出来たとき、悲しいことにその頃にはラブレターを書く人間はいなくなっていた。(これも皮肉が利いている)
フロレンティーノ・アリーサの五十ぶりの愛の告白を受け、戸惑うフェルミーナ・ダーサだが、その二人の時間の溝を埋める役割を果たしたのも、彼の書いた手紙だった。
そういった目にしたくないものまで含めて、人を愛せるだろうかと疑ってしまうくらい。
フロレンティーノ・アリーサの最後の言葉が素敵だ。
こんなにカッコいいエンディングを誰が想像しただろう。
2014年8月24日日曜日
真夏の冷え冷え
暑いから、ひんやりとした感触をイメージしてみる
かき氷とか、冷たい飲み物ではなく
お化け屋敷とか、怪談とか、もっと精神的なもの
たとえば、一九一六年の冬、ミュンヘンで開かれた「新しい文学の夕べ」で行われた若い作家たちの自作朗読会をイメージしてみる
一人の作家は、こんな物語を語りはじめる
司令官から死刑執行の立ち合いに招かれた旅行家が見る奇妙な機械
その機械は、下部が「ベッド」、中間部が「馬鍬(まぐわ)」、上が「製図屋」と呼ばれている機能で構成されている
「ベッド」に縛り付けられた囚人を、「まぐわ」に取りつけた針が、「製図屋」の指示により刺し、刻んでいく
死刑執行を行う将校。彼は、前の上司である司令官が作ったこの機械を信奉している
将校は、今の司令官に、この機械による処刑方法を廃止される恐れがあることを察知し、自分の味方になってくれるよう、旅行家に頼む
しかし、説得に失敗し、将校は、処刑予定であった囚人を機械から外し、自分の身体を使って機械による処刑を行う
グロテスクな機械の動きと身体を刺し貫く長い針
作品名は「流刑地にて」
作者は、フランツ・カフカ
会場にいた作家の印象
「…黒い髪、蒼ざめた顔、その全身が当惑を隠しきれないでいる」
朗読中に聴衆の三人が失神し、会場から運び出された
カフカが生涯に行った唯一の自作朗読会
彼の作品は、よく未来を予見しているような内容だと評されるが、この作品も例外ではない
二十年あまりのちにナチス・ドイツが行ったことを思えば
迫害されたユダヤ人にとって、それはさらにグロテスクで巨大な「流刑地」に他ならなかった
引用 「流刑地にて」の翻訳者 池内紀氏の解説より
かき氷とか、冷たい飲み物ではなく
お化け屋敷とか、怪談とか、もっと精神的なもの
たとえば、一九一六年の冬、ミュンヘンで開かれた「新しい文学の夕べ」で行われた若い作家たちの自作朗読会をイメージしてみる
一人の作家は、こんな物語を語りはじめる
司令官から死刑執行の立ち合いに招かれた旅行家が見る奇妙な機械
その機械は、下部が「ベッド」、中間部が「馬鍬(まぐわ)」、上が「製図屋」と呼ばれている機能で構成されている
「ベッド」に縛り付けられた囚人を、「まぐわ」に取りつけた針が、「製図屋」の指示により刺し、刻んでいく
死刑執行を行う将校。彼は、前の上司である司令官が作ったこの機械を信奉している
将校は、今の司令官に、この機械による処刑方法を廃止される恐れがあることを察知し、自分の味方になってくれるよう、旅行家に頼む
しかし、説得に失敗し、将校は、処刑予定であった囚人を機械から外し、自分の身体を使って機械による処刑を行う
グロテスクな機械の動きと身体を刺し貫く長い針
作品名は「流刑地にて」
作者は、フランツ・カフカ
会場にいた作家の印象
「…黒い髪、蒼ざめた顔、その全身が当惑を隠しきれないでいる」
朗読中に聴衆の三人が失神し、会場から運び出された
カフカが生涯に行った唯一の自作朗読会
彼の作品は、よく未来を予見しているような内容だと評されるが、この作品も例外ではない
二十年あまりのちにナチス・ドイツが行ったことを思えば
迫害されたユダヤ人にとって、それはさらにグロテスクで巨大な「流刑地」に他ならなかった
引用 「流刑地にて」の翻訳者 池内紀氏の解説より
2014年8月18日月曜日
百年の孤独/ガルシア・マルケス
面白いのは分かっているのだが、なかなかページが進まなかった「百年の孤独」
人物の名前と相関関係が覚えられない。
同じことを何度も読んでいるような錯覚に陥る。
まとまった時間が取れない等々。
やはり一冊の本は、三日以内に読み切るのがベスト。
今回、休みの時間と、池澤夏樹の「世界文学を読みほどく」に収められている「ブエンディア家系図」、「マコンド<百年の歴史実話・抄>」の助けもあって、ようやく読み切ることができた。
特に<あだ名>が付いている家系図の存在が大きかった。
ブエンディア家では、近親婚が多いせいで、父母、祖父母と同じような名前が付けられたり、性格も似通っているというせいで、誰の物語なのか読み進めるうちに分からなくなってしまい、混乱してしまうのだから。
(物語中、ブエンディア家を支えていた偉大な母ウルスラでさえ、曾孫の兄弟を取り違えてしまう)
しかし、この込み入った人物関係を確認しながら読み進めると、物語に集中する時間が途切れない。
最後の章、今までの一家の歴史を振り返るような預言書の言葉とともにブエンディア家が蟻地獄に吸い込まれるように消えてゆき、マコンドの町も崩れ去っていくあたりは圧巻でした。
ブエンディア家一族は、誰も個性的なのだが、強く印象に残ったのは、
・ホセ・アルカディオ・ブエンディア<最初の者>
・ウルスラ<家刀自>
・アウレリャノ<大佐>
・アマランタ<黒い繃帯>
・レベーカ<もらわれっ子>
・レメディオス<小町娘> <>は、池澤氏が付けたあだ名
上記の面々だろうか。
やはり、初代、2代目までが多い。
マコンドの町を作った偉大な初代と、個性が強い二代目、若干影が薄くなる三代目、二代目の面影を強く感じさせる中興の祖的な四代目、能力はあるがマコンドにいるせいで不幸になってゆく五代目と六代目、そして、蟻のむさぼる七代目。
近親婚、畸形児、超常現象、猥雑、貧富の波、不透明な政治体制、革命、暗殺、老い、世代交代。
百年という永遠にも感じる時間の中で、盛衰を繰り返したブエンディア家とマコンドの町。
しかし、いつかは終わる時が来るのだと思うと、その読後感は深さを増すばかりだ。
人物の名前と相関関係が覚えられない。
同じことを何度も読んでいるような錯覚に陥る。
まとまった時間が取れない等々。
やはり一冊の本は、三日以内に読み切るのがベスト。
今回、休みの時間と、池澤夏樹の「世界文学を読みほどく」に収められている「ブエンディア家系図」、「マコンド<百年の歴史実話・抄>」の助けもあって、ようやく読み切ることができた。
特に<あだ名>が付いている家系図の存在が大きかった。
ブエンディア家では、近親婚が多いせいで、父母、祖父母と同じような名前が付けられたり、性格も似通っているというせいで、誰の物語なのか読み進めるうちに分からなくなってしまい、混乱してしまうのだから。
(物語中、ブエンディア家を支えていた偉大な母ウルスラでさえ、曾孫の兄弟を取り違えてしまう)
しかし、この込み入った人物関係を確認しながら読み進めると、物語に集中する時間が途切れない。
最後の章、今までの一家の歴史を振り返るような預言書の言葉とともにブエンディア家が蟻地獄に吸い込まれるように消えてゆき、マコンドの町も崩れ去っていくあたりは圧巻でした。
ブエンディア家一族は、誰も個性的なのだが、強く印象に残ったのは、
・ホセ・アルカディオ・ブエンディア<最初の者>
・ウルスラ<家刀自>
・アウレリャノ<大佐>
・アマランタ<黒い繃帯>
・レベーカ<もらわれっ子>
・レメディオス<小町娘> <>は、池澤氏が付けたあだ名
上記の面々だろうか。
やはり、初代、2代目までが多い。
マコンドの町を作った偉大な初代と、個性が強い二代目、若干影が薄くなる三代目、二代目の面影を強く感じさせる中興の祖的な四代目、能力はあるがマコンドにいるせいで不幸になってゆく五代目と六代目、そして、蟻のむさぼる七代目。
近親婚、畸形児、超常現象、猥雑、貧富の波、不透明な政治体制、革命、暗殺、老い、世代交代。
百年という永遠にも感じる時間の中で、盛衰を繰り返したブエンディア家とマコンドの町。
2014年8月17日日曜日
花物語/物語シリーズ
原作は読んでいたのだが、大人げなく、やはり気になって見てしまった。
改めて、アニメを見ると、やはり、沼地蠟花という存在は何だったのかというのが、とても気になる。
神原駿河の中学時代のバスケットボールのライバルである彼女は、スポーツ推薦で進学した高校で、疲労骨折をしてしまい、家庭の事情もあり、学校を辞めてしまう。
これは、ネタバレになってしまうが、実は自殺で亡くなっている。
彼女が学校を辞めてから、何故、他人の不幸話と悪魔の体の部位を蒐集しはじめるのかを、神原 駿河に独白するシーンがあるのだが、彼女が学校を辞めた直後、自殺で死んでいる以上、その話は架空のもののはずだ。
しかし、悪魔の体の部位を蒐集しはじめるきっかけとなった花鳥櫻花の話なんかは、相談者の名前は嘘っぽいが、その中身は妙にリアリティがあり、切実なものに感じた。
(沼地蠟花の声優さんの声はイメージとは違ったが、いいと思う)
助けてくださいなんて、彼女は切実に言ってきた。
彼女は制服の下にジャージをはいていてね、だるんだるんのジャージだった。
ちょうど今、私が着ているような。
彼女は私の目の前で、そのジャージを脱いだ。
分かるよね。彼女の足は悪魔の足となっていた。
この足が勝手に私のお母さんを殺そうとするんです、と彼女は言った。
彼女には将来を誓い合った恋仲の大学生がいて、その男の子を身ごもったそうなんだ。
そして、その後、当然、親から大いに反対され、中絶するように言われた。
それで彼女は悪魔に頼った。
彼女は左足のミイラに祈ったのさ。
悪魔は母親を消すという形でそれを実行しようとした。
花鳥さんの足に憑りついてね。
失敗したんだ。それ自体は。
夜中にトランス状態になった花鳥さんは、同じ屋根の下で寝ていた母親を、しこたま蹴ったものの、結果、死には至らなかった。
母親を入院に追い込んだ犯人は自分であることはすぐに分かった。
そして、彼女はついに進退窮まったという訳さ。
その時、私は何を考えたと思う。
私は助けてあげたいと思ったんだよ。
だから、私は彼女を抱きしめた。
何も言わず強く強く力強く。
そして言った。「大丈夫。あなたの悩み事は私が全部引き受けた。絶対に解決してあげるから。だからもう、何も心配しなくていい。」
そんな無責任なことを彼女の耳元で囁いた。私の脳裏には、佐世保の事件を起こした女子高生の事が頭をよぎったし、もしかしたら、彼女は、父親を金属バットで殴った後、沼地蠟花のような存在を求めていたかもしれないと思った。
そして、それは神原駿河にとっても、同じだったのかもしれないということも。
彼女は、沼地蠟花という存在を必要としていた。
もし、沼地蠟花が幽霊だったとしたら、神原駿河が見たものは、彼女が心の奥底で求めていた助けが具現化したものであり、自分の罪の告白を聞いてくれて、彼女の暗い過去を洗い流し、背中を前に押してくれる理想の友人だったのかもしれない。
私は、沼地蠟花が神原駿河に話していた
「友達作ったり、恋したり、本読んだり、携帯いじったりしていればいいと思うんだ」
という科白が皮肉ではなく、実は神原駿河の本当の願いだったのではないかと思った。
** ** **
その貝木泥舟と神原駿河が初めてあった場面は、やはり、神原駿河が町を出た理由について、オープンキャンパスで出かけていたというエピソードはいれてほしいと思った。
貝木泥舟とオープンキャンパスのミスマッチが原作を読んでいるとき、心に残ったからだ。
また、二人が駆けっこした駅は、明らかにJR品川駅をモチーフにしていたが、私のイメージでは、東急田園都市線 溝の口駅あたりが、ちょうど鄙びた感じでベストのような気がする。
(近くに学校もあるしね)
2014年8月16日土曜日
レイテ戦記/大岡昇平
戦争というものが、どんなものなのかを振り返る方法として、ドキュメンタリーや映画を見るというのも一つの方法だと思うが、個人的にはいつも消化不良を感じてしまう。
一つには限られた時間内で製作者が抽出した史実のみを見せられるということ、二つ目には特にドラマ仕立てのものには、感動を誘おうとしたり、美化しようとしたりして、どこかに嘘があると感じることが多いことだ。
そういう気持ちを感じさせないもの、それは文章しかない。
大岡昇平の「レイテ戦記」は、太平洋戦争末期、日本の敗戦を決定的なものにしたフィリピン レイテ島で行われた日米両軍の激しい戦闘の事実を簡明な文章で詳細に描き出している。
膨大な資料(四百冊を超える様々な種類の日米双方の書誌)と、二十もの図版(戦地図、地図、年表、軍編成の表)に基づき、多面的な観点から正確な事実を掘り起こそうとした紛れもなく第一級の戦記なのだが、同時に第一級の文学でもあるという稀有な本だ。
この本を一人で書き上げた大岡の知力と忍耐力に敬服する一方、彼のこの本を書かずにはいられなかった強い気持ちを感じる。
言うまでもなく、大岡本人が歩兵として現地に出征していたという事実が大きく影響している。
日本のフィリピン決戦参加兵の数は約 592,000人、うち戦没者数は約 464,925人。実に約78%が戦争で命を落とした。
しかも、軍事上の作戦の不手際で、無意味に死んでいった たくさんの兵士がいた。
なぜ、自分は死ななければならなかったのか?
私の死は無意味なものだったのか?
そんな死者の無念を慰める唯一の方法は、可能な限り事実を正確に洗い出し、「七五ミリ野砲の砲声と三八銃の響きを再現」することだと、大岡は考えた。
たとえ、大きな戦争の歯車の動きから見れば、局地的な作戦計画だったとしても、それは現にその場にあって戦っている将兵にとっては生きるか死ぬかの問題だから、前線指揮官の発する攻撃命令はもとより、師団参謀の立てる作戦、大本営の作戦、敵軍の作戦と行動、大局的な戦況まで、その作戦の背景を遡ってゆく。
戦死者とその遺族に、なぜ、死ななければならなかったのか、その真実を伝えるために。
そして、よく戦ったものを評価もしている。
例えば、神風特攻に関する記述
大岡の視点はシニカルすぎるような気もするが、今の日本を見ると、これらの指摘は残念ながら当てはまりそうである。
日米安保条約にしても、集団的自衛権にしても、沖縄の基地問題にしても、政府の対応を見る限り、日本はアメリカの属国的な立場で生きていくことを宣言しているように思えるし、いわゆる無党派層といわれる多数派の国民は、特に定見もなく、時々の強者に従っていくだけのような存在のようだ。
このように、「レイテ戦記」は、決して過去の読み物ではない。最後の文章の通り、「その声を聞こうとする者には聞こえる声で、語り続けているのである」。
一つには限られた時間内で製作者が抽出した史実のみを見せられるということ、二つ目には特にドラマ仕立てのものには、感動を誘おうとしたり、美化しようとしたりして、どこかに嘘があると感じることが多いことだ。
そういう気持ちを感じさせないもの、それは文章しかない。
大岡昇平の「レイテ戦記」は、太平洋戦争末期、日本の敗戦を決定的なものにしたフィリピン レイテ島で行われた日米両軍の激しい戦闘の事実を簡明な文章で詳細に描き出している。
膨大な資料(四百冊を超える様々な種類の日米双方の書誌)と、二十もの図版(戦地図、地図、年表、軍編成の表)に基づき、多面的な観点から正確な事実を掘り起こそうとした紛れもなく第一級の戦記なのだが、同時に第一級の文学でもあるという稀有な本だ。
この本を一人で書き上げた大岡の知力と忍耐力に敬服する一方、彼のこの本を書かずにはいられなかった強い気持ちを感じる。
言うまでもなく、大岡本人が歩兵として現地に出征していたという事実が大きく影響している。
日本のフィリピン決戦参加兵の数は約 592,000人、うち戦没者数は約 464,925人。実に約78%が戦争で命を落とした。
しかも、軍事上の作戦の不手際で、無意味に死んでいった たくさんの兵士がいた。
なぜ、自分は死ななければならなかったのか?
私の死は無意味なものだったのか?
そんな死者の無念を慰める唯一の方法は、可能な限り事実を正確に洗い出し、「七五ミリ野砲の砲声と三八銃の響きを再現」することだと、大岡は考えた。
たとえ、大きな戦争の歯車の動きから見れば、局地的な作戦計画だったとしても、それは現にその場にあって戦っている将兵にとっては生きるか死ぬかの問題だから、前線指揮官の発する攻撃命令はもとより、師団参謀の立てる作戦、大本営の作戦、敵軍の作戦と行動、大局的な戦況まで、その作戦の背景を遡ってゆく。
戦死者とその遺族に、なぜ、死ななければならなかったのか、その真実を伝えるために。
そして、よく戦ったものを評価もしている。
例えば、神風特攻に関する記述
口では必勝の信念を唱えながら、この段階では、日本の勝利を信じている職業軍人は一人もいなかった。ただ一勝を博してから、和平交渉に入るという戦略の仮面をかぶった面子の意識に動かされていただけであった。しかも悠久の大義の美名の下に、若者に無益な死を強いたところに、神風特攻の最も醜悪な部分があると思われる。
しかし、これらの障害にも拘わらず、出撃数フィリピンで四〇〇以上、沖縄一九〇〇以上の中で、命中 フィリピンで一一一、沖縄で一三三、ほかにほぼ同数の至近突入があったことは、われわれの誇りでなければならない。
想像を絶する精神的苦痛と動揺を乗り越えて目標に達した人間が、われわれの中にいたのである。これは当時の指導者の愚劣と腐敗とはなんの関係もないことである。今日では全く消滅してしまった強い意志が、あの荒廃の中から生まれる余地があったことが、われわれの希望でなければならない。なお、本書の最終章であるエピローグでは、 レイテ島の戦いの結果、最も被害を受けたのは、フィリピンの人々であることにも触れている。そして、この中で、興味深いのは、日本ではひどく評判の良いマッカーサーについて、縦断爆撃を行ったことでマニラ市を徹底的に破壊したこと、戦後、フィリピンにおいて戦前よりも過酷な植民地支配を行ったことを指摘している。もちろん、その契機を作った日本の責任にも。
共産国封じ込めの基地として、フィリピンには台湾や沖縄のような有効性、重要性はない。東洋における民主主義のとりでとして、アメリカが日本占領に期待をかけていたことはその後の経過が示している。
日本は旧式ながら近代国家の軍備を持ち、極東でアメリカよりも有利に行動できた間、それは脅威であった。しかし正に屈伏させられようとしていた一九四五年では、近代的なドッグ、飛行機工場、鉄道網と、九千万のよく教育された人口を持つ有力な下級国家であった。
国民は習慣的事大主義を持ち、一人の天皇を味方につけることが出来れば、フィリピン人より容易に手なずけることが出来そうであった。下級国家、習慣的事大主義…
大岡の視点はシニカルすぎるような気もするが、今の日本を見ると、これらの指摘は残念ながら当てはまりそうである。
日米安保条約にしても、集団的自衛権にしても、沖縄の基地問題にしても、政府の対応を見る限り、日本はアメリカの属国的な立場で生きていくことを宣言しているように思えるし、いわゆる無党派層といわれる多数派の国民は、特に定見もなく、時々の強者に従っていくだけのような存在のようだ。
このように、「レイテ戦記」は、決して過去の読み物ではない。最後の文章の通り、「その声を聞こうとする者には聞こえる声で、語り続けているのである」。
2014年8月3日日曜日
佐世保女子高生殺人事件に思う
この事件の概要をニュースで知るにつけ、村上春樹の「ダンス・ダンス・ダンス」に出てくる少女ユキと、西尾維新の「猫物語(白)」の主人公 羽川 翼を思い浮かべてしまう。
この事件を起こしてしまった加害者の女子高生と、この小説の二人に相似性を感じてしまうのだ。
まず、一つ言えるのは、加害者の女子高生はネグレクト(育児放棄)の状態にあったのではないかということだ。
この事件の加害者は、高校1年生。成長期とはいえ、まだまだ、親が面倒をみて、かまってあげることが必要だったと思う。
私も一人暮らしを大学1年から始めた口だが、部屋に閉じこもってばかりいると、誰とも口を利かないし、社会との接触もなくなる。
そんな何で、人よりも強い知的好奇心と行動力が犯罪の方向に傾いてしまっても、自分を抑止してくれるものがない。
まして、この子には、実母を亡くし、直後に父親が別の女性と再婚するいう急激な家庭環境の変化があり、それが原因だと思うが不登校の事実もあった。
父親が、もし、「お前はもう大人なのだから、自分の問題は自分自身で解決すべきだ。私はお前の自主性をできるだけ尊重するつもりだ」というような事を言っていたとしたら、悲劇である。
勉強もスポーツも人並み以上にできる能力を持った子供であればあるほど、また、父親を好きであればあるほど、その期待に応えようとするのではないか。
警察の取り調べに対して、「父親の再婚について初めから賛成している。父親を尊敬している。母が亡くなって寂しかったので新しい母が来てうれしかった」などと述べているコメントにも、その期待に応えようとしている彼女の意思が感じられる。
父親をバットでなぐった彼女の行動にこそ、父親は真剣に向き合うべきだった。
(報道によると、父親はバットでなぐられた際、精神科医に娘の入院を勧められたがこれを拒否し、自分の命を守るために娘に一人暮らしをさせたというが、これが本当だとしたら、親としての監護義務を放棄したのに等しい)
村上春樹の「ダンス・ダンス・ダンス」に出てくる十三歳の少女ユキも、離婚した両親からネグレクトされていて、一人で都心の高級マンションに住んでいる。彼女には芸術的なセンスがある。
両親には、彼女を親として責任をもって育てようという意思はない。
父親は金銭的に援助はするが、娘に感覚が合わないと拒絶されることを理由に育児には参加せず、感受性が似通った母親からは「親子としてではなく友達になりたい」と求められ、少女は困惑する。
(その少女の危機を、この物語では「僕」が助けようとする)
今回の事件では、加害者の女子高生は、父親とともにスピードスケート競技に参加するなどしていて、一見、仲が良かったらしいが、もし、父親が娘に、親子ではなく友達の関係を求めていたとしたら、これも悲劇である。
「猫物語(白)」の羽川 翼も、両親の病死・離婚が重なり、血の繋がっていない義理の父母からネグレクトされている(彼女は自宅に「自分の部屋」がなく、廊下で寝ていた)。
しかし、羽川 翼は、そんな自分の境遇について、義理の父母に不平不満を言う訳でもなく、常に品行方正に明るく振る舞おうとする。勉強も学年1番の成績を維持しており、行動力もある。
だが、彼女の心に溜まったストレスは、彼女をブラック羽川(猫の怪異)に化身させ、街の人々を襲い、精気を吸い取る事件を引き起こす。
そして、それに留まらず心に溜まった嫉妬心が、苛虎という強力な虎の怪異を生み出し、彼女が嫉妬心を抱いた義理の父母、自分を助けようとしてくれた友人の家まで焼き尽くそうとする。
しかし、苛虎が友人の戦場ヶ原ひたぎの家を燃やそうとしている危機を察知したとき、羽川 翼は、自分が育児放棄の虐待を受けている事実を認め、自分の闇の心に立ち向かおうと決心する。
何故、羽川翼は、友人を傷つける前に立ち止ることが出来たのか。
一つには、月並みだが、羽川翼には、本当に彼女の身を案じてくれる人が傍にいたからということなのだと思う。
人は、誰かに大事にされている自分を実感できなければ、誰かを大事にしようという思いには至らない。
羽川翼が自宅の火事で、泊まるところもなく、廃墟で一人寝ていたところを、真夜中まで探し続けてきた友人の戦場ヶ原ひたぎは泣きながら彼女を叱りつける。「何故、自分自身を大事にしないのか」と。
そして、彼女が苛虎に負けそうになった時(彼女が凶暴な自我である虎を抑えられなくなった時)、それを退治することができる力(妖刀)を持った友人の阿良々木もいた。
羽川翼と対等、もしくはそれ以上の能力をもった人が彼女の精神的な危機を見逃さず、助けようとしたという条件も必要だったのかもしれない。
現実社会で、戦場ヶ原や阿良々木のような友人を持つことはやはり難しい。
今回の事件で、それが出来たのは、女子高生とたまにご飯を一緒に食べる機会を持っていた学校の先生と、危機を察知していた精神科医だったのかもしれない。
しかし、それだけでは足りず、彼女の悪を鎮める「妖刀」の存在も必要だったのだろう。
その「妖刀」が具体的に何だったのかは分からない。
でも、それはおそらく、彼女が傷ついている自分自身を認め、自分に向き合うきっかけをくれるものだったのに違いない。
この事件を起こしてしまった加害者の女子高生と、この小説の二人に相似性を感じてしまうのだ。
まず、一つ言えるのは、加害者の女子高生はネグレクト(育児放棄)の状態にあったのではないかということだ。
この事件の加害者は、高校1年生。成長期とはいえ、まだまだ、親が面倒をみて、かまってあげることが必要だったと思う。
私も一人暮らしを大学1年から始めた口だが、部屋に閉じこもってばかりいると、誰とも口を利かないし、社会との接触もなくなる。
そんな何で、人よりも強い知的好奇心と行動力が犯罪の方向に傾いてしまっても、自分を抑止してくれるものがない。
まして、この子には、実母を亡くし、直後に父親が別の女性と再婚するいう急激な家庭環境の変化があり、それが原因だと思うが不登校の事実もあった。
父親が、もし、「お前はもう大人なのだから、自分の問題は自分自身で解決すべきだ。私はお前の自主性をできるだけ尊重するつもりだ」というような事を言っていたとしたら、悲劇である。
勉強もスポーツも人並み以上にできる能力を持った子供であればあるほど、また、父親を好きであればあるほど、その期待に応えようとするのではないか。
警察の取り調べに対して、「父親の再婚について初めから賛成している。父親を尊敬している。母が亡くなって寂しかったので新しい母が来てうれしかった」などと述べているコメントにも、その期待に応えようとしている彼女の意思が感じられる。
父親をバットでなぐった彼女の行動にこそ、父親は真剣に向き合うべきだった。
(報道によると、父親はバットでなぐられた際、精神科医に娘の入院を勧められたがこれを拒否し、自分の命を守るために娘に一人暮らしをさせたというが、これが本当だとしたら、親としての監護義務を放棄したのに等しい)
村上春樹の「ダンス・ダンス・ダンス」に出てくる十三歳の少女ユキも、離婚した両親からネグレクトされていて、一人で都心の高級マンションに住んでいる。彼女には芸術的なセンスがある。
両親には、彼女を親として責任をもって育てようという意思はない。
父親は金銭的に援助はするが、娘に感覚が合わないと拒絶されることを理由に育児には参加せず、感受性が似通った母親からは「親子としてではなく友達になりたい」と求められ、少女は困惑する。
(その少女の危機を、この物語では「僕」が助けようとする)
今回の事件では、加害者の女子高生は、父親とともにスピードスケート競技に参加するなどしていて、一見、仲が良かったらしいが、もし、父親が娘に、親子ではなく友達の関係を求めていたとしたら、これも悲劇である。
「猫物語(白)」の羽川 翼も、両親の病死・離婚が重なり、血の繋がっていない義理の父母からネグレクトされている(彼女は自宅に「自分の部屋」がなく、廊下で寝ていた)。
しかし、羽川 翼は、そんな自分の境遇について、義理の父母に不平不満を言う訳でもなく、常に品行方正に明るく振る舞おうとする。勉強も学年1番の成績を維持しており、行動力もある。
だが、彼女の心に溜まったストレスは、彼女をブラック羽川(猫の怪異)に化身させ、街の人々を襲い、精気を吸い取る事件を引き起こす。
そして、それに留まらず心に溜まった嫉妬心が、苛虎という強力な虎の怪異を生み出し、彼女が嫉妬心を抱いた義理の父母、自分を助けようとしてくれた友人の家まで焼き尽くそうとする。
しかし、苛虎が友人の戦場ヶ原ひたぎの家を燃やそうとしている危機を察知したとき、羽川 翼は、自分が育児放棄の虐待を受けている事実を認め、自分の闇の心に立ち向かおうと決心する。
何故、羽川翼は、友人を傷つける前に立ち止ることが出来たのか。
一つには、月並みだが、羽川翼には、本当に彼女の身を案じてくれる人が傍にいたからということなのだと思う。
人は、誰かに大事にされている自分を実感できなければ、誰かを大事にしようという思いには至らない。
羽川翼が自宅の火事で、泊まるところもなく、廃墟で一人寝ていたところを、真夜中まで探し続けてきた友人の戦場ヶ原ひたぎは泣きながら彼女を叱りつける。「何故、自分自身を大事にしないのか」と。
そして、彼女が苛虎に負けそうになった時(彼女が凶暴な自我である虎を抑えられなくなった時)、それを退治することができる力(妖刀)を持った友人の阿良々木もいた。
羽川翼と対等、もしくはそれ以上の能力をもった人が彼女の精神的な危機を見逃さず、助けようとしたという条件も必要だったのかもしれない。
現実社会で、戦場ヶ原や阿良々木のような友人を持つことはやはり難しい。
今回の事件で、それが出来たのは、女子高生とたまにご飯を一緒に食べる機会を持っていた学校の先生と、危機を察知していた精神科医だったのかもしれない。
その「妖刀」が具体的に何だったのかは分からない。
でも、それはおそらく、彼女が傷ついている自分自身を認め、自分に向き合うきっかけをくれるものだったのに違いない。
2014年8月2日土曜日
ディフェンス/ウラジーミル・ナボコフ
ナボコフが書いたチェスの小説。
さぞかし、巧緻に入り組んだチェスの戦いが描かれているのだろうと思いきや、読み終わってみると、むしろ主人公がチェスから遠ざかっている(遠ざかろうとしている)展開の方が長かった。
主人公のルージンは、ロシアの作家の息子でありながら、学校では、うだつの上がらない生徒だった。それがある日、叔母にチェスを教えてもらったのをきっかけに、その才能を開花させる。
やがて、彼は、チェスのマエストロとして有名になったが、実生活では、やはり無能力かつ肥満気味のうだつの上がらない男になっていた。
そんな彼を奇跡的に好きになった女の子と恋仲になるのだが、トゥラーティとのチェスの優勝決定戦で、神経衰弱となり、その試合を放棄してしまうだけでなく、以降、チェスの活動ができなくなってしまう。
物語中、もっとも読みごたえがあるのは、音楽に例えられたこの優勝決定戦におけるチェスの駒の動きとルージンの意識の動きである。
最初のうちはまるでミュートをはめたヴァイオリンのようにそっと、そっと進行した。両者は用心しながら布陣を敷き、あれこれの駒を丁寧に進め、狙いがあるようなそぶりはまったく見せなかった。
そして、なんの前触れもなく、弦がやさしく鳴り響いた。それは対角線を制しているトゥラーティの駒だった。しかしただちにかすかな旋律がルージン側にもそっと現れた。
トゥラーティは退却し、引きこもった。そしてまたしばらくのあいだ両者は、まるで前進する気がまったくないかのように、自陣の手入れに専念した――手を入れ、組み替え、整える。
そのときまた突然に火花が散り、すばやい音の組み合わせが轟いた。二つの小隊が衝突し、どちらもすぐに一掃されたのだ。こんなふうに、戦いの序章から、徐々に激しい駒の動きが展開していくさまがイメージとして思い浮かぶ文章が素晴らしい。
訳者の若島正は、「ロリータ」の翻訳者でもあるが、チェスプロブレム(詰将棋のようなもの)の国際マスターの称号を得ているので、この本の翻訳者としては最適な人物かもしれない。
全くの個人的な感覚であるが、この小説を読んでいると、どうも、キューブリックの映画に出てくる役者や映像のイメージがチラチラと思い浮かんでしまう。
実際にキューブリックが「ロリータ」を映画化したということもあるが、彼がチェス好きとしても有名だったということも意識にあって、そう思うのかもしれない。
☆おまけ
http://chess.plala.jp/chess_beta.html
2014年7月29日火曜日
街場のアメリカ論/内田樹
いわゆるアメリカ論については、藤原新也の「アメリカ」、司馬遼太郎の「アメリカ素描」しか、読んだことがない。
司馬遼太郎の本には、今読んでもうなずけるところがあるし、藤原新也の本は、著者が著者だけに個性的な視点で観察されたアメリカ像が面白かったが、この内田樹の「街場のアメリカ論」も負けていない。
例えば、「原因は何か?」という問いを人間が立てるのは、「原因がわからない」場合だけである。
歴史の場合も同じで、ある出来事が起きる。そのあと別の出来事が起こる。それが原因と結果に見えるとしたら、それはそのままでは原因と結果の関係で結ばれているようには見えないからである。だから、歴史の教科書で、「原因」ということばが使ってあるときは注意が必要である。
「原因」ということばを人が使うのは、「原因」がよくわからないときだけだから。
なんていう話から、他人の意見をそのまま鵜呑みにするのは知性の活動を放棄することに等しいと断じ、自分の頭を使って、歴史を推論することが必要で、だから、年号を覚えることはとても有用だと述べている。
また、ある歴史的な出来事の意味を理解するためには、「なぜ、この出来事は起きたのか?」を問うだけでは足りず、「なぜ、この出来事は起きたのに、他の出来事は起きなかったのか?」という問いも同時に必要だと述べ、その例として、何故、幕末、いち早く日本に開国を迫ったアメリカが日本を支配できなかったのか? それは同時期にアメリカで南北戦争が起きていたからという例を挙げている。
ここまでは、アメリカ論に入る前の導入部分なのだが、
アメリカン・コミックのヒーローが象徴するものは何なのか?
上が変でも大丈夫なアメリカの統治システム
戦死者が実は少ないアメリカ
アメリカ没落のシナリオ
実は子供嫌いのアメリカ
キリスト教の福音主義
訴訟社会
などで繰り広げられるアメリカ論は、どれも納得感が高い。
今は日本に限らず、何処に行っても、アメリカの文化は目につく環境にあるが、知性を働かせ、一歩、深く踏み込むと、アメリカの意外な正体が浮かび上がってくる。
これだけ、自分は分かっていなかった(考えていなかった)んだということを気づかせてくれる本でした。
2014年7月28日月曜日
80年代 「きまぐれオレンジ☆ロード」と 「ストップ!! ひばりくん!」、そして「サマーブリーズ '86」
西尾維新原作の物語シリーズの「恋物語」最終話で、貝木泥舟が、千石撫子に神様を辞めさせるため、彼女がひた隠しに作っていた漫画を暴露する。
この貝木の台詞を聞いていて、私の頭に真っ先に思い浮かんだのが、 「きまぐれオレンジ☆ロード」だった。
この男子向けの、ご都合主義のとろけるような物語は、私が最後に少年ジャンプを読んでいた時期と重なるため、印象に残っている。
ただ、キャラクターの描き方も、物語としても、正直、あと一歩という感は否めなかった。
完成度の高さから言えば、主人公がオカマという、時代を先取りしていた江口寿史の 『ストップ!! ひばりくん!』が、やはり忘れがたい。
絵が全然古びていない。
「なんだ、あのとろけるようなご都合主義のラブコメは。
80年代かよ。
あんな男が現実にいるかよ。馬鹿馬鹿しい。
千石撫子が書いていた「君と撫でっこ」は、少女漫画のようだが、しかも展開的には結構エッチだったりしてな 。」
ただ、キャラクターの描き方も、物語としても、正直、あと一歩という感は否めなかった。
完成度の高さから言えば、主人公がオカマという、時代を先取りしていた江口寿史の 『ストップ!! ひばりくん!』が、やはり忘れがたい。
絵が全然古びていない。
どちらもラブコメだが、「きまぐれ」が甘いだけのファンタ味だとすると、「ひばりくん」は、すごく可愛いけども、男なんだよなーという人生の不条理を示している点で、苦みのあるジンジャエールだろうか。
私がなぜ、こんな思いにふけってしまったのかというと、最近お気に入りの一十三十一(ひとみとい)の「サマーブリーズ '86」を聴いていたからだ。
これも、甘い80年代の雰囲気が伝わってくるいい歌です。
*全くの思いつきだが、「きまぐれ」の登場人物と、西尾維新の物語シリーズのアニメ化された登場人物が、すごく似ている気がする。
「きまぐれ」の主人公 春日 恭介は超能力者で、超能力者の妹2人を持つ。
「物語」の主人公 阿良々木暦は、吸血鬼で、やはり妹が2人いて、一人は武道の達人で、もう一人は実は怪異である。
「きまぐれ」のヒロインは、鮎川まどかで、ロングストレートヘアの、頭脳明晰でスポーツ万能なミステリアスな美少女。だが、学校では不良とみなされ孤立している。
「物語」のヒロインは、複数いるが、暦の恋人となる戦場ヶ原ひたぎは、当初は、ロングストレートヘアの、ミステリアスな美少女で、こちらも頭脳明晰でスポーツができるが、怪異にとりつかれたせいで学校で孤立している。
「きまぐれ」には、杉 ひろみという恭介の友人として、めがねを掛けた女の子が登場する。「物語」では、羽川翼というめがねを掛けた暦の友人が現れる。
「きまぐれ」には、広瀬 さゆりというツインテールの美少女が現れ、「物語」でも、八九寺真宵というツインテールの女の子が現れる。*
2014年7月27日日曜日
夏の砦/辻 邦生
この小説は、十年以上前に購入したあと、長らく未読のまま手元に置き去りにしていた。
一つには、題名から受ける明るい印象と比較して、作品の内容が暗いからというとても乱暴な感想を抱いたせいだ。
この小説の主人公 支倉冬子(はせくら ふゆこ)が体験してきた暗い過去を追体験する気力というか、意欲がどうしても湧いてこなかったというのが率直な感想である。
しかし、福永武彦の作品を改めて読んでいるうちに、同年代の作家ということが気になり、ようやく、なんとか読み切ることができた。
文章は非常に質がよい。音読してみると分かるが、やや硬すぎるきらいはあるけれど、きらきらとしたクリスタルのような理知的な響きに満ちていている。
それでも、私がこの作品にのめり込むことができなかったのは、主人公 支倉冬子に魅力を感じなかったというのが一番の理由である。
この娘(こ)は、人生を楽しんでいないという印象をどうしても強く感じる。
それは彼女が訪れた北欧の街の雰囲気そのもの、あるいは彼女から見た古い実家の雰囲気そのものだったのかもしれないが、そこから感じるのは人生の終わりのようで、黄昏てしまっているのだ。
最後の方で、そういったネガティブな面を克服したかのような展開になるが、その結末が死(しかも死を甘受したかのような終わり方)というのも嫌なのかもしれない。
彼女が恋をしていないというところも原因かもしれない。
この小説の中では、冬子の他にも、主要人物として男爵家の娘が2人出てくるが、ここでも浮いた話が出てこない。仮装舞踏会を開き、若い男女がたくさん集まる機会もあったのに…何故、恋愛をしないのだろう?なぜ、召使の小人が死んだなんて辛気臭い話で終わらすのだろうと、思ってしまう。
この作品から感じた物足りなさばかり取り上げてしまった。
ただ、人は結局、自分が体験した過去からは逃れることはできないし、その過去を豊な土壌にして未来に活かしていくしかないという主題を、美しい文章で、きめ細かに一人の女性の記憶と精神を深掘りして描き切っているという点においては徹底されており、とても読み応えのある作品だと思う。
一つには、題名から受ける明るい印象と比較して、作品の内容が暗いからというとても乱暴な感想を抱いたせいだ。
この小説の主人公 支倉冬子(はせくら ふゆこ)が体験してきた暗い過去を追体験する気力というか、意欲がどうしても湧いてこなかったというのが率直な感想である。
しかし、福永武彦の作品を改めて読んでいるうちに、同年代の作家ということが気になり、ようやく、なんとか読み切ることができた。
文章は非常に質がよい。音読してみると分かるが、やや硬すぎるきらいはあるけれど、きらきらとしたクリスタルのような理知的な響きに満ちていている。
それでも、私がこの作品にのめり込むことができなかったのは、主人公 支倉冬子に魅力を感じなかったというのが一番の理由である。
この娘(こ)は、人生を楽しんでいないという印象をどうしても強く感じる。
それは彼女が訪れた北欧の街の雰囲気そのもの、あるいは彼女から見た古い実家の雰囲気そのものだったのかもしれないが、そこから感じるのは人生の終わりのようで、黄昏てしまっているのだ。
最後の方で、そういったネガティブな面を克服したかのような展開になるが、その結末が死(しかも死を甘受したかのような終わり方)というのも嫌なのかもしれない。
彼女が恋をしていないというところも原因かもしれない。
この小説の中では、冬子の他にも、主要人物として男爵家の娘が2人出てくるが、ここでも浮いた話が出てこない。仮装舞踏会を開き、若い男女がたくさん集まる機会もあったのに…何故、恋愛をしないのだろう?なぜ、召使の小人が死んだなんて辛気臭い話で終わらすのだろうと、思ってしまう。
この作品から感じた物足りなさばかり取り上げてしまった。
ただ、人は結局、自分が体験した過去からは逃れることはできないし、その過去を豊な土壌にして未来に活かしていくしかないという主題を、美しい文章で、きめ細かに一人の女性の記憶と精神を深掘りして描き切っているという点においては徹底されており、とても読み応えのある作品だと思う。
2014年7月21日月曜日
増補版 街場の中国論/内田樹
本書は、2005年に神戸女子学院大学の大学院の演習で著者が話した内容を2007年にまとめたものに、2011年に尖閣問題などを扱った章を追加した内容になっている。
内容的に古いかなと懸念したが、今読んでも十分通用する内容になっていると思う。
言っていることも分かりやすい。
例えば、中国という国を論じるときに、国の規模を考慮しないことは不適切であるという指摘。
それと、中国の近代史を取り上げる中で、毛沢東がしたことの功罪というものは、いまだに、中国という国を読み解く上での重要な要素であるのだなということがよく分かりました。
この本を読むことで、ちまたにありふれている嫌中論のマスコミ報道、書籍では得られない視座が得られると思います。
内容的に古いかなと懸念したが、今読んでも十分通用する内容になっていると思う。
言っていることも分かりやすい。
例えば、中国という国を論じるときに、国の規模を考慮しないことは不適切であるという指摘。
この国は人口十四億人である。五十五の少数民族を擁し、少数民族だけで人口一億四千万人いる。それだけで日本の人口より多いのである。それが「日本と同じように統治されていない」ことをあげつらうのはあまり意味のないことである。
…小国には「小国の制度」があり、大国には「大国の制度」がある。「小国」では「いろいろなものを勘定に入れて、さじ加減を案分する」という統治手法が可能であり、大国ではそんな面倒なことはできない。だから、大国では「シンプルで誰にでもわかる国民統合の物語」を絶えず過剰に服用する必要が出てくる。また、日本と中国の国情の最大の違いは、中国の統治形態が日本と比べると極めて不安定だという指摘。
中央政府のハードパワーが落ちれば、あらゆる国境地域で独立運動が起き、場合によっては内戦が始まるというリスクをつねに勘定に入れて中国政府のトップは外交政策を起案し実行している。
日本政府はそのようなリスクを勘定に入れる必要がない。…政権がどれほど外交上の失点を重ねようと、内閣の総辞職や国政選挙での与党の惨敗というようなことはありえても、九州や北海道が独立するとか、戒厳令が布告されるといった事態を想像する必要はない。それと、中国政府が領有権問題で強硬姿勢をとるのは、外国に領土的に屈伏してきた歴史的事実に対する国民的な屈辱の記憶が生々しいからだという指摘。
一八四〇~四二年のアヘン戦争の敗北で巨額の賠償金と香港の割譲を強いられて以来、一九四九年の中華人民共和国成立まで、百年以上にわたり中国人は外国に領土的に屈服し続けてきた。百年以上、まるで肉食獣に食い散らかされるように、国土を蚕食され、主権を脅かされてきた国民の「領土的トラウマ」がどれほどのものか、私たちは一度彼らの立場になって想像してみる必要がある。これだけでも、だいぶ中国の見方が変わるが、本書では、古代中国の統治方法 中華思想という華夷秩序によって整序された宇宙観とそれに馴染んできた日本の立ち位置、そして、その中国の座にとって代わったアメリカとの関係、そのアメリカの日中韓に対する思惑、東アジア戦略についても分かりやすく説明しており、今の各国の政治状況を思い浮かべても、うなづけるところが多い。
それと、中国の近代史を取り上げる中で、毛沢東がしたことの功罪というものは、いまだに、中国という国を読み解く上での重要な要素であるのだなということがよく分かりました。
この本を読むことで、ちまたにありふれている嫌中論のマスコミ報道、書籍では得られない視座が得られると思います。
2014年7月18日金曜日
it's a very deep sea / The Style Council
今日、熱があるのに仕事に行かなければならず、自分はいつからこんなに仕事人間になったのだろうと思う。
そうして、ぼーっと電車の車窓の窓を見ながら、自分が一番ひまを持てあましていた大学時代の朝を思い浮かべていた。
よく朝方まで夜更かしして、十時ぐらいまで寝て、それからお風呂に入っていた。
明るい窓から差し込む日の光に水面が光っているのをみながら、身体をお湯になじませる。
特にさむい冬は毎日のように朝風呂に入っていた。
私にとってはお風呂は覚醒するための装置のようなものだった。
そんな時によくお風呂で口ずさんでいたのが、スタイル・カウンシルの"it's a very deep sea"だった。
perhaps I'll come to the surface and come to my senses, perhaps I'll come to...
この歌詞を口ずさみ、少しずつゆっくりと深海から海面に上がっていく自分をイメージして。
but it's a very deep sea around my own devices.
そうして、ぼーっと電車の車窓の窓を見ながら、自分が一番ひまを持てあましていた大学時代の朝を思い浮かべていた。
よく朝方まで夜更かしして、十時ぐらいまで寝て、それからお風呂に入っていた。
明るい窓から差し込む日の光に水面が光っているのをみながら、身体をお湯になじませる。
特にさむい冬は毎日のように朝風呂に入っていた。
私にとってはお風呂は覚醒するための装置のようなものだった。
そんな時によくお風呂で口ずさんでいたのが、スタイル・カウンシルの"it's a very deep sea"だった。
perhaps I'll come to the surface and come to my senses, perhaps I'll come to...
この歌詞を口ずさみ、少しずつゆっくりと深海から海面に上がっていく自分をイメージして。
but it's a very deep sea around my own devices.
2014年7月13日日曜日
NHKスペシャル 集団的自衛権 行使容認は何をもたらすのか
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0713/index.html
番組では、①集団的自衛権 行使容認を閣議決定する前の与党協議における自民党、公明党の思惑と、②今回の決定が今後日本に何をもたらすのかを検証していた。
印象に残ったのが、
①については、自民党から、今回の集団的自衛権 行使容認に関して、反対の意見がほとんど出なかったこと(唯一、村上誠一郎議員)に関して、公明党 山口代表が、かつて、自衛隊をPKO活動に派遣することを決定したときには、自民党内でも多様な意見が出たが、今回はそのような意見が出なかったということは自民党の今後の課題であろうという趣旨の一言。
番組では、今回閣議決定した基本方針で、シーレーン上の機雷除去ができるかどうか、自民党と公明党の見解を確認している場面があったが、公明党が、それを行使するということはかなりの極限状態になる場合は考えられると、苦渋が感じられるコメントをしたのに対し、自民党の石破氏は、それはできます、ひどく明確に答えていたのも印象的だった。
今回、公明党は、自民党の暴走を止める方向で協議に応じ、その方針を抑制の方向に修正することに貢献したとも考えられるが、政治的妥協を行ったというのも事実である。
今後、この同床異夢を更に受け入れていくのか、一定のレベルを超えた場合には、明確にNoを突き付けるのかも気になるところだ。
②については、同じ敗戦国であるドイツが、湾岸戦争を機に、NATO域外派兵を行うようになったが、五十数名の兵士が戦闘で亡くなっている事実があるということ、だから、国民には派兵に当たり、どのようなリスクが起こりうるかを明確に説明すべきであるということ。
また、派兵を決定する前提として、周辺国の信頼と理解が必要条件であるということ。フランスとイギリスに対しては、ナチスドイツの復活と疑われることのない信頼関係の構築が派兵の条件であるということ。
①については、大政翼賛会ではないが、軍国化の兆しが生まれてもおかしくはない土壌になっているのではないかという懸念、②については、安倍首相がいまだに、自衛隊員が戦闘で命を落とす可能性が高まることを国民に明確に説明していないこと、そして、近隣国とは、集団的自衛権はおろか、いまだに、まともな会話ができていない関係性にあるという事実だ。
こんな状況下で、集団的自衛権行使容認を閣議決定する意義は本当にあったのだろうかと首をかしげざるを得ない。
番組では、①集団的自衛権 行使容認を閣議決定する前の与党協議における自民党、公明党の思惑と、②今回の決定が今後日本に何をもたらすのかを検証していた。
印象に残ったのが、
①については、自民党から、今回の集団的自衛権 行使容認に関して、反対の意見がほとんど出なかったこと(唯一、村上誠一郎議員)に関して、公明党 山口代表が、かつて、自衛隊をPKO活動に派遣することを決定したときには、自民党内でも多様な意見が出たが、今回はそのような意見が出なかったということは自民党の今後の課題であろうという趣旨の一言。
番組では、今回閣議決定した基本方針で、シーレーン上の機雷除去ができるかどうか、自民党と公明党の見解を確認している場面があったが、公明党が、それを行使するということはかなりの極限状態になる場合は考えられると、苦渋が感じられるコメントをしたのに対し、自民党の石破氏は、それはできます、ひどく明確に答えていたのも印象的だった。
今回、公明党は、自民党の暴走を止める方向で協議に応じ、その方針を抑制の方向に修正することに貢献したとも考えられるが、政治的妥協を行ったというのも事実である。
今後、この同床異夢を更に受け入れていくのか、一定のレベルを超えた場合には、明確にNoを突き付けるのかも気になるところだ。
②については、同じ敗戦国であるドイツが、湾岸戦争を機に、NATO域外派兵を行うようになったが、五十数名の兵士が戦闘で亡くなっている事実があるということ、だから、国民には派兵に当たり、どのようなリスクが起こりうるかを明確に説明すべきであるということ。
また、派兵を決定する前提として、周辺国の信頼と理解が必要条件であるということ。フランスとイギリスに対しては、ナチスドイツの復活と疑われることのない信頼関係の構築が派兵の条件であるということ。
①については、大政翼賛会ではないが、軍国化の兆しが生まれてもおかしくはない土壌になっているのではないかという懸念、②については、安倍首相がいまだに、自衛隊員が戦闘で命を落とす可能性が高まることを国民に明確に説明していないこと、そして、近隣国とは、集団的自衛権はおろか、いまだに、まともな会話ができていない関係性にあるという事実だ。
こんな状況下で、集団的自衛権行使容認を閣議決定する意義は本当にあったのだろうかと首をかしげざるを得ない。
2014年7月12日土曜日
妄想と想像―「知に働けば蔵が建つ」/内田 樹
内田 樹の著書「知に働けば蔵が建つ」の中に、「宿命は何か」という短い文章を読んで、なるほどと思った。著者は、こんなふうに考える。
前にも、こんな失敗したなぁとか、やっぱり、あれが起こってしまったとか、あのとき、あれをやってなかったから、やっぱりこうなったんだ、という残念なイメージである。
(不思議と、そういうことは予想が的中する)
これは、私の関心、想像力の方向性が悪い出来事に向かっているせいだろうか。
妄想と想像は違う。
妄想には具体的な細部がないが、想像には具体的な細部がある。
強い想像力を持っている人は、多くの細部を深く想像する習慣があるので、訪れる未来のうちに、必ず「想像したとおり」の断片を発見してしまう。
だから、想像力の豊かな人は、はじめて経験する出来事にも、しばしば既視感を覚える。
そして、自分の意思決定以外の力が自分が今いるこの場所に導いたのではないかと、宿命の力を感じる。
想像力の豊かな人は、どんな人生を選択したとしても、その人生の至るところに「宿命の刻印」を感じる。
だから、そのような人は、「想像したとおりのことが私の人生において実現した」というふうに考える。
強い想像力を備えた人は、構造的に幸福な人である。
この文章に、若干感動しかけたのだが、よくよく考えると私個人としては、既視感というと、あまりいい場面で感じたことがないというのが正直な印象である。
前にも、こんな失敗したなぁとか、やっぱり、あれが起こってしまったとか、あのとき、あれをやってなかったから、やっぱりこうなったんだ、という残念なイメージである。
(不思議と、そういうことは予想が的中する)
これは、私の関心、想像力の方向性が悪い出来事に向かっているせいだろうか。
その「マイナス想像力」を、こうあったらいいだろうなと思う「プラス想像力」に使ってみようと、ふと思ったのだが、具体的な細部を想像するということは、ほとんど、自分の人生の計画を具体的に作ることに他ならないのではという思いに至る。
つまり、今まで、既視感を悪いことにしか感じていなかったということは、私は、自分のプラス方向については、具体的な細部を想像しない「妄想」しかしていなかったのではないかという思い。
2014年7月10日木曜日
未来都市/福永武彦
小説家 福永武彦が書いたSF小説。
人生に絶望した男が行き着いた場所、それは「自殺酒場」だった。
BAR SUICIDE
そこで男は、怪しいバーテンダーに、死にたければ特別のカクテルを作るともちかけられ、人が止めるのも聞かず、それを飲み干してしまう。
死んだと思った男は、「自殺酒場」にいた男とともに、未来都市へ向かう汽車の中、目覚める。
たどり着いた男が、未来都市で目にしたのは、天才哲学者の管理の下、人間の悪しき記憶や意識が取り除かれた幸福な人々が住む街の風景だった…
まず、冒頭の「自殺酒場」という奇抜な発想がいい。
(ドアーズの「アラバマ・ソング」がBGMでかかっていそう)
この物語は、息子の池澤夏樹が書いたSF小説「やがてヒトに与えられた時が満ちて…」に、雰囲気がとても似ている。
特に未来都市のイメージ。
「やがて…」のほうは、コンピュータによって管理されているが、人々が欲望を抑えて穏やかに暮らしている様子などは、「未来都市」と、ほぼ同じといっていい。
池澤夏樹が意識して構成を似せたのか、気になるところだが、娘の池澤春菜さんといい、SF小説に足を踏み入れているところは、やはり遺伝的なものなのかもしれない。
人生に絶望した男が行き着いた場所、それは「自殺酒場」だった。
BAR SUICIDE
そこで男は、怪しいバーテンダーに、死にたければ特別のカクテルを作るともちかけられ、人が止めるのも聞かず、それを飲み干してしまう。
死んだと思った男は、「自殺酒場」にいた男とともに、未来都市へ向かう汽車の中、目覚める。
たどり着いた男が、未来都市で目にしたのは、天才哲学者の管理の下、人間の悪しき記憶や意識が取り除かれた幸福な人々が住む街の風景だった…
まず、冒頭の「自殺酒場」という奇抜な発想がいい。
(ドアーズの「アラバマ・ソング」がBGMでかかっていそう)
この物語は、息子の池澤夏樹が書いたSF小説「やがてヒトに与えられた時が満ちて…」に、雰囲気がとても似ている。
特に未来都市のイメージ。
「やがて…」のほうは、コンピュータによって管理されているが、人々が欲望を抑えて穏やかに暮らしている様子などは、「未来都市」と、ほぼ同じといっていい。
池澤夏樹が意識して構成を似せたのか、気になるところだが、娘の池澤春菜さんといい、SF小説に足を踏み入れているところは、やはり遺伝的なものなのかもしれない。
2014年7月6日日曜日
呪いの時代/内田樹
鷲田清一といい、哲学者が良質な文章でエッセイを書き、その哲学の知識・メソッドに基づき、現在起きている出来事の分析を読むことができる時代になったのは、とてもいいことだと思う。
わたしが高校生ぐらいの時には、岸田秀の「ものぐさ精神分析」ぐらいしかなかったような気がするが、今は、色々な著者を選択できる。
こういった小説家でも作家でもない学者の文章というのは、ずばり物事の本質を言い当てるところが、やはり読んでいて面白いところだ。
例えば、本書においても、以下のようなことが指摘されている。
(政治家にとっては、野党やメディアが叩いているのは「他人から見た私」という仮象なので、痛くも痒くもない)
についての説明の文章なのだが、 自民党の政治家の数々の失言があった時の対応や、最近話題の県議会議員の対応などを思い浮かべると、すごく納得できる。
また、本書では、上記の考え方を、秋葉原で無差別殺傷事件を起こした犯人についても当てはめているが、確かに、PCの遠隔操作ウイルス事件の犯人や、ストーカー事件の加害者(今晩やっていたNHKスペシャル)の心理も説明できるような気がするということは、日本に広く蔓延している病巣の本質を捉えているのかもしれない。
わたしが高校生ぐらいの時には、岸田秀の「ものぐさ精神分析」ぐらいしかなかったような気がするが、今は、色々な著者を選択できる。
こういった小説家でも作家でもない学者の文章というのは、ずばり物事の本質を言い当てるところが、やはり読んでいて面白いところだ。
例えば、本書においても、以下のようなことが指摘されている。
他人が見ている私とは違うところに「ほんとうの私」がいる。それこそが「真正の私」であり、世間の人間が見ているのは仮象に過ぎない、と。
だから、「世間の人間が見ている私」の言動について、「ほんとうの私」は責任を取る必要を感じない。これは、政治家が不祥事を起こした時に、何故、不祥事そのものについて詫びないのか?
(政治家にとっては、野党やメディアが叩いているのは「他人から見た私」という仮象なので、痛くも痒くもない)
についての説明の文章なのだが、 自民党の政治家の数々の失言があった時の対応や、最近話題の県議会議員の対応などを思い浮かべると、すごく納得できる。
また、本書では、上記の考え方を、秋葉原で無差別殺傷事件を起こした犯人についても当てはめているが、確かに、PCの遠隔操作ウイルス事件の犯人や、ストーカー事件の加害者(今晩やっていたNHKスペシャル)の心理も説明できるような気がするということは、日本に広く蔓延している病巣の本質を捉えているのかもしれない。
2014年7月5日土曜日
寝ながら学べる構造主義/内田樹(たつる)
表題にある「寝ながら」までは行かないが、寝そべりながらでも、現代思想史の流れを、ひととおり理解できるという非常に分かりやすい本だ。
思想史の世界では、現代は、ポスト構造主義の時代(構造主義以後期)と呼ばれている。
それは、構造主義の思考方法があまりにも深く私たちのもののの考え方や感じ方に浸透してしまった、その発想方法そのものが「自明なもの」になってしまった時代だから。
例えば、アメリカの同時多発テロの後、アメリカがアフガンの空爆を行った際、「ブッシュの反テロ戦略にも一理あるが、アフガン市民の苦しみを思いやることも必要ではないか」という意見。
このように争っている当事者のどちらか一方に「絶対的正義」があるはずだとは思わず、世界の見え方は視点が異なれば違うという客観的かつ冷静な意見。
これが構造主義の考え方ということになるらしい。
私たちは自分が考えるほど、自由に、主体的にものを見ている訳ではない。むしろ、殆どの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に「見せられ」「感じさせられ」「考えさせられ」ているという意識。
本書では、この構造主義の成り立ちについて、その前史として、マルクス、フロイト、ニーチェの思想にその源流をさぐり、構造主義の始祖ソシュールの言語学に触れ、構造主義の四銃士といわれる、社会史のミシェル・フーコー、記号論のロラン・バルト、文化人類学のクロード・レヴィ・ストロース、精神分析のジャック・ラカンの思想を実に分かりやすく説明している。
(フーコーの章の「国家は身体を操作する」なんて目から鱗でした)
レヴィ・ストロースは「みんな仲良くしようね」、バルトは「ことばづかいで人は決まる」、ラカンは「大人になれよ」、フーコーは「私はバカが嫌いだ」という、身もふたもないまとめ方。
難解な構造主義者の主張を理解したことについて、著者が、「べつに哲学史の知識がふえたためでも、フランス語読解力がついたためでもありません。馬齢を重ねるうちに、人と仲良くすることのたいせつさも、ことばのむずかしさも、大人になることの必要性も、バカはほんとうに困るよね、ということも痛切に思い知らされ、おのずと先賢の教えがしみじみ身にしみるようになったというだけ」と述懐しているのも面白い。
思想史の世界では、現代は、ポスト構造主義の時代(構造主義以後期)と呼ばれている。
それは、構造主義の思考方法があまりにも深く私たちのもののの考え方や感じ方に浸透してしまった、その発想方法そのものが「自明なもの」になってしまった時代だから。
例えば、アメリカの同時多発テロの後、アメリカがアフガンの空爆を行った際、「ブッシュの反テロ戦略にも一理あるが、アフガン市民の苦しみを思いやることも必要ではないか」という意見。
このように争っている当事者のどちらか一方に「絶対的正義」があるはずだとは思わず、世界の見え方は視点が異なれば違うという客観的かつ冷静な意見。
これが構造主義の考え方ということになるらしい。
私たちは自分が考えるほど、自由に、主体的にものを見ている訳ではない。むしろ、殆どの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に「見せられ」「感じさせられ」「考えさせられ」ているという意識。
本書では、この構造主義の成り立ちについて、その前史として、マルクス、フロイト、ニーチェの思想にその源流をさぐり、構造主義の始祖ソシュールの言語学に触れ、構造主義の四銃士といわれる、社会史のミシェル・フーコー、記号論のロラン・バルト、文化人類学のクロード・レヴィ・ストロース、精神分析のジャック・ラカンの思想を実に分かりやすく説明している。
(フーコーの章の「国家は身体を操作する」なんて目から鱗でした)
レヴィ・ストロースは「みんな仲良くしようね」、バルトは「ことばづかいで人は決まる」、ラカンは「大人になれよ」、フーコーは「私はバカが嫌いだ」という、身もふたもないまとめ方。
難解な構造主義者の主張を理解したことについて、著者が、「べつに哲学史の知識がふえたためでも、フランス語読解力がついたためでもありません。馬齢を重ねるうちに、人と仲良くすることのたいせつさも、ことばのむずかしさも、大人になることの必要性も、バカはほんとうに困るよね、ということも痛切に思い知らされ、おのずと先賢の教えがしみじみ身にしみるようになったというだけ」と述懐しているのも面白い。
2014年6月29日日曜日
暦物語/西尾維新
「暦物語」は、今までのメインストーリー、すなわち、阿良々木暦が吸血鬼と出会った4月から彼の大学受験日の3月までの間に起きた事件、「化物語」「傷物語」「偽物語」「猫物語」「傾物語」「囮物語」「鬼物語」「恋物語」「憑物語」という大きな物語の流れの間に、実はこんなエピソードがありました、という小さな作品を時系列に並べている構成になっていて、そういう意味では、この作品を読む前には、大体は、これらの前作を読んでおいたほうが納得がいくと思う。
こういった作品は、余談めいたスピンオフとか、番外編とか言って、本編より見劣りするものが多いが、この「暦物語」は、とても面白かった。
まず、推理小説仕立てになっているところが面白い。
一つ一つの作品の中で、学校怪談、都市伝説のような、怪異とは呼べるかどうか微妙な小さい不思議な事件が発生し、それを、阿良々木暦がワトソン役となり、忍野メメ、羽川翼、戦場ヶ原ひたぎ、果ては貝木泥舟までがホームズ役になって、謎解きをする。
例えば、学校の花壇にいつの間にかできた石像と祠、校舎の屋上に月一で供えられる花束、鬼の形相の模様が浮き出る公園の砂場、お風呂の水面に浮かぶ女性の顔、突如その存在が明らかになった老木、八人目の茶道部員など、ちょっとした不思議な話が出てくる。
これらを、現実的に、合理的に謎解きするという推理小説的な手法だけではなく、真正面からの解決を回避し、ある意味、大人の成熟した方法で騙すという手法が提示されているところが面白い。
老木、茶道部員での解決方法、貝木泥舟の風説流布の手法、パンデミック論、斧乃木余接の謎の探し物などは、おかしな話だが、読んでいて妙になるほどと感心してしまった。
こういった作品は、余談めいたスピンオフとか、番外編とか言って、本編より見劣りするものが多いが、この「暦物語」は、とても面白かった。
まず、推理小説仕立てになっているところが面白い。
一つ一つの作品の中で、学校怪談、都市伝説のような、怪異とは呼べるかどうか微妙な小さい不思議な事件が発生し、それを、阿良々木暦がワトソン役となり、忍野メメ、羽川翼、戦場ヶ原ひたぎ、果ては貝木泥舟までがホームズ役になって、謎解きをする。
例えば、学校の花壇にいつの間にかできた石像と祠、校舎の屋上に月一で供えられる花束、鬼の形相の模様が浮き出る公園の砂場、お風呂の水面に浮かぶ女性の顔、突如その存在が明らかになった老木、八人目の茶道部員など、ちょっとした不思議な話が出てくる。
これらを、現実的に、合理的に謎解きするという推理小説的な手法だけではなく、真正面からの解決を回避し、ある意味、大人の成熟した方法で騙すという手法が提示されているところが面白い。
老木、茶道部員での解決方法、貝木泥舟の風説流布の手法、パンデミック論、斧乃木余接の謎の探し物などは、おかしな話だが、読んでいて妙になるほどと感心してしまった。
2014年6月28日土曜日
福永武彦新生日記/序 池澤夏樹
作家 福永武彦が結核を患い、東京清瀬の療養所で過ごしていた時期の日記。
1949年1月1日から7月15日までの日記は、自殺を仄めかす暗い出だしで始まる。心が離れてしまった妻との関係、不安定な体調、その暗い境遇から逃れるかのように、福永の旺盛な知的活動が日々記録されている。
ラジオでクラシックを聴いたり、ギリシャ語を勉強したり、ヘミングウェイを読んだり。
特に、ヘミングウェイの「日はまた昇る」には感心したらしく、ノートには気に入った文章もメモされている。
It is awfully easy to be hard-boiled about everything in the daytime, but at night it is another thing.
(昼間はすべてにハードボイルドになるのはたやすいが、夜となると話は別だ)
お金はないが、自分で本を買ったり、誰かに頼んだり、借りたりして、暇なし読書をし、体調の良い日はコツコツと小説を書くのを続けていたようだ。
1951年12月10日から1953年3月3日までの日記では、病気の回復期にある福永武彦が、少しずつ、外の社会の接触を回復していくプロセスが描かれている。そして、妻 澄子とは別れ、福永の日記には、谷静子という女性と岩松貞子という女性に対する思いが描かれる。前者は福永の芸術的な感覚を理解できる女性で、後者は福永の面倒を甲斐甲斐しくみてくれる女性(結局、福永は貞子と再婚)。
ナツキ(池澤夏樹)に関する記述も所々見られる。北海道地震にギクッとしたり(実は夏樹は母に連れられ東京に来ていたが知らなかった)、小学就学児童のメンタルテストで品川区の中で一位になったことについて、「やさしい性質らしい」と述べていたり、澄子が池澤喬氏と同居したことで、ナツキに会えなくなることについて気落ちしている。
本の冒頭には、母 山下澄子(原條あき子)にやさしく見つめられる五歳の初々しい池澤夏樹の写真も写っており、失われた三人の家族の関係、その喪失感が伝わってくる。
本の冒頭には、母 山下澄子(原條あき子)にやさしく見つめられる五歳の初々しい池澤夏樹の写真も写っており、失われた三人の家族の関係、その喪失感が伝わってくる。
そういった喪失感を乗り越えて、福永が小説家として本格的に活動していく過程を綴った日記を、池澤夏樹は、福永が好きで読んでいたダンテの「新生」への連想から、「新生日記」と名づけている。
この苦難を乗り越えた小説家としての父を、同業者として客観的に評価しているところが、この本の明るさを醸し出している。
この苦難を乗り越えた小説家としての父を、同業者として客観的に評価しているところが、この本の明るさを醸し出している。
2014年6月22日日曜日
福永武彦戦後日記/序 池澤夏樹
池澤春菜さんの「乙女の読書道」で、この本が紹介されていたので、読んでみた。
小説家 福永武彦氏の1945年から1947年にかけての日記である。
血縁的にみれば、福永武彦氏の長男が、池澤夏樹氏で、その娘が池澤春菜さんということになる。
そういうゴシップ的な要素を無視しても、この日記はかなり読み応えのある内容になっている。
終戦後の混乱期に、文学で身を立てようとしている二十七歳の青年がいる。しかし、彼には北海道の帯広に残した妻(詩人の原條あき子)と生まれたばかりの子供(夏樹氏)もいる。
戦後の物資が少ないことに加え、まだ、小説家としての実績のない福永の執筆生活は困窮する。
居候した親戚の家からも追い出されそうになる。
しかし、就職、食料の確保、金策に奔走しなければならないような生活でも、彼は仕事の計画を立て、東京で成功して、妻と息子を呼び一緒に生活することを夢みる。
やがて、妻が実家で暮らしずらくなってしまい、彼は無職のまま、帯広に帰るが、見つけた借家は火事になり、かろうじて親子三人で暮らせる三畳一間の部屋を借り、中学の英語教師の職を得る。
しかし、その生活も長くは続かず、福永は結核に侵され、療養生活に入る。
残された妻は先行きの見えない生活に精神を病み、夫を責め、自殺を仄めかすようになる。
(歴史にIfはないが、こんなにも生活が困難な時代でなければ、福永一家3人の運命はだいぶ違うものになっていたかもしれない。そして、池澤夏樹氏の文壇への登場の仕方も変わっていたのではないだろうか。)
貧しいながらも明日を夢みていた1945年は口語体で、徐々に生活に絶望の度合いが増しはじめてからは、文語体で、これらの出来事が事細かに連綿と日記として記されている。
戦後の交通事情(汽車で帯広から信濃追分まで3日!)、闇市、進駐軍、配給、停電、食生活、物価、友人からの借金、永井荷風がまだ現役で作品を発表していたこと、当時のインテリ達が考える天皇制の廃止等、戦後の混乱期の東京の様子が記録されているところも、資料的な価値が高い。
福永は、日記を書くことの意義をこう考えていたようだ。彼がいかに優れた小説家になろうと日々努力していたかが垣間見える。
小説家 福永武彦氏の1945年から1947年にかけての日記である。
血縁的にみれば、福永武彦氏の長男が、池澤夏樹氏で、その娘が池澤春菜さんということになる。
そういうゴシップ的な要素を無視しても、この日記はかなり読み応えのある内容になっている。
終戦後の混乱期に、文学で身を立てようとしている二十七歳の青年がいる。しかし、彼には北海道の帯広に残した妻(詩人の原條あき子)と生まれたばかりの子供(夏樹氏)もいる。
戦後の物資が少ないことに加え、まだ、小説家としての実績のない福永の執筆生活は困窮する。
居候した親戚の家からも追い出されそうになる。
しかし、就職、食料の確保、金策に奔走しなければならないような生活でも、彼は仕事の計画を立て、東京で成功して、妻と息子を呼び一緒に生活することを夢みる。
やがて、妻が実家で暮らしずらくなってしまい、彼は無職のまま、帯広に帰るが、見つけた借家は火事になり、かろうじて親子三人で暮らせる三畳一間の部屋を借り、中学の英語教師の職を得る。
しかし、その生活も長くは続かず、福永は結核に侵され、療養生活に入る。
残された妻は先行きの見えない生活に精神を病み、夫を責め、自殺を仄めかすようになる。
(歴史にIfはないが、こんなにも生活が困難な時代でなければ、福永一家3人の運命はだいぶ違うものになっていたかもしれない。そして、池澤夏樹氏の文壇への登場の仕方も変わっていたのではないだろうか。)
貧しいながらも明日を夢みていた1945年は口語体で、徐々に生活に絶望の度合いが増しはじめてからは、文語体で、これらの出来事が事細かに連綿と日記として記されている。
戦後の交通事情(汽車で帯広から信濃追分まで3日!)、闇市、進駐軍、配給、停電、食生活、物価、友人からの借金、永井荷風がまだ現役で作品を発表していたこと、当時のインテリ達が考える天皇制の廃止等、戦後の混乱期の東京の様子が記録されているところも、資料的な価値が高い。
福永は、日記を書くことの意義をこう考えていたようだ。彼がいかに優れた小説家になろうと日々努力していたかが垣間見える。
作家にとって一日一日は貴重であり失われたものは帰らないが、日記は書くことのメチエを自分にためす点に効用があるのではない。
現実が一度しか生起せず、それを常に意識し、その一度を彼の眼から独自に眺めるために、小説家に日記は欠くべからざるものであるだろう。
日々の記録として価値があるのではない。小説家の現実と彼が如何に闘いまた如何に自己を豊にしたかにその効用があるのだ。
その日常が平凡でありその描写が簡潔であっても、その日記が詰まらなければ作家である小説家が詰まらないのだ。
2014年6月14日土曜日
乙女の読書道/池澤春菜
池澤春菜さんの書評集「乙女の読書道」
結論から言うと、この人は自分のことを語れる文章の形を持っている。
正直なところ、彼女の取り上げた本のほとんど(SFファンタジーや児童書)は、自分の興味と重ならなかったが、彼女の活字中毒の話、タイに留学した際に、サン・テグジュベリの「人間の土地」をすり切れるまで読んだ話、古本屋で買う本の話なんかは、非常に共感できる部分があった。
ただ、私も人のことは言えないが、ちょっと取り上げている本のカテゴリーが偏りすぎているかも。
おっこれは、と思うタイトルがあると、父の夏樹さんの推薦だったり(笑)。
(正直に言っちゃうところは好感は持てる)
巻末には、夏樹さんとの対談の内容も収められているが、次のステップとして、書評の文章の量を倍にする訓練をしなさいとか、職業作家の娘へのアドバイスも面白い。
祖父、祖母、父の文学者としての血統ゆえ、色々とプレッシャーはあるのだろうが、頑張ってほしい。
結論から言うと、この人は自分のことを語れる文章の形を持っている。
正直なところ、彼女の取り上げた本のほとんど(SFファンタジーや児童書)は、自分の興味と重ならなかったが、彼女の活字中毒の話、タイに留学した際に、サン・テグジュベリの「人間の土地」をすり切れるまで読んだ話、古本屋で買う本の話なんかは、非常に共感できる部分があった。
ただ、私も人のことは言えないが、ちょっと取り上げている本のカテゴリーが偏りすぎているかも。
おっこれは、と思うタイトルがあると、父の夏樹さんの推薦だったり(笑)。
(正直に言っちゃうところは好感は持てる)
巻末には、夏樹さんとの対談の内容も収められているが、次のステップとして、書評の文章の量を倍にする訓練をしなさいとか、職業作家の娘へのアドバイスも面白い。
祖父、祖母、父の文学者としての血統ゆえ、色々とプレッシャーはあるのだろうが、頑張ってほしい。
2014年6月9日月曜日
NHKスペシャル ミラクルボディー サッカー・FIFAワールドカップ 第2回 スペイン代表 世界最強の"天才脳"
番組では、前回のワールドカップで優勝したスペイン代表のサッカーの強さの秘密に迫ったもので、興味深かった。
小柄な選手が、チキタカと呼ばれる速いパス回しで、相手選手を攪乱し、スペースを作り、得点を挙げる。長いロングボールで一気にゴールを狙うカウンターサッカー(先日のザンビア戦での青山からのパスと大久保のゴールが好例)とは対極に位置するものだ。
このスペイン代表のサッカーを牽引してきたのが、FCバルセロナ所属の身長170cmの二人の選手。
的確なパスでゲーム全体を操る司令塔のシャビ(Xavi)と、ゴール前でチャンスを作る創造的なプレーが得意な魔術師イニエスタ(Iniesta)。
ちなみに、このFCバルセロナでは、カンテラ(石切り場)と言われるジュニアユースの練習場で、チキタカを通し、ディフェンダーをかわすためには、次にどこにパスを回せばよいかを瞬時に判断する訓練が日々行われている。
番組では、二人の脳を調べていたが、シャビは、空間認識力に長けており、加えて、試合中は、過去のゲームの局面をデータベースのように蓄えている脳の部分が非常に活発に動くという。
そのデータに基づき的確なパスを瞬時に出す直観力。このような頭の使い方は、プロ棋士に似ているという。
一方、イニエスタは、限られた局面で複数のパターンを瞬間的に創造できる力が異常に高かった。
この二人の能力が相乗効果となって、スペインの強いサッカーを実現しているということだ。
翻って、日本のサッカーを見てみると、パスサッカーを目指しているように思うが、能力は及ばずともシャビに当たる選手は思い浮かぶが、ゴール前で予想外の動きをするイニエスタのような選手がいないのが実態なのでしょうね。
小柄な選手が、チキタカと呼ばれる速いパス回しで、相手選手を攪乱し、スペースを作り、得点を挙げる。長いロングボールで一気にゴールを狙うカウンターサッカー(先日のザンビア戦での青山からのパスと大久保のゴールが好例)とは対極に位置するものだ。
このスペイン代表のサッカーを牽引してきたのが、FCバルセロナ所属の身長170cmの二人の選手。
的確なパスでゲーム全体を操る司令塔のシャビ(Xavi)と、ゴール前でチャンスを作る創造的なプレーが得意な魔術師イニエスタ(Iniesta)。
ちなみに、このFCバルセロナでは、カンテラ(石切り場)と言われるジュニアユースの練習場で、チキタカを通し、ディフェンダーをかわすためには、次にどこにパスを回せばよいかを瞬時に判断する訓練が日々行われている。
番組では、二人の脳を調べていたが、シャビは、空間認識力に長けており、加えて、試合中は、過去のゲームの局面をデータベースのように蓄えている脳の部分が非常に活発に動くという。
そのデータに基づき的確なパスを瞬時に出す直観力。このような頭の使い方は、プロ棋士に似ているという。
一方、イニエスタは、限られた局面で複数のパターンを瞬間的に創造できる力が異常に高かった。
この二人の能力が相乗効果となって、スペインの強いサッカーを実現しているということだ。
翻って、日本のサッカーを見てみると、パスサッカーを目指しているように思うが、能力は及ばずともシャビに当たる選手は思い浮かぶが、ゴール前で予想外の動きをするイニエスタのような選手がいないのが実態なのでしょうね。
2014年6月8日日曜日
新々百人一首/丸谷才一
買った当初は読んでピンとこなかった本も、本棚の片隅にあって、数年後パラパラとページをめくると、こんなに面白かったのかと思うことがある。
丸谷才一の「新々百人一首」(1999年発行)も、買った当初は、読んでみても、どうにも王朝和歌という文学形式に興味が湧かなかったが、十五年経った今、こうして読んでみると、その面白さがひたひたと感じられるようになった。
小倉百人一首にならって、百首選ばれているが、新古今集の部立てに従って、
春・夏・秋・冬・賀・哀傷・旅・離別・恋・雑・釈経・神祇の配列になっている。
まだ、夏の部までしか読んでいないが、紀貫之が屏風歌(調度的装飾歌)の代表的作者であったとか、鳥の泪(なみだ)が、日本の和歌独特のイメージであるとか、夜が明ける前から鳴く春鳥とは、閨中における婦女愉悦の声を意味すること等は、知りませんでした。
それと、一首ごとに丸谷の解説が付いているのだが、これが、文明批評や歴史学のように読ませる内容になっている。
例えば、
絵はものいわぬ詩であり、詩はものいう絵であるという見解にもとづいて、詩人たちと画家たちは何世紀も仕事をして来た。画家は文学の主題をてがかりにして構図を定め、詩人は視覚芸術ならではのイメージを読者につきつけようとして苦心した。詩と絵画は姉妹芸術であった。とマリオ・プラーツが「記憶の女神ムネモシュネ」で指摘するのを見ると、われわれは妙に当惑する。…東洋の詩と絵画については、あまりにも当たり前の話だからである。…たとえば出入りの八百屋が中元にくれた団扇には、あやしげな蔬菜図のかたわらに不出来な発句が書きそえてあるのだ。われわれはイタリアの英文学者があっけにとられるような美的状況のなかで暮らしている。
といった文章や、
平 忠度(たいら ただのり)の歌が、「千載集」撰入の際に、何故、作者名を伏せられ、読み人しらずとされたのか、他の勅撰集での用例、他の研究者の見立て、千載集の成立時期、政治的背景等を踏まえ推測していくくだりは、まるで推理小説を読んでいるような気分になる。
2014年6月7日土曜日
日本文学全集/池澤夏樹個人編集 その2
池澤夏樹個人編集の日本文学全集は、全30巻を予定しているが、そのうち、12巻までが、明治時代の前、つまり、前近代ともいえる江戸時代から奈良時代まで遡って、作品を取り上げている。
しかも、その古典作品を、ただ載せても普通の人は読めないから、すべて翻訳する。
国文学者ではなく(ただし折口信夫を除く)、現代のわりとポピュラーな小説家たちによって(中には外国語学者や哲学者という異色な顔ぶれもあるが)。
この辺の事情を、編集者の池澤夏樹は、こう述べている。
大抵の日本文学全集では、ほとんど全てが明治以降の作品となっている。
それは、私たちが読む現代日本文学の主たる祖先は、明治維新以降にはじまる文学であり、更に、そのルーツは西洋文学であり、明治維新前の古典文学とは隔絶しているという文学史観に基づくものなのかもしれない。いわゆる私小説に代表される日本自然主義文学の意識といってもいい。
しかし、一方で、自分たちのルーツを日本の古典まで遡って探し求め、過去に裏づけられた、より多層的な表現を手に入れようとした小説家たちもいた。代表的な作家でいうと、森鴎外や永井荷風、谷崎潤一郎、石川淳、丸谷才一などで、いわゆる古典主義文学の流れだ。
今回の文学全集を編集する池澤夏樹の意識は、明らかに後者の方だろう。
つまり、現在の私たちのことば、考え方、生活のルーツは、712年の古事記に始まり現代にいたるまでの約1,300年近い歴史の堆積の中にあるのだという意識だ。
この全集が、現代の読者に、古典を苦労なく読ませることにより、当時の作者や読者(日本人)の気持ちや生活を知り、共感を覚え、日本人とは何者か、自分とは何者かを考える機会を与えることを考えると、その意義は意外と重いものなのかもしれない。
そして、もう一つ期待することは、これら古典文学を現代日本語に移し替える作業に携わった比較的若い現代の小説家たちの作品に、どのような影響を与えていくかということだ。
言わば、現代日本文学という若干ぱさぱさした栄養のない畑に、肥沃な腐葉土を混ぜ合わせるような作業なのかもしれない。
編集者の池澤夏樹にその目論見があったことは間違いない。
しかも、その古典作品を、ただ載せても普通の人は読めないから、すべて翻訳する。
国文学者ではなく(ただし折口信夫を除く)、現代のわりとポピュラーな小説家たちによって(中には外国語学者や哲学者という異色な顔ぶれもあるが)。
この辺の事情を、編集者の池澤夏樹は、こう述べている。
今の日本はまちがいなく変革期である。島国であることは国民国家形成に有利に働いたが、世界ぜんたいで国民国家というシステムは衰退している。その時期に日本人とは何者であるかを問うのは意義のあることだろう。
その手がかりが文学。なぜならばわれわれは哲学よりも科学よりも神学よりも、文学に長けた民であったから。しかしこれはお勉強ではない。
権威ある文学の殿堂に参拝するのではなく、友人として恋人として隣人としての過去の人たちに会いに行く。
書かれた時の同時代の読者と同じ位置で読むために古典は現代の文章に訳す。当代の詩人・作家の手によってわれわれの普段の言葉づかいに移したものを用意する。このような作品構成で編まれる文学全集は、おそらく、初めてのことではないかと思う。
大抵の日本文学全集では、ほとんど全てが明治以降の作品となっている。
それは、私たちが読む現代日本文学の主たる祖先は、明治維新以降にはじまる文学であり、更に、そのルーツは西洋文学であり、明治維新前の古典文学とは隔絶しているという文学史観に基づくものなのかもしれない。いわゆる私小説に代表される日本自然主義文学の意識といってもいい。
しかし、一方で、自分たちのルーツを日本の古典まで遡って探し求め、過去に裏づけられた、より多層的な表現を手に入れようとした小説家たちもいた。代表的な作家でいうと、森鴎外や永井荷風、谷崎潤一郎、石川淳、丸谷才一などで、いわゆる古典主義文学の流れだ。
今回の文学全集を編集する池澤夏樹の意識は、明らかに後者の方だろう。
つまり、現在の私たちのことば、考え方、生活のルーツは、712年の古事記に始まり現代にいたるまでの約1,300年近い歴史の堆積の中にあるのだという意識だ。
この全集が、現代の読者に、古典を苦労なく読ませることにより、当時の作者や読者(日本人)の気持ちや生活を知り、共感を覚え、日本人とは何者か、自分とは何者かを考える機会を与えることを考えると、その意義は意外と重いものなのかもしれない。
そして、もう一つ期待することは、これら古典文学を現代日本語に移し替える作業に携わった比較的若い現代の小説家たちの作品に、どのような影響を与えていくかということだ。
言わば、現代日本文学という若干ぱさぱさした栄養のない畑に、肥沃な腐葉土を混ぜ合わせるような作業なのかもしれない。
編集者の池澤夏樹にその目論見があったことは間違いない。
2014年6月4日水曜日
日本文学全集/池澤夏樹個人編集 が出るらしいよ
池澤夏樹が、なんと、日本文学全集を編集することになったらしい。
http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/
収録作品を見ただけで、もうワクワクする。
いきなり、古事記で、しかも池澤夏樹が新訳?
それにとどまらず、伊勢物語、源氏物語を川上弘美、角田光代が新訳。
土佐日記、方丈記、徒然草を、堀江敏幸、高橋源一郎、内田樹が新訳。
しかも、さらにとどまらず、平家物語を古川日出男が新訳。
曾根崎心中をいとうせいこうが。
好色一代男を島田雅彦が。
たけくらべを川上未映子が。
思いっきり、異色な顔ぶれで、新訳のオンパレード(表現古?)
目次だけで判断するのは浅はかかも知れないが、これは、明らかに古典の復権を目論んだ企画である。
そういった古典の新訳は、谷崎が源氏物語を新訳したように、珍しいことではないけれど、あくまで作家個人として行われてきたことだと思う。
文学全集で、こんな試みをするなんて。
11月が第一回配本らしいが待ちきれない。
http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/
収録作品を見ただけで、もうワクワクする。
いきなり、古事記で、しかも池澤夏樹が新訳?
それにとどまらず、伊勢物語、源氏物語を川上弘美、角田光代が新訳。
土佐日記、方丈記、徒然草を、堀江敏幸、高橋源一郎、内田樹が新訳。
しかも、さらにとどまらず、平家物語を古川日出男が新訳。
曾根崎心中をいとうせいこうが。
好色一代男を島田雅彦が。
たけくらべを川上未映子が。
思いっきり、異色な顔ぶれで、新訳のオンパレード(表現古?)
目次だけで判断するのは浅はかかも知れないが、これは、明らかに古典の復権を目論んだ企画である。
そういった古典の新訳は、谷崎が源氏物語を新訳したように、珍しいことではないけれど、あくまで作家個人として行われてきたことだと思う。
文学全集で、こんな試みをするなんて。
11月が第一回配本らしいが待ちきれない。
2014年6月2日月曜日
失われた時の海/ガルシア・マルケス
ガルシア・マルケスの短編の中でも、一際、幻想的な小説だ。
ある日、夜の海からバラの芳香が漂ってくる。
海では人が死ぬと、遺体を海に流すが、ときどき花束を海に浮かべていた。
バラの匂いを嗅いで、老人の妻は土の下に埋めてもらいたいため、生きたまま埋葬してほしいと夫に頼む。
しかし、老人の妻は亡くなり、花も供えられず、海に流される。
やがて、海からふたたびバラの香りが漂い、村にはたくさんの人がやって来た。
その中に、大金持ちのハーバード氏がいた。
彼は、お金を無心する人々に約束をさせ、それが実現できれば、希望するお金をあげ、そのうち、音楽や花火、軽業師を呼び寄せ、お祭りを主催した。
祭りは一週間続き、終わったとき、ハーバート氏は長い眠りに就く。
やがて、長い眠りからさめたハーバート氏は海の底に食べ物を探しに行く。
この海の底の風景が美しい。
ぼんやりと光る水没した村の前では、音楽堂の周りをメリーゴーランドに乗った男女が回っており、テラスには色鮮やかな花が咲き乱れている。
死者たちの海が始まると、大勢の死体が幾重にも層をなしていている。
最近亡くなった人たちの水域には、五十歳も若返った美しい老人の妻があった。
そして、海の底には、何千という海亀が石のように海底に貼り付いており、そのうちの一匹をひっくり返すと、眠った海亀はふわふわと上に昇っていく。
海から上がり、海亀をたらふく食べたハーバート氏は、こんなことを話す。
「われわれは現実をしっかり見据えなければならない。現実とはつまり、あの香りは二度と戻ってこないということなのだ」と。
涼しい夜風に吹かれ、遠くから聞こえる街の喧騒を潮騒のように感じ、物語を反芻すると、心が深く深く沈んでいくのが分かる。
ある日、夜の海からバラの芳香が漂ってくる。
海では人が死ぬと、遺体を海に流すが、ときどき花束を海に浮かべていた。
バラの匂いを嗅いで、老人の妻は土の下に埋めてもらいたいため、生きたまま埋葬してほしいと夫に頼む。
しかし、老人の妻は亡くなり、花も供えられず、海に流される。
やがて、海からふたたびバラの香りが漂い、村にはたくさんの人がやって来た。
その中に、大金持ちのハーバード氏がいた。
彼は、お金を無心する人々に約束をさせ、それが実現できれば、希望するお金をあげ、そのうち、音楽や花火、軽業師を呼び寄せ、お祭りを主催した。
祭りは一週間続き、終わったとき、ハーバート氏は長い眠りに就く。
やがて、長い眠りからさめたハーバート氏は海の底に食べ物を探しに行く。
この海の底の風景が美しい。
ぼんやりと光る水没した村の前では、音楽堂の周りをメリーゴーランドに乗った男女が回っており、テラスには色鮮やかな花が咲き乱れている。
死者たちの海が始まると、大勢の死体が幾重にも層をなしていている。
最近亡くなった人たちの水域には、五十歳も若返った美しい老人の妻があった。
そして、海の底には、何千という海亀が石のように海底に貼り付いており、そのうちの一匹をひっくり返すと、眠った海亀はふわふわと上に昇っていく。
海から上がり、海亀をたらふく食べたハーバート氏は、こんなことを話す。
「われわれは現実をしっかり見据えなければならない。現実とはつまり、あの香りは二度と戻ってこないということなのだ」と。
涼しい夜風に吹かれ、遠くから聞こえる街の喧騒を潮騒のように感じ、物語を反芻すると、心が深く深く沈んでいくのが分かる。
2014年5月26日月曜日
大飯原発運転差止請求事件判決
大飯原発の運転再開を認めない判決を出した福井地裁の対応。
私も、その判決要旨を読んでみました。
http://www.news-pj.net/diary/1001
http://www.cnic.jp/5851
今回の判決は、読売新聞などで、原子力規制員会の判断を無視しているとか、科学技術を知らない裁判官の現実離れした判決であるとか、色々な批判を目にするが、
人の生命、生活を守るほうが、電気を生み出す経済活動より優先されるべき
という、ある意味、根本的なとてもシンプルで、当たり前すぎることを言ってるだけに過ぎないような気がする。
しかし、何故、こんなに当たり前のことが簡単なことではないように、皆言うのだろう。
夏場の電力が不足するとか、安い電力が手に入らなくなるとか、日本の経済が失速するとか、環境問題(CO2)とか。
子供が駄々をこねるように、色々と言い訳するが、結局のところ、もっと電気を使って、大量に物を生産して、日本は少子化だから、新興国にも輸出して、消費させ、お金をもっと得て、裕福になろうという欲望を肯定しているだけではないのか。
このエネルギー問題は、そういう身もふたもないような本音のところまで下りて行かないと、物事の本質は見えてこないのかもしれない。
そして、そう考えていくと、この大人が子どもに言うような当たり前のことが、私たちに突き付けてくる意味も考えなければならない。
原発の稼働を止めることで、本当に経済は失速するかもしれない。失業率も高くなるかもしれない。CO2の増加を抑えるため、節電も必要になるかもしれない。生活も今より不便になるかもしれない。今より裕福にはなれないかもしれない。
しかし、2011年のあの事故の時に、私たちに突き付けられた問題の本質は、この生命の安全と、経済活動の、どちらを優先するのかということだったのではないだろうか。
私も、その判決要旨を読んでみました。
http://www.news-pj.net/diary/1001
http://www.cnic.jp/5851
今回の判決は、読売新聞などで、原子力規制員会の判断を無視しているとか、科学技術を知らない裁判官の現実離れした判決であるとか、色々な批判を目にするが、
人の生命、生活を守るほうが、電気を生み出す経済活動より優先されるべき
という、ある意味、根本的なとてもシンプルで、当たり前すぎることを言ってるだけに過ぎないような気がする。
しかし、何故、こんなに当たり前のことが簡単なことではないように、皆言うのだろう。
夏場の電力が不足するとか、安い電力が手に入らなくなるとか、日本の経済が失速するとか、環境問題(CO2)とか。
子供が駄々をこねるように、色々と言い訳するが、結局のところ、もっと電気を使って、大量に物を生産して、日本は少子化だから、新興国にも輸出して、消費させ、お金をもっと得て、裕福になろうという欲望を肯定しているだけではないのか。
このエネルギー問題は、そういう身もふたもないような本音のところまで下りて行かないと、物事の本質は見えてこないのかもしれない。
そして、そう考えていくと、この大人が子どもに言うような当たり前のことが、私たちに突き付けてくる意味も考えなければならない。
原発の稼働を止めることで、本当に経済は失速するかもしれない。失業率も高くなるかもしれない。CO2の増加を抑えるため、節電も必要になるかもしれない。生活も今より不便になるかもしれない。今より裕福にはなれないかもしれない。
しかし、2011年のあの事故の時に、私たちに突き付けられた問題の本質は、この生命の安全と、経済活動の、どちらを優先するのかということだったのではないだろうか。
2014年5月25日日曜日
落葉/ガルシア・マルケス
マルケスの初期の短編が集められた作品集。
これが、マルケス?と思わせるような他の小説家の手法が読み取れるものもあるが、やはり、圧巻なのは、「百年の孤独」に繋がりのある「落葉」や「マコンドに降る雨を見たイサベルの独白」などだ。
葬式に連れられた男の子とその母親、そして、その母親の父である大佐。その大佐の家に突然現れて居候し、孤独のうちに死んでいった医師。
その医師は、村人の急患の診療にも応じず、村人から嫌われ続けている。
葬式に来た町長は、死んだ医師の死体の逆さ吊りを要求する。
バナナ会社が進出し、村から搾取し続け、去っていった後の荒廃したマコンド村の空気。
蔦は家々を侵し、狭い通りには雑草が伸び、土塀には亀裂が走り、女は昼日中に寝室でトカゲと出くわすのです。わたしがあらためてマンネンロウとオランダ水仙を栽培するのをやめてからは、そして、目に見えない手が食器棚のクリスマスの皿を砕き、誰も二度と着ようとはしない衣服の中の虫を太らせはじめた時からは何もかもが破壊されているように見えます。
世界の終わりのような死に行く村の空気が、何故、こんなに魅力的なのだろう。
「マコンドに降る雨を見たイサベルの独白」は、非常に短い短編だけれど、ひたすら雨が振り続けるマコンドの中で、イサベルの意識が少しずつ狂っていく感覚が描かれていて、これも何とも言えず、引き込まれる世界観である。
この作品でも、相当長く振り続けるが雨が、物語の最後には降り止むことになる。
しかし、「百年の孤独」では、4年11ヶ月と2日間雨が降り続ける。
決して読みやすい小説たちとは言えないが、マルケスの魅力が分かる短編集と言っても嘘ではあるまい。
登録:
投稿 (Atom)