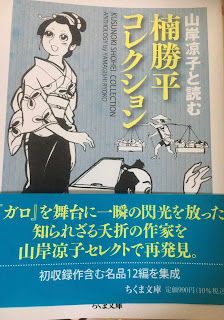今さらながら、アメリカHBOで制作されたテレビドラマ「チェルノブイリ」に衝撃を受けている。この事故は、こんな風に起きたんだということが、ものすごくリアルに伝わってくる。
チェルノブイリ原子力発電所の事故は、1986年4月26日午前1時23分に、現ウクライナキエフ州プリピャチで起きた。
発電所のコントロールルームで茫然とする技術者たち。炉心が爆発で飛び散ったという技師の報告も、地上に散乱する黒鉛(通常は炉心内で使用されるため、外部に飛び散らない)を見ても信じられず、炉心への注水と消防への通報を指示するディアトロフ副技師長。漏れた放射能の測定値も3.6レントゲンだと思い込む(36ミリシーベルト、これもすごい数値であるが、実際は500~数万レントゲンという恐ろしい数値だった)。
アメリカの攻撃か?という技師の質問も、いかにも冷戦時代下という気がする。
一方、発電所から4キロ離れたアパートで、消防士であるワシリー・イグナテンコと妻リュドミラは、衝撃波を受けた窓から、炎を立ち昇らせた発電所の光景を見、リュドミラは化学物質を気にするが(放射能については認識がなかった?)、ワシリーは義務感から非番にもかかわらず消火のため出動する。
放射能の怖ろしさもリアルである。放射能焼けし顔が赤黒くなる技師。吐瀉する技師。作業着から血がにじみ出す技師。鉄の味を口腔に感じる消防士、黒鉛をそれと知らず拾い上げ、手が焼けただれる消防士。
ブリュハーノフ原子力発電所長とフォーミン技師長に、「Under Control」と説明するディアトロフ副技師。彼らの認識は緊急用水タンクの水素爆発と建物火災という誤認に落ち着く。(私はこの「Under Control」という言葉を聞いて、オリンピック誘致の際に日本の首相が福島第一原発について世界に説明した言葉を思い出しました)
人は最悪の事態を認識せず、見たいものを見て、聞きたいものだけを聞くという典型的な状況が立ち現れる。
一方、発電所の火災の様子を、まるで花火のように子供連れで見る夫婦。きれいとつぶやく妻。やがて、彼らに雪のような灰が降りかかる。はしゃぐ子供たち。誰もそれが有害な放射性降下物だと気づかない。
もっとも悲惨なのは、爆発に至る操作をしてしまい、自責の念にかられ、すでに無くなった炉心に注水するため、炉心近くのバルブに近づき注水活動をしたアキーモフ副技師長とトプトゥーノフだろう。放射能障害で朦朧となりながらも真っ赤に焼けただれた手で注水を続け、彼らはそれが原因で悲惨な死を迎える。
旧ソビエトの政治体制の欠陥も描写される。事故を受け、急遽開催されたプリピャチ市執行委員会で、ブリュハーノフ原子力発電所長の説明に疑義を呈する委員もいたが、年老いた委員が、都市を封鎖し、電話回線を切り、市民に真実を知らせないことが得策であるという驚くべき発言を行い、議場は拍手喝さいを送る。
いかにも計画都市として整然とした街並みのプリピャチでは、子供たちが通学する中、放射能に侵され、痙攣した鳥が空から落ちてくる。プリピャチ市民は集団避難を指示されるまでの間、1時間当たり1レントゲン(10ミリシーベルト)の放射能にさらされることになる。(当時5万人が住んでいたが、30年以上経った今も立入禁止区域でほとんど人は住んでいない)
事態が正しい解決の方向に向かうのは、閣僚会議副議長兼エネルギー部門担当のボリス・シチェルビナから、RBMK原子炉の専門家ヴァレリー・レガソフに事故処理のため、政府委員会への出席を求める電話が掛かってきてからだった。
チェルノブイリのレポートを読んで、炉心が壊れたことを察知したレガソフは、ゴルバチョフ書記長が出席する政府委員会で、事実誤認の楽観的状況を話すシチェルビナに反論し、事態の重大さを専門家として説明し、ゴルバチョフはシチェルビナとレガソフにチェルノブイリに行って事態を報告するよう指示を出す。
このシチェルビナとレガソフの無骨なやり取りが、見ていて面白いのだが、このドラマから最も印象に残るのは、放射能に自らの命を縮めながら、事態の困難さを全身に受け止める二人の耐え切れなさを示すかのように繰り返されるため息と、タバコの煙とウォッカである。
実際、その後も目を覆いたくなるような光景が繰り広げられる。
VIDEO






%2C_Tokyo_National_Museum_C-59.jpg/800px-Fukai_(Noh_mask)%2C_Tokyo_National_Museum_C-59.jpg)