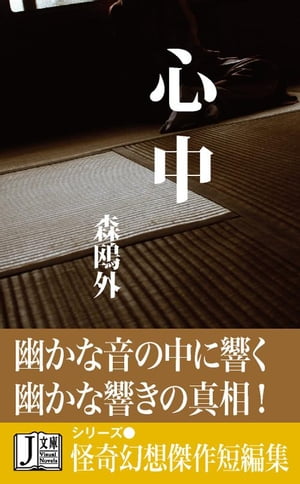秋、海辺の別荘で、森鴎外が朝の散歩をしながら、水平線から立ち昇ってくる日輪を見る。
鷗外はそれを見ながら生と死を考え、そして、過去の自分に思いを巡らす。
二十代、ドイツ留学時の「全く処女のやうな官能を以て、外界のあらゆる出来事に反応して、内にはかつて挫折したことのない力を蓄へていた時」。
それでいて、夜眠れない時、自分のしていることが、生の内容を満たすに足るか疑問に思い、ただ、舞台の上の役を勤めているに過ぎないのではないかと疑念にかられる。
自然科学では解けないこの悩みを、若い鷗外はハルトマンの無意識哲学に答えを探すが、見つからない。
やがて、留学を終え、日本に帰ってきても、鷗外は「失望を以て故郷の人に迎へられた」と感じる。(そんなはずはないのだが)
鷗外がそう感じる理由は、合理性のない改革に悉く反対したからだ。
東京の建物の高さを一定にして整然としようとする改革案に、「そんな兵隊の並んだような町は美しくは無い」とか、沢山牛肉を食わせるより「米も魚も消化の良いものだから日本人の食物はそのままがよかろう」とか、仮名遣い改良の議論も、そのままがよいと反論した。
ほとんど理にかなった反論であるが、「洋行帰りの保守主義者」と自身を揶揄している通り、鷗外の出世にはマイナスに働いたらしい(明治三十二年には小倉の軍医部長に左遷?されている)。
鷗外は、「自分はこのままで人生の下り坂を下っていく。そしてその下り果てた所が死である」ことを感じながら、ゲーテの箴言「いかにして人は己を知ることを得べきか。省察を以てしては決して能はざらん。されど行為を以てしては或は能くせむ。汝の義務を果さんと試みよ。やがて汝の価値を知らむ。汝の義務とは何ぞ。日の要求なり。」という境地、「日々の要求を義務として、それを果たしていく」ことに精神の拠り所を求めようとする。
この告白文(鷗外の自分の人生や死に対する思い)を読んで驚いたのは、今読んでも、ひどく共感できるところが多いということだ。
明治の偉人としての悩みではなく、常識的な考えを持った大人が人生の半ばを過ぎたときに感じる誠実な諦観のようなものをそこには感じる。
しかし、この作品を書いた時、鷗外はまだ四十九歳なんだけどね。人生六十年の時代だった頃は、もう晩年だったのでしょうね。