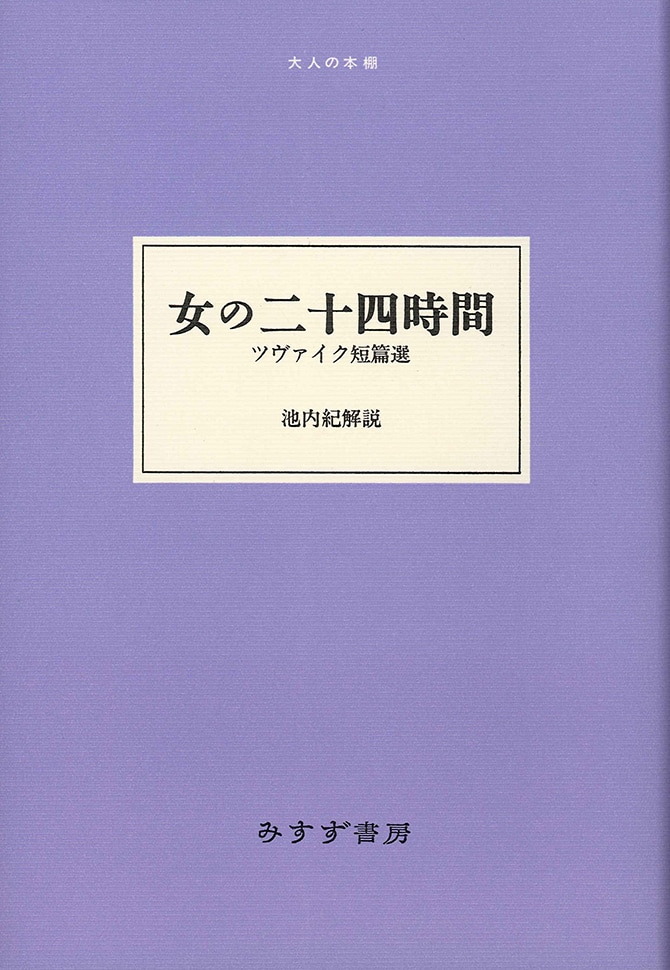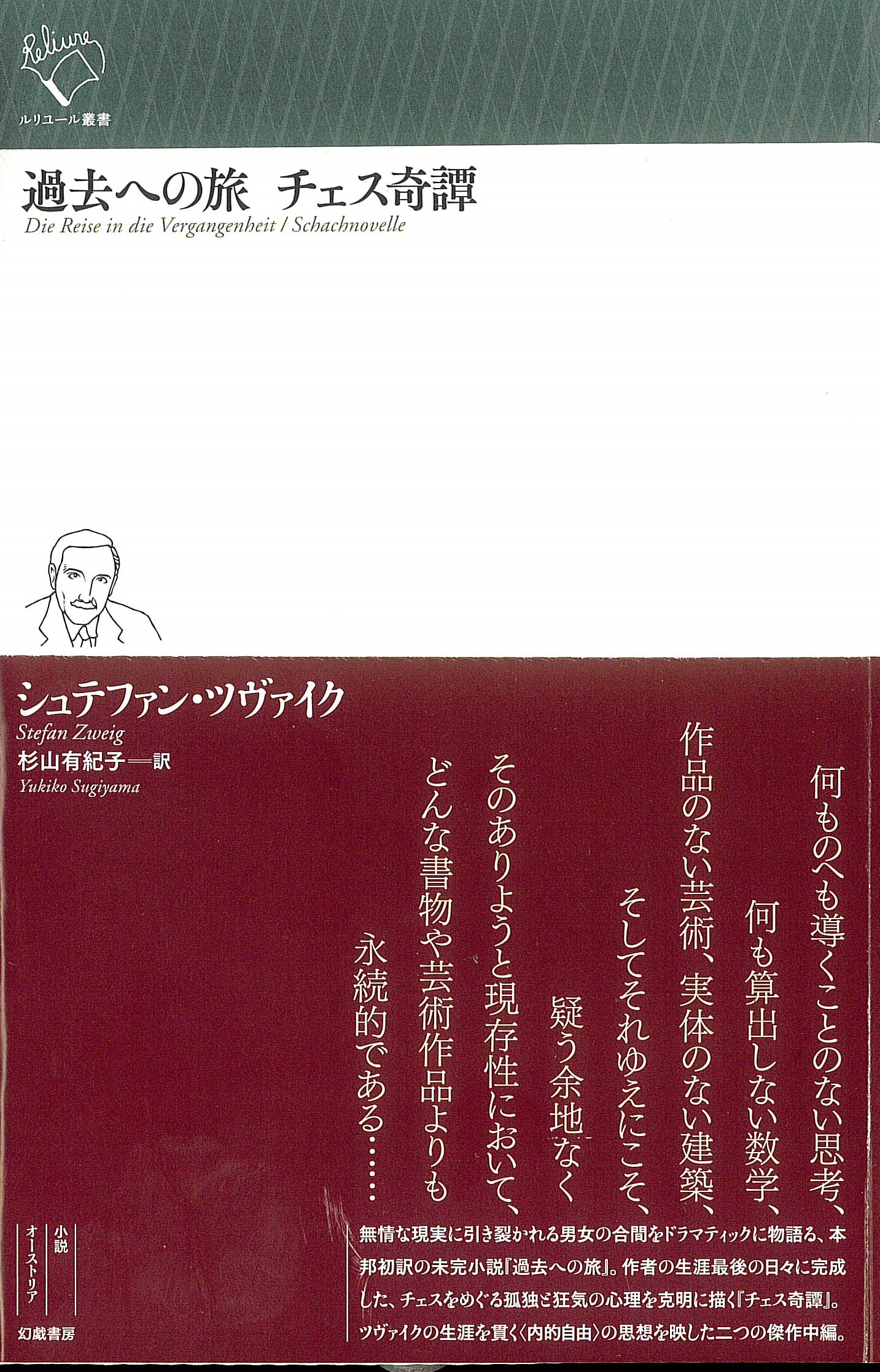クライストの小説では、登場人物たちが少なからず自分たちの運命を左右される事件が起きるのだが、この小説は、その事件がかなり多い。
1.疫病
ローマの豪商ピアキ氏が自分の息子を連れてラグーサに行ったが、そこではペストに似た疫病が蔓延しており、一人の感染した少年ニコロを助けたばかりに、ピアキ氏は自分の息子を失う。そしてピアキ氏は、病から回復したニコロを自分の養子にする。
2.火事
ピアキ氏の妻 エルヴィーレは十三歳の時、家が火事になり命を落としそうになるが、名門貴族のジェノヴァ人の若者が彼女を救い、彼はその代償に命を落とす。
エルヴィーレは自分の部屋に彼の肖像画を飾り、神のように密かに崇めていた。
3.瓜二つという偶然
ニコロは大人になり、仕事はできたが、少年の頃から早熟で女性に対する関心が異常に高く、妻をめとった後も、僧院長の愛人との関係を持っていた。
そのニコロが、ある日、その愛人と逢瀬する際に身に着けたジェノヴァの騎士の格好を、 エルヴィーレが偶然に見て気絶する。
ニコロは、 エルヴィーレの憧れていたジェノヴァ人の若者と瓜二つだったという偶然があった。
4.強姦未遂
エルヴィーレが実はひそかに自分を愛しているのではないかと誤解したニコロはエルヴィーレに対する関心を強めるが、ニコロの不徳を知っているエルヴィーレは一向に彼に対する関心を示さない。それどころか、ニコロは、その不徳を知ったピアキ氏からも冷たくされる。
ニコロはピアキ氏による冷遇もエルヴィーレのせいであると思い怨みを募らせる。そして、エルヴィーレの部屋に飾っていた騎士が実は自分ではないという真実を知った時、恥辱と情欲と復讐心から、再びジェノヴァの騎士の格好をして、エルヴィーレを我が物にしようと策略する。
5.殺人
ニコロが気絶したエルヴィーレを犯そうとしていたところに、ピアキ氏が戻ってくる。彼は、ニコロに無一文で家から出ていくことを求めるが、家の所有権はすでにニコロに移転しており、ニコロは僧院長が別れたがっていた愛人と結婚することと引き換えに、僧院長のとりなしにより、家の所有権がニコロに帰属している政府の判決書を得る。
一方、ニコロに仕掛けられた罠が原因で高熱を出したエルヴィーレは死亡し、これに憤怒したピアキ氏は、判決書を、ニコロの口にねじ込んで悶絶死させる。
6.死刑
ピアキ氏は、絞首刑による死罪の判決を下されたが、教会側が説得する自身の犯罪の有罪性の承認、免罪、神による救済の一切を拒否する。
彼は、地獄の底の底に降りて、ニコロに対する復讐をもう一度やり直すことを誓う。
これを知った教皇の命により、教会はついに彼を一切の免罪なしで、絞首刑に処す。
というかなり特異な事件に彩られている。
ピアキ氏の憤怒は、ニコロを助けたばかりに、本当の息子を失い、人生の晩年において、妻を失い、自宅の所有権を失し、すべてを失ったという結果からすれば当然ともいえるが、地獄において養子をさらに殺すと宣言するあたりは、鬼気迫るものがある。
一方でこの事件が起きてしまった原因の一つとして、エルヴィーレによる隠れた形でのジェノヴァ騎士に対する恋愛とも思える崇拝が挙げられるだろう。
エルヴィーレはピアキ氏と結婚しながらも、実はピアキ氏を愛してはおらず、十三歳の時に自分を救ってくれたジェノヴァ騎士を愛していたという事実も重い。
彼女は、ジェノヴァ騎士の姿をしたニコロを見て二度失神するが、ニコロが情欲を感じた通り、それは恐怖によるものではなく、愛する者とリアルに接触するという歓喜のために起こったものだろう。
という具合に、この短編小説は、クライスト特有の事件に翻弄される人々を描きながらも、実に技巧的で精緻な構成になっている。
この小説も、クライストがピストル自殺をした年に出版されたものだ。




.JPG/1200px-Kleist%2C_H._V._Der_Findling_(1811).JPG)