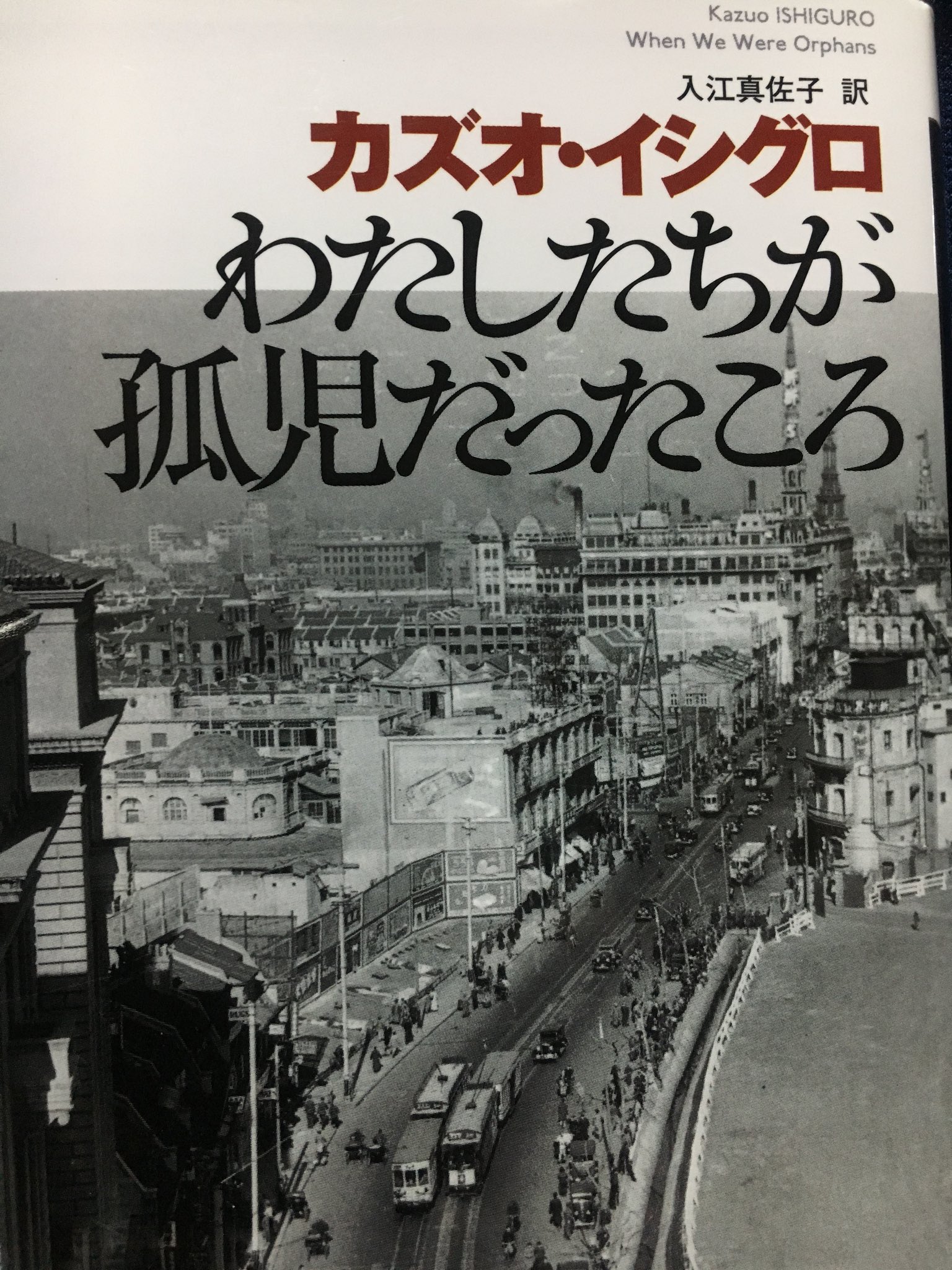アーシュラ・K・ル=グヴィンが1月22日に亡くなったことを知ったせいもあるが、偶然読んでいたゲド戦記Ⅰの続きを読みたくなってしまった。
岩波少年文庫の本書を読み終えて思うのは、この物語は、大人が読んでもおかしくない緻密さとテーマを秘めているということだ。
ゲド戦記Ⅰでは、ゲドが抱えてしまった自分の影との闘いを描いており、本書では、幽閉された墓所に幼いうちに連れてこられ、闇の大巫女として育てられて、やがては自分の名前さえ忘れてしまったアルハ(本当の名はテナー)が、墓所の宝庫に、世界に平和をもたらすという腕輪を探しにきたゲドと出会い、葛藤しながらも、自分を取り戻して、ゲドとともに自由な世界に旅立つという物語だ。
しかし、この物語に深みを与えているのは、実に物語の半分をも費やし、アルハが閉じ込められていた闇の世界を描いているところだろう。この闇の比重が物語後半であふれ出る光のまぶしさを際立たせている。
それにしても、宮崎駿の作品のルーツのような要素が、ル=グヴィンの描くアース―シーの世界には満ちている。
ゲドがテナーを載せて船で旅立とうとする場面は、まるで未来少年コナンの一場面のように希望に満ちた明るい映像が浮かんでくる。
冒頭に添えられる物語の舞台となる世界を描写した具体的な地図も、ナウシカに代表される作品で多くみられる共通点だ。
2018年1月28日日曜日
2018年1月22日月曜日
西部 邁さんの死
西部 邁さんの死を知って、かなりショックを覚えた。
私が、西部 邁さんに好感を持ったのは、彼のテレビでの一見ひねくれたロジックに、筋の通った信念を感じていたことと、彼の書く文章が論理的で読みやすかったこと、そして、私が好きな林達夫と井上達夫をともに称揚していたことにある。
あわてて、書籍から「生まじめな戯れ」を取り出したが、私が読みたかったのは、たぶん別の本に書かれていた彼の自伝的文章だ。
それは、彼が若い頃に吃音のくせがあったが、学生運動の際、大勢の前で演説をすることとなり、ここが正念場と覚悟を決めて話したら、以来、吃音なしで話せるようになったという内容で、そのせいか、彼は吃音の癖がある人をみると、そういった覚悟を持たずに過ごして来てしまった人ではないかという思いがよぎってしまうという文章だ。
大多数の論調に臆せず、少数意見をぶつける人だったが、実は相当な努力家で繊細な人だったのかもしれない。
ご冥福をお祈りします。
私が、西部 邁さんに好感を持ったのは、彼のテレビでの一見ひねくれたロジックに、筋の通った信念を感じていたことと、彼の書く文章が論理的で読みやすかったこと、そして、私が好きな林達夫と井上達夫をともに称揚していたことにある。
あわてて、書籍から「生まじめな戯れ」を取り出したが、私が読みたかったのは、たぶん別の本に書かれていた彼の自伝的文章だ。
それは、彼が若い頃に吃音のくせがあったが、学生運動の際、大勢の前で演説をすることとなり、ここが正念場と覚悟を決めて話したら、以来、吃音なしで話せるようになったという内容で、そのせいか、彼は吃音の癖がある人をみると、そういった覚悟を持たずに過ごして来てしまった人ではないかという思いがよぎってしまうという文章だ。
大多数の論調に臆せず、少数意見をぶつける人だったが、実は相当な努力家で繊細な人だったのかもしれない。
ご冥福をお祈りします。
2018年1月21日日曜日
ゲド戦記Ⅰ 影との闘い/アーシュラ・K・ル=グヴィン
小中学生向けの作品ということもあるが、文章が非常に読みやすく(翻訳者の清水真砂子さんの文章力にもよると思う)、いい作品だなと思った。
ファンタジー作品なのに、文章に浮ついたところがない。
そして、圭角の多い主人公 ハイタカ/ゲドが魔法使いとしての修行をする中で自分に取りついた影と闘う物語は、あまりにも馴染みのあるストーリーと言っていい。
この作品から影響を受けたと思われる数多くの作品を自然に思い起こすことができるのが、その偉大さを証明している。
スター・ウォーズのフォースと暗黒面は、そのものだと言えるし、宮崎駿の「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」などにもその影響をみることができる。西尾維新のライトノベル小説「猫物語(白)」まで、カバーしてしまうと思う。
この作品は、「イシが伝えてくれたこと 鶴見俊輔」(近現代作家集 III/日本文学全集28)を読み終わった時から読みたかった本だが、ようやく、読み終わることができた。
一人の原住アメリカ人が示した欧米文明に対する批評の精神を受け継いだル=グヴィンが、このような豊かな作品を作り上げたことが、まるで奇跡のように思える。
ファンタジー作品なのに、文章に浮ついたところがない。
そして、圭角の多い主人公 ハイタカ/ゲドが魔法使いとしての修行をする中で自分に取りついた影と闘う物語は、あまりにも馴染みのあるストーリーと言っていい。
この作品から影響を受けたと思われる数多くの作品を自然に思い起こすことができるのが、その偉大さを証明している。
スター・ウォーズのフォースと暗黒面は、そのものだと言えるし、宮崎駿の「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」などにもその影響をみることができる。西尾維新のライトノベル小説「猫物語(白)」まで、カバーしてしまうと思う。
この作品は、「イシが伝えてくれたこと 鶴見俊輔」(近現代作家集 III/日本文学全集28)を読み終わった時から読みたかった本だが、ようやく、読み終わることができた。
一人の原住アメリカ人が示した欧米文明に対する批評の精神を受け継いだル=グヴィンが、このような豊かな作品を作り上げたことが、まるで奇跡のように思える。
2018年1月8日月曜日
わたしたちが孤児だったころ/カズオ・イシグロ
「孤児」とは、親のない子、みなしごのことだが、タイトルにある「わたしたち」とは、主人公のクリストファー・バンクスと彼が養子に引き取ったジェニファーのことを意味しているのだろう。
でも、この物語を読み終えると、常に自分が輝く場所を求め、社交界をさまよっていたサラ・ヘミングスも「孤児」のようだし、アヘン戦争をめぐるイギリスと中国の関係に翻弄され、過酷な運命を辿ったクリストファーの両親や、日中戦争に翻弄されたアキラも「孤児」のように思える。
フィリップおじさんさえ、「孤児」と言えるのかもしれない。
その孤児たちの運命を知るため、失踪した両親を探すために私立探偵となったクリストファーに過去の記憶を遡らせ、決して戻ることができない現在につなげるという手法は、「追憶」を得意とするカズオ・イシグロらしい物語だと思う。
さらにいえば、タイトルにある「孤児だった」という過去形になっていることが、この物語の穏やかな終わりを暗示していると思う。
しかし、これは本当に英語を母国語にした作家の作品なのだろうか。
私は、まるで、近現代の時代に置き換えられた「安寿と厨子王」を読んでいるような気分になった。
でも、この物語を読み終えると、常に自分が輝く場所を求め、社交界をさまよっていたサラ・ヘミングスも「孤児」のようだし、アヘン戦争をめぐるイギリスと中国の関係に翻弄され、過酷な運命を辿ったクリストファーの両親や、日中戦争に翻弄されたアキラも「孤児」のように思える。
フィリップおじさんさえ、「孤児」と言えるのかもしれない。
その孤児たちの運命を知るため、失踪した両親を探すために私立探偵となったクリストファーに過去の記憶を遡らせ、決して戻ることができない現在につなげるという手法は、「追憶」を得意とするカズオ・イシグロらしい物語だと思う。
さらにいえば、タイトルにある「孤児だった」という過去形になっていることが、この物語の穏やかな終わりを暗示していると思う。
しかし、これは本当に英語を母国語にした作家の作品なのだろうか。
私は、まるで、近現代の時代に置き換えられた「安寿と厨子王」を読んでいるような気分になった。
登録:
投稿 (Atom)