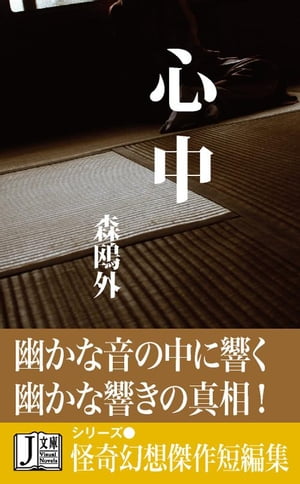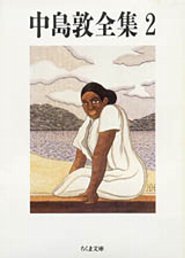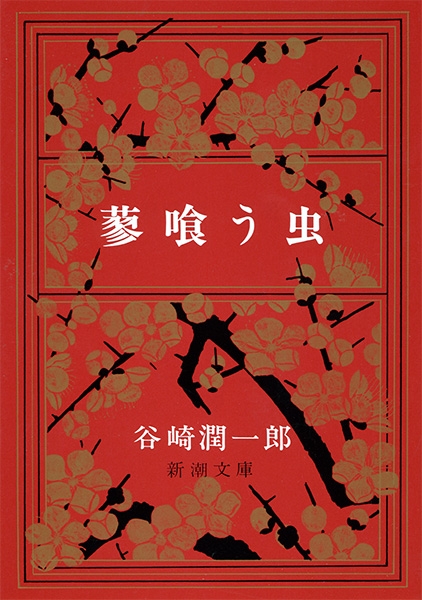文學界の11月号で、村上春樹がスタン・ゲッツについて書いていた記事を読んでいて、興味が湧き、この本を読んでみたのだが、非常に読み応えのある本だった。
スタン・ゲッツの生れてから死ぬまでのいきさつ、歪んだ母親の愛情、優秀なテナーサックスのプレイヤーとしての側面と酒とドラッグの中毒に苦しめられ、それが家族への暴力にまで及んでいた事実が事細かに書かれていて、芸術家の二面性というものの不思議さを感じた。
実際、スタンは十六歳には、有名なジャズトロンボーン奏者ジャック・ティーガーデンに才能を見込まれ、彼のバンドに加わり、その頃から、まわりにも勧められて酒やタバコを呑みはじめ、やがてヘロインによる恍惚感を体験し、麻薬中毒者になるのだが、スタンの音楽的才能は、まったく影響を受けないかのように順調に開花していく。
ケントンの首席サキソフォン・ソロイストになり、ベニー・グッドマン、ウディ・ハーマンの楽団に入り、活躍する。そして「初秋(Early Autumn)」の演奏で、一気に彼はスターダムへのし上がる。
二十七歳の時には、麻薬容疑で逮捕され、収監前に麻薬切れに苦しみ、モルヒネを入手しようとドラッグストアで強盗未遂事件を起こしてしまう。
刑務所では精神的鬱に苛まれ、以前よりさらに酒を飲み、アルコールによる麻痺状態を求めるようになる。
二人目の妻 モニカとのアルコールをめぐる闘いは壮絶な域に達している。過度のアルコールや睡眠薬の服用で正気を失ったスタンが彼女や子供たちを殴り、やがて耐え切れなくなったモニカが、ひそかにアンタビューズ(Antabuse 抗酒癖剤)を料理に混ぜるようになり、スタンはアルコールを飲む度にひどい吐き気に襲われるようになる。(スタンは後にその事実を知り、許せなかった彼はモニカと離婚している。しかし、その離婚も途方もない時間と金額がかかる訴訟を経てようやくのことだ)
一方で、スタン・ゲッツの音楽はさらに成熟度を増し、1961年(三十四歳)の時に革新的なアルバム「フォーカス」を作り上げる。1962年には、ボサノヴァ音楽と出会い、アルバム「ジャズ サンバ」を発表する。この「ジャズ サンバ」は、ジャズなのにビルボードの1962年9月15日号のポップ・アルバム部門のチャートに顔を出すほど売れることになる。このアルバムを契機に、全米にボサノヴァブームが吹き荒れることになる。
(アントニオ・カルロス・ジョビンが説明するボサノヴァとは「新しい感覚」を言う)
そして、ボサノヴァの神とも呼ばれるジョアン・ジルベルトと、アルバム「ゲッツ/ジルベルト」を作り上げる。このアルバムはビルボードのアルバム・チャートで2位に達する大ヒット作となり、グラーミー賞では最優秀アルバム賞などを受賞する。
このアルバムでボーカルを務めているジョアンの元妻 アストラッド・ジルベルトは、普通の主婦だったが、スタンが彼女の無垢を感じさせる声に惹かれ、急遽、レコーディングになったということも意外だった。
スタン・ゲッツが断酒と薬物の摂取を止めることができたのは1985年(五十八歳)のことだ。しかし、1988年には肝臓がんが見つかり、一時は回復の基調があったが、1991年には2つ目の肝臓がんが発見され、最後はモルヒネを投与され、安らかに死を迎えている。
訳者の村上春樹は、スタン・ゲッツについて、作家のフィッツジェラルドに例えて「フィッツジェラルドはどのようなつまらない小説でも、うまく書かないわけにはいかなかった。それはおそらくスタン・ゲッツに関しても言えることではあるまいか」と評している。
言い換えるなら、彼が手を触れた音楽には、それがたとえ比較的価値の劣る作品であったとしても、そこには必ず「スタン・ゲッツ」という刻印が明瞭にきざまれることになった。
また、スタン・ゲッツの音楽の神髄を「リリシズム」、筋の通った「叙情精神」と述べている。そして、「その力は本人の自由意志では制御することのできない内的な力だ。その力は、美しい芸術を産み出すための根源的なソースとなり、またあるときには持ち主の魂を鋭くついばむ永遠のデーモンともなる。」と。
本書は、この他にも、1945年頃のチャーリー・パーカーやマイルズ・デイヴィス、ビリー・ホリデー、サラ・ヴォーンが居たジャズ全盛期のニューヨークのクラブの様子が描かれており、ジャズファンならずとも興味がそそられる内容が多いと思う。
(日本の敗戦時期に、こんなに豊かな音楽が奏でられていたことは少し皮肉に思った)