これも、作中、森鴎外、本人らしき人物が出てくる。
その本人が女中から聞いた話である。
ある料理屋の二階で女中、十四五人が寝ている。
雪が降った寒い夜、目が覚めてしまった女中二人が憚り(便所)に行こうとする。
しかし、憚りは二階から遠い処にある。
梯子を下りて、長い、狭い廊下を通っていかなければならない。
途中、庭の竹のさらさらと擦れ合う音が怖かったり、石灯籠が白い着物を着た人がしゃがんでいるようにも見える。
左の方には茶室のような四畳半の部屋があり、女の泣き声が聞こえるという作り話のようなことを言う者もいる。
便所の前には、一燭ばかりの電灯が一つ附いているが、それが宙に浮かんでいるように、途中の廊下は暗黒である。
行く途中、二人は「ひゅうひゅう」という奇妙な音を聞く。
最初は便所からするものだと思っていたその音が、実は四畳半の部屋から聞こえてくることに気づく。
意を決した女中が襖を開けると、そこに見えたものは...という物語だ。
結末はタイトルを見れば何となく想像がつくと思うが、私は何と言っても、この便所までの遠い道のりに、とても懐かしさを覚えた。
昔ながらの日本家屋に住んだことがある人なら覚えがあるだろうが、なぜ、あんなに便所は遠いのだろう。
風の強い寒い夜、目覚めてしまって、暗い冷たい廊下を歩く時間の長さを感じながら、ざわざわと騒ぐ風の音に何となく恐怖感を覚える。
この作品を読んで、その感覚を久々に思い出した。

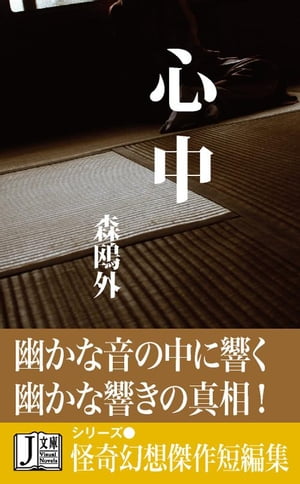
0 件のコメント:
コメントを投稿