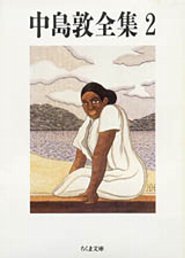カフカの作品は、読む度に印象ががらって変わってしまうところが本当に面白い。
この「訴訟」(今までの翻訳版では「審判」という名称が多かったと思う)という作品。
このタイトルの変更の印象のせいかもしれないが、主人公Kの言葉遣いもぞんざいな感じで訳されているせいなのか、今までは、どちらかというと、抗らえない不条理な国家権力の不気味さ、それに対する個人の無力感という印象しかなかった作品が、改めて読んでみると、まるでパロディのような印象を持った。
特に笞打人の章は、想像するだけで笑ってしまう。まるでデビット・リンチが撮るカルトチックな一場面のようだ。
カフカ自身、この作品を友人たちの前で朗読する際、笑いの発作に襲われて何度も小休止せざるを得なかったという、マックス・ブロートの証言が巻末の解説で説明されていたのも興味深い。

2020年8月31日月曜日
2020年8月30日日曜日
章魚木の下で・書簡/中島敦
中島敦がパラオ南洋庁国語教科書編集書記として赴任していたのは、昭和16年7月から17年3月頃まで、わずか9か月の期間であるが、この期間が彼の創作活動や喘息持ちの健康状態によい影響を与えたのか、悪い影響を与えたのか、判別がつかないところがある。
家族宛てに送った書簡には、寒い日本の冬を避けられた安堵感が述べられているが、パラオで下痢やデング熱にかかってしまったり、湿気に苦しむ様子が述べられている。一方で、ポナペ(ポンペイ島)、トラック島、サイパンに小旅行すると、体も復調し、少し太ったという記述も見られる。
ただ、旅行から戻ってもパラオでの暑気は体に堪えるらしく、「一日も早く今の職をやめないと、体も頭脳も駄目になってしまう」とか、「記憶力の減退には我ながら呆れるばかり」という記述も見られる。創作活動も「この暑さ、むし暑さでは、頭を働かせることは、殆ど不可能といってもいい」と創作活動が進んでいない様子が述べている。
しかし、間違いなく、中島敦にこの南洋での体験がなかったら、「南島譚」や「環礁」といった作品群は書かれなかったことを思うと複雑な気持ちになる。
私の好みでいうと「李陵」や「弟子」より、これら南洋もののほうが、力みのようなものが抜けており、読んでいて面白いからだ。
昭和16年12月の真珠湾攻撃による日米開戦の影響もあり、彼は結局、昭和17年3月の冬の寒さの真っただ中の日本に戻り、たちまち風邪をひき、体調を崩してしまい、同年12月には喘息の悪化で命を落としてしまうのだが、まだ、三十三歳、作家としてはまだこれからという時期だっただけに本当に惜しいことだったと思う。
南洋の旅が逆に彼の寿命を縮める原因となってしまったのかもしれないが、彼が最後に書いたというエッセイ「章魚木の下で」を読むと、もともとの中島敦の理念であったとは思うが、南洋にいたことも影響して、日本国内で湧き上がった戦争熱に染まらなかった健全な文学者の最後の姿が見られる。
まだ若かったのに病気で亡くなったこと、大きな戦争が始まる足跡を聞きながら、悲惨な状態になる前にこの世を去ったこと、短い創作活動だったが良質な他人に真似ができない作品を生み出したこと、死後、書簡や断片的作品も含めて研究され続けていることなどが共通しているように思う。
家族宛てに送った書簡には、寒い日本の冬を避けられた安堵感が述べられているが、パラオで下痢やデング熱にかかってしまったり、湿気に苦しむ様子が述べられている。一方で、ポナペ(ポンペイ島)、トラック島、サイパンに小旅行すると、体も復調し、少し太ったという記述も見られる。
ただ、旅行から戻ってもパラオでの暑気は体に堪えるらしく、「一日も早く今の職をやめないと、体も頭脳も駄目になってしまう」とか、「記憶力の減退には我ながら呆れるばかり」という記述も見られる。創作活動も「この暑さ、むし暑さでは、頭を働かせることは、殆ど不可能といってもいい」と創作活動が進んでいない様子が述べている。
しかし、間違いなく、中島敦にこの南洋での体験がなかったら、「南島譚」や「環礁」といった作品群は書かれなかったことを思うと複雑な気持ちになる。
私の好みでいうと「李陵」や「弟子」より、これら南洋もののほうが、力みのようなものが抜けており、読んでいて面白いからだ。
昭和16年12月の真珠湾攻撃による日米開戦の影響もあり、彼は結局、昭和17年3月の冬の寒さの真っただ中の日本に戻り、たちまち風邪をひき、体調を崩してしまい、同年12月には喘息の悪化で命を落としてしまうのだが、まだ、三十三歳、作家としてはまだこれからという時期だっただけに本当に惜しいことだったと思う。
南洋の旅が逆に彼の寿命を縮める原因となってしまったのかもしれないが、彼が最後に書いたというエッセイ「章魚木の下で」を読むと、もともとの中島敦の理念であったとは思うが、南洋にいたことも影響して、日本国内で湧き上がった戦争熱に染まらなかった健全な文学者の最後の姿が見られる。
章魚木(たこのき)の島で暮していた時戦争と文学とを可笑しい程截然と区別していたのは、「自分が何か実際の役に立ちたい願い」と、「文学をポスター的実用に供したくない気持」とが頑固に素朴に対立していたからである。章魚木の島から華の都へと出て来ても、此の傾向は容易に改まりそうもない。まだ南洋呆けがさめないのかも知れぬ。比べるのはおかしいかもしれないが、中島敦とカフカの共通点を妙に感じてしまう。
まだ若かったのに病気で亡くなったこと、大きな戦争が始まる足跡を聞きながら、悲惨な状態になる前にこの世を去ったこと、短い創作活動だったが良質な他人に真似ができない作品を生み出したこと、死後、書簡や断片的作品も含めて研究され続けていることなどが共通しているように思う。
2020年8月17日月曜日
狼疾記/中島敦
狼疾記(ろうしつき)と読む。
孟子の書に、「指一本惜しいばかりに、肩や背中まで失っても気づかない人を「狼疾の人」という」言葉があり、冒頭、その漢文が引用されている。
この言葉を、この小説(?)に当てはめれば、自分という存在は何なのかという問いの答えを知りたいがばかりに、生きることの本質や喜びを見失ってしまっている主人公の三造が「狼疾の人」ということになるのだろう。
何をやっても、自分という存在の不確かさに考えが及び、生きることが無意味に思えてしまう。
酒を飲んで酔っ払っても、自分の発言や行動を厳しく検分する自意識に苛まれ、眠ろうとしても、二・三時間は眠れない。
すでに中学生の時から、そのような思いが憑りついてしまっていたというのだから、作者が書いた「悟浄出世」の悟浄のように、重い病にかかってしまったというほか、ないかもしれない。
途中、主人公の三造が、読んでいたフランツ・カフカの「巣穴」について、「何という奇妙な小説であろう」と感想を述べているが、作者の中島敦もこの「巣穴」を読んで実際に同じような印象を受けたような気がする。
「巣穴」では、実在するかも分からない外敵を警戒し、自己保全のために巣穴を改良することに汲々とする小動物を描いているが、自分の存在の不確かさに悩まされる三造の姿を、まるで戯画化されているような気分を味わったに違いない。
思えば、カフカが書く他の小説の主人公も、いや、カフカ自身も「狼疾の人」だった。
中島敦がカフカ自身の奇妙な実生活まで知っていたとは思えないが、他の小説を読んで
自分との共通点に気づいていた可能性は高い。
孟子の書に、「指一本惜しいばかりに、肩や背中まで失っても気づかない人を「狼疾の人」という」言葉があり、冒頭、その漢文が引用されている。
この言葉を、この小説(?)に当てはめれば、自分という存在は何なのかという問いの答えを知りたいがばかりに、生きることの本質や喜びを見失ってしまっている主人公の三造が「狼疾の人」ということになるのだろう。
何をやっても、自分という存在の不確かさに考えが及び、生きることが無意味に思えてしまう。
酒を飲んで酔っ払っても、自分の発言や行動を厳しく検分する自意識に苛まれ、眠ろうとしても、二・三時間は眠れない。
すでに中学生の時から、そのような思いが憑りついてしまっていたというのだから、作者が書いた「悟浄出世」の悟浄のように、重い病にかかってしまったというほか、ないかもしれない。
途中、主人公の三造が、読んでいたフランツ・カフカの「巣穴」について、「何という奇妙な小説であろう」と感想を述べているが、作者の中島敦もこの「巣穴」を読んで実際に同じような印象を受けたような気がする。
「巣穴」では、実在するかも分からない外敵を警戒し、自己保全のために巣穴を改良することに汲々とする小動物を描いているが、自分の存在の不確かさに悩まされる三造の姿を、まるで戯画化されているような気分を味わったに違いない。
思えば、カフカが書く他の小説の主人公も、いや、カフカ自身も「狼疾の人」だった。
中島敦がカフカ自身の奇妙な実生活まで知っていたとは思えないが、他の小説を読んで
自分との共通点に気づいていた可能性は高い。
(カフカの書いたイラスト)
2020年8月16日日曜日
かめれおん日記/中島敦
この作品をエッセーと呼ぶことに、躊躇いを感じるのは、あまりにも多くの事柄が一つの文章に含まれているせいだろうか。
- 生徒からカメレオンを貰う話
- 実務的・現実的な同僚 吉田の話
- 夜空の星座の話
- ゲーテの「詩と真実」の話
- Operaという単語からの連想
- 自分の生き方をめぐる考察
- 不眠症の話
- 体調不良と薬の話
- 自分の体内の臓器に関する考察
- 失望しないための決心に関する考察
- 和歌五首
- 常識・慣習から離れた自由に関する考察
- 自己を責める悪癖について
- 三連休の睡眠と体調不良について
- カメレオンを見ながらの眠気と字を書くことの億劫さ
- 自分の精神のあり方を説明していたある文章の一節
- 同僚 吉田の処世術に関する話
- 幸福に関して、老子からの引用
- 暴力、腕力に対処すべき方法
- カメレオンを上野動物園に預ける話
- 赤ん坊を抱いた元音楽教師を見つめる女教師(未婚の老嬢達!)の視線について
- カメレオンからかつて飼っていたインコ、オウムへの思い
- 同僚 Kの高等教員検定試験合格の話
- 横浜山手の外人墓地の散策
- エウリピデスの作品の一節
これのヒントになるかどうかは分からないが、文中で、中島が自己の精神の欠陥であるかのように以下の通り説明している。
正に「かめれおん」にふさわしい中島敦の精神世界の多様性とでも言うしかない。
ものを一つの系列――或る目的へと向って排列された一つの順序――として理解する能力が私には無い。一つ一つをそれぞれ独立したものとして取上げて了う。一日なら一日を、将来の或る計画のための一日として考へることが出来ない。それ自身の独立した価値をもった一日でなければ承知できないのだ。一つのテーマに結び付ける工夫をしたり、全体のバランスを調整して書くという手法以前に、これだけの多種多様なテーマが頭の中で渦巻いていること自体、稀有なことではないか。とても、常人が書ける代物ではない。
正に「かめれおん」にふさわしい中島敦の精神世界の多様性とでも言うしかない。
2020年8月15日土曜日
真昼/中島敦
「環礁 ミクロネシヤ巡島記抄」からの一篇。
「目がさめた。」という冒頭の文章から、ランボーの詩「夜明け」を意識しているように思ったら、真ん中のあたりで「永遠」の一節が引用されていた。
南洋の何にもない真昼過ぎ、快い午睡から目覚めて、青い海と空を眺め、白い珊瑚屑がかすかに崩れる心地よい音を聞いても、中島は幸せを感じることなく、自分が求めているものは、怠惰と安逸ではなく、未知の環境での自己の新たな才能の発掘と来たるべき戦争の戦場に選ばれることを予想しての冒険への期待だったはずだと自分を責める。
(中島敦がパラオ南洋庁国語教科書編集書記として赴任していたのは、昭和16年7月から17年3月頃まで。大日本帝国海軍が真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が開戦した時期である。中島敦が戦争に楽観的な印象を抱いていたことが分かる一節で興味深い。)
そして、自分がいかに西洋文明に基づいた意識で南洋の世界を見ているかに気づき、何処にいても変わらない自意識に辟易とする。
中島自身おかしがっているが、島民(土民と呼んでいる)の家屋で寝ていたときに、何故か、歌舞伎座のみやげもの屋の明るい店先とその前を行き交う人波を思い出したというエピソードも面白い。
彼は何故そんな光景を突然思い出したのか「皆目判らぬ」と言っているが、何のことはない、美しいけれど寂しい南洋の世界に居ながら、都会の華美な喧騒を懐かしんでいるのだ。
中島敦の代表作をみると、特に中国古典に基づいた作品を読むと、彼がいかにも老成した作家のように思えてしまうのだが、この作品からは、自意識に悩まされ、都会にも未練があるまだ若い三十二歳の男の精神が垣間見える。
「目がさめた。」という冒頭の文章から、ランボーの詩「夜明け」を意識しているように思ったら、真ん中のあたりで「永遠」の一節が引用されていた。
南洋の何にもない真昼過ぎ、快い午睡から目覚めて、青い海と空を眺め、白い珊瑚屑がかすかに崩れる心地よい音を聞いても、中島は幸せを感じることなく、自分が求めているものは、怠惰と安逸ではなく、未知の環境での自己の新たな才能の発掘と来たるべき戦争の戦場に選ばれることを予想しての冒険への期待だったはずだと自分を責める。
(中島敦がパラオ南洋庁国語教科書編集書記として赴任していたのは、昭和16年7月から17年3月頃まで。大日本帝国海軍が真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が開戦した時期である。中島敦が戦争に楽観的な印象を抱いていたことが分かる一節で興味深い。)
そして、自分がいかに西洋文明に基づいた意識で南洋の世界を見ているかに気づき、何処にいても変わらない自意識に辟易とする。
中島自身おかしがっているが、島民(土民と呼んでいる)の家屋で寝ていたときに、何故か、歌舞伎座のみやげもの屋の明るい店先とその前を行き交う人波を思い出したというエピソードも面白い。
彼は何故そんな光景を突然思い出したのか「皆目判らぬ」と言っているが、何のことはない、美しいけれど寂しい南洋の世界に居ながら、都会の華美な喧騒を懐かしんでいるのだ。
中島敦の代表作をみると、特に中国古典に基づいた作品を読むと、彼がいかにも老成した作家のように思えてしまうのだが、この作品からは、自意識に悩まされ、都会にも未練があるまだ若い三十二歳の男の精神が垣間見える。
2020年8月14日金曜日
夾竹桃の家の女/中島敦
「環礁 ミクロネシヤ巡島記抄」からの一篇。
デング熱に罹り、まだ病から回復しきれていない作者が、だるさを抱えたまま、パラオの村を歩いている。
風が止み、蒸し風呂のように熱く重たい空気に病み上がりの体が耐え切れなくなってしまった作者がふと立ち寄った島民の家で、赤ん坊に乳を含ませた上半身裸の若い女と目が合ってしまう。作者は若い女が自分に欲情していると感じ、作者も若い女にほのかに欲望を感じている。
そんな状況になったのは、その日の温度と湿度、花の匂いのせいだと作者は理由を説明している。
そして、そんな混濁した感情を洗い流してくれるような激しいスコール。
雨上がりの道で再び会った若い女の澄ました顔が、このエピソードに妙なリアリティを与えている。
中島敦の作品としては、珍しくエロティックな印象が残る短編だ。
デング熱に罹り、まだ病から回復しきれていない作者が、だるさを抱えたまま、パラオの村を歩いている。
風が止み、蒸し風呂のように熱く重たい空気に病み上がりの体が耐え切れなくなってしまった作者がふと立ち寄った島民の家で、赤ん坊に乳を含ませた上半身裸の若い女と目が合ってしまう。作者は若い女が自分に欲情していると感じ、作者も若い女にほのかに欲望を感じている。
そんな状況になったのは、その日の温度と湿度、花の匂いのせいだと作者は理由を説明している。
そして、そんな混濁した感情を洗い流してくれるような激しいスコール。
雨上がりの道で再び会った若い女の澄ました顔が、このエピソードに妙なリアリティを与えている。
中島敦の作品としては、珍しくエロティックな印象が残る短編だ。
2020年8月11日火曜日
中国共産党および香港政府による国家安全維持法に基づいた香港民主活動家に対する弾圧
香港国家安全維持法が異常な手続きとスピードで成立・施行されたのが6月30日。
そこから3か月も経たない間に、香港民主活動家である蘋果日報(アップル・デイリー)創業者の黎智英(ジミー・ライ)氏と民主活動家の周庭(アグネス・チョウ)氏を中心とする男女10人が、8月10日、香港警察に逮捕された。
黎智英氏と周庭氏に対する容疑は、香港への制裁を外国に働きかけたとして、香港国家安全維持法で禁止する「外国勢力との結託」に違反する容疑で逮捕されたものらしい。
いよいよ、中国共産党は、香港民主活動家に対する弾圧を本格的に進めることを決断したと思われるが、日本は同じ民主主義の価値観を共有する人々への弾圧に明確に強く抗議すべきだ。
あのCOVID-19対策で失点続きのトランプ政権でさえ、中国・香港の関係する政府高官等に対して、制裁などの手段を使って、中国共産党に香港政策の再考を迫る一連の取り組みを進めている。
イギリスも、7月22日、約300万人の香港市民がイギリス市民権を獲得できるようになる特別ビザの条件を公表している。
今回の件に関して、中国共産党・香港政府に対する明確な非難の意思表示を行わないことは、日本国自身が民主主義を尊重しない国家であることを黙示的にも表明したのに等しい。
もう、天安門事件のように、今回の事件を成功例にしてはいけない。
そこから3か月も経たない間に、香港民主活動家である蘋果日報(アップル・デイリー)創業者の黎智英(ジミー・ライ)氏と民主活動家の周庭(アグネス・チョウ)氏を中心とする男女10人が、8月10日、香港警察に逮捕された。
黎智英氏と周庭氏に対する容疑は、香港への制裁を外国に働きかけたとして、香港国家安全維持法で禁止する「外国勢力との結託」に違反する容疑で逮捕されたものらしい。
いよいよ、中国共産党は、香港民主活動家に対する弾圧を本格的に進めることを決断したと思われるが、日本は同じ民主主義の価値観を共有する人々への弾圧に明確に強く抗議すべきだ。
あのCOVID-19対策で失点続きのトランプ政権でさえ、中国・香港の関係する政府高官等に対して、制裁などの手段を使って、中国共産党に香港政策の再考を迫る一連の取り組みを進めている。
イギリスも、7月22日、約300万人の香港市民がイギリス市民権を獲得できるようになる特別ビザの条件を公表している。
今回の件に関して、中国共産党・香港政府に対する明確な非難の意思表示を行わないことは、日本国自身が民主主義を尊重しない国家であることを黙示的にも表明したのに等しい。
もう、天安門事件のように、今回の事件を成功例にしてはいけない。
寂しい島 環礁ーミクロネシヤ巡島記抄ー/中島敦
タロ芋畑も、白い砂浜も、サンゴ礁も美しいのに、子供が何故か生まれない島を「此処ほど寂しい島はない」と中島敦は言う。
そして、その理由を「神がこの島の人間を滅ぼそうと決意したからだろう。非科学的と嗤われても、そうでも考えるより外、仕方が無いようである」と彼が感じたのは、日本から離れ、圧倒的な自然に囲まれた南洋の雰囲気に神の存在を感じたせいだろうか。
寂しい島の滅びを悲しみつつも、その寂しい感覚を神や宇宙の存在に引き上げているところが面白い。
島を離れる船の上から見上げた夜空の南国の星座の描写がとてもダイナミックだ。
今、私は、人類の絶えて了ったあとの・誰も見る者も無い・暗い天体の整然たる運転を――ピタゴラスの云う・巨大な音響を発しつつ廻転する無数の球体共の樣子を想像して見た。
この文章から受けるダイナミックな印象は、「李陵」のそれとは違うような気がする。彼が学んだ中国古典のエネルギーとは別のところから由来しているような気がする。たとえて言うなら、まるで宮沢賢治が書くかもしれないような。
中島敦の多面性が、この「環礁」の短編ごとに感じられるのが興味深い。
2020年8月10日月曜日
幸福/中島敦
中島敦は、第一次世界大戦後、日本がミクロネシア諸島を委任統治していた時代、南洋庁の編修書記という職務で、約9か月間、パラオに滞在していた時期がある。
その時の経験を基に、南洋を舞台にした幾つかの短編を書き残している。
「幸福」もその一つで、南洋の島に伝わる昔話だ。
身分が卑しい下僕は、彼の主人である長老に、過重な労働を強いられ、いつもひどい仕打ちを受けている。彼は忍耐強い男であったが、そのうち、空咳が出る疲れ病いにかかってしまう。下僕が、神に、病いの苦しみか、労働の苦しみのいずれかを減じてほしいと祈ったところ、夢を見るようになる。
その夢の中では、下僕は長老に成り代わっており、食卓には御馳走が並び、女は妻だけでない範囲で自由にすることができ、誰もが彼の指示に従う。特に長老に似た召使いに対しては過酷な仕事をいいつける。夢から覚めれば、また卑しい下僕に戻ってしまうが、夜の楽しさを思い、彼は昼間の辛苦にも耐えられるようになる。そのうち、夢の中での美食のせいか、病気までもが回復し、めっきりと肥り始める。
一方、長老も同じ時期から夢を見始めるが、その夢は、自分が卑しい召使いとして、自分に成り代わった下僕に無理難題の仕事を強いられるという夢だった。そのうち、長老は、空咳をしはじめ、痩せ衰えていく。
怒った長老は、ついに下僕を呼びつけ、手酷く罰しようとするが...という物語だ。
ガルシア・マルケスのマジック・リアリズム的な作品だが、やはり、空咳をし、痩せ衰えていく下僕に、喘息に侵されていた中島敦自身の影を感じてしまう。
彼がこの下僕のように幸せな夢を見続けることで健康を取り戻し、もっと多くの作品を書き残すことが出来ていたら、どんなによかったろうと思う。
その時の経験を基に、南洋を舞台にした幾つかの短編を書き残している。
「幸福」もその一つで、南洋の島に伝わる昔話だ。
身分が卑しい下僕は、彼の主人である長老に、過重な労働を強いられ、いつもひどい仕打ちを受けている。彼は忍耐強い男であったが、そのうち、空咳が出る疲れ病いにかかってしまう。下僕が、神に、病いの苦しみか、労働の苦しみのいずれかを減じてほしいと祈ったところ、夢を見るようになる。
その夢の中では、下僕は長老に成り代わっており、食卓には御馳走が並び、女は妻だけでない範囲で自由にすることができ、誰もが彼の指示に従う。特に長老に似た召使いに対しては過酷な仕事をいいつける。夢から覚めれば、また卑しい下僕に戻ってしまうが、夜の楽しさを思い、彼は昼間の辛苦にも耐えられるようになる。そのうち、夢の中での美食のせいか、病気までもが回復し、めっきりと肥り始める。
一方、長老も同じ時期から夢を見始めるが、その夢は、自分が卑しい召使いとして、自分に成り代わった下僕に無理難題の仕事を強いられるという夢だった。そのうち、長老は、空咳をしはじめ、痩せ衰えていく。
怒った長老は、ついに下僕を呼びつけ、手酷く罰しようとするが...という物語だ。
ガルシア・マルケスのマジック・リアリズム的な作品だが、やはり、空咳をし、痩せ衰えていく下僕に、喘息に侵されていた中島敦自身の影を感じてしまう。
彼がこの下僕のように幸せな夢を見続けることで健康を取り戻し、もっと多くの作品を書き残すことが出来ていたら、どんなによかったろうと思う。
2020年8月9日日曜日
虎狩/中島敦
「虎狩」という タイトルから、「山月記」を思い浮かべる人もいるかもしれないが、ここで描かれているのは、作者が朝鮮の小学校に通っていた時分、同級生であった朝鮮人(半島人) 趙大煥という男についてのことである。
どちらかというと作者が日韓併合後の朝鮮の人々の様子を描いた「巡査の居る風景 一九二三年の一つのスケッチ」に近い印象を受けた。
趙大煥という少年は、日本語がうまく、母親が日本人(内地人)という噂もあるが、愛すべき少年というよりは、半島人であるがゆえの弱さ、性格的に屈折している点が作者の思い出として語られている。
例えば、趙が自分の名を名乗ることに少しも拘泥していないことを見せる反面、自分が半島人であるということを友人達が意識して、恩恵的に自分と遊んでくれているのだ、ということを非常に気にしていて、彼にそういう意識を持たせまいとする、教師や私作者達の心遣いまでが、彼を救いようもなく不機嫌にした点や、
上級生に生意気だと殴られ、泣き崩れた趙が、あたかも作者をとがめるような調子で、つぶやいた「どういうことなんだろうなあ。一体、強いとか、弱いとか、いうことは。」という言葉(作者は、内地人と半島人の隠しきれない差別感に絶望した感情を感じる)や、
虎狩に行って、虎に襲われそうになった勢子に対して、趙が足で荒々しく其の身体を蹴返して見ながら「チョッ! 怪我もしていない」と言い放つ姿(作者は、講談か何かで読んだことのある「終りを全うしない相」とは、こういうのを指すのではないかと考える)だ。
物語の最後、作者と趙の奇妙な再会が語られるが、ここでも作者は、趙の下卑とも言える表情をきっかけに彼のことを思い出すことになり、あくまで、作者にとって、趙大煥は、半島人であるがゆえの弱さ、屈折している性格のキーワードとして認識されているような気がする。
決して悪い作品ではないのだが、読んていて、気になったのは、中島の視点が支配している日本側のものではないかという感覚がぬぐえない点だ。
もちろん、彼がこれを書いた時代からすれば、あえてこの問題を取り上げていることのほうが称賛されるべきことなのかもしれないが。
敗戦国となった日本人が、むしろ米国で暮らしていたら、周りのアメリカ人にどう思われるか、この作品を読んだら、よけいに身に染みたかもしれない。
どちらかというと作者が日韓併合後の朝鮮の人々の様子を描いた「巡査の居る風景 一九二三年の一つのスケッチ」に近い印象を受けた。
趙大煥という少年は、日本語がうまく、母親が日本人(内地人)という噂もあるが、愛すべき少年というよりは、半島人であるがゆえの弱さ、性格的に屈折している点が作者の思い出として語られている。
例えば、趙が自分の名を名乗ることに少しも拘泥していないことを見せる反面、自分が半島人であるということを友人達が意識して、恩恵的に自分と遊んでくれているのだ、ということを非常に気にしていて、彼にそういう意識を持たせまいとする、教師や私作者達の心遣いまでが、彼を救いようもなく不機嫌にした点や、
上級生に生意気だと殴られ、泣き崩れた趙が、あたかも作者をとがめるような調子で、つぶやいた「どういうことなんだろうなあ。一体、強いとか、弱いとか、いうことは。」という言葉(作者は、内地人と半島人の隠しきれない差別感に絶望した感情を感じる)や、
虎狩に行って、虎に襲われそうになった勢子に対して、趙が足で荒々しく其の身体を蹴返して見ながら「チョッ! 怪我もしていない」と言い放つ姿(作者は、講談か何かで読んだことのある「終りを全うしない相」とは、こういうのを指すのではないかと考える)だ。
物語の最後、作者と趙の奇妙な再会が語られるが、ここでも作者は、趙の下卑とも言える表情をきっかけに彼のことを思い出すことになり、あくまで、作者にとって、趙大煥は、半島人であるがゆえの弱さ、屈折している性格のキーワードとして認識されているような気がする。
決して悪い作品ではないのだが、読んていて、気になったのは、中島の視点が支配している日本側のものではないかという感覚がぬぐえない点だ。
もちろん、彼がこれを書いた時代からすれば、あえてこの問題を取り上げていることのほうが称賛されるべきことなのかもしれないが。
敗戦国となった日本人が、むしろ米国で暮らしていたら、周りのアメリカ人にどう思われるか、この作品を読んだら、よけいに身に染みたかもしれない。
2020年8月2日日曜日
悟浄歎異―沙門悟浄の手記―/中島敦
悟浄が、悟空、八戒、三蔵法師を観察して分析した文章なのだが、これがなかなか名言が多い。
例えば、悟空を評して、
そして、程度の差はあれ、我々が住む娑婆においても、上記登場人物たちの性格を持った人々は少なからずおり、私たちはこの物語を通して、悟浄の分析に共感を覚え、我が身や周りの人々を顧みたりするのだ。
最初にこの物語を読んだとき「わが西遊記の中」という副題を見て、他にも作品があるのではないかという期待を持ったが、残念ながら「悟浄出世」とこの「悟浄歎異」だけだったことを知り、とても残念な気持ちになったのを覚えている。
例えば、悟空を評して、
彼は火種。世界は彼のために用意された薪。世界は彼によって燃されるために在る。
災厄は、悟空の火にとって、油である。困難に出会うとき、彼の全身は(精神も肉体も)焔々と燃上がる。逆に、平穏無事のとき、彼はおかしいほど、しょげている。独楽のように、彼は、いつも全速力で廻っていなければ、倒れてしまうのだ。八戒を評して、
この豚は恐ろしくこの生を、この世を愛しておる。嗅覚・味覚・触覚のすべてを挙げて、この世に執しておる。
八戒は、自分がこの世で楽しいと思う事柄を一つ一つ数え立てた。夏の木蔭の午睡。渓流の水浴。月夜の吹笛。春暁の朝寐。冬夜の炉辺歓談。……なんと愉しげに、また、なんと数多くの項目を彼は数え立てたことだろう! ことに、若い女人の肉体の美しさと、四季それぞれの食物の味に言い及んだとき、彼の言葉はいつまで経たっても尽きぬもののように思われた。三蔵法師を評して、
三蔵法師は不思議な方である。実に弱い。驚くほど弱い。変化の術ももとより知らぬ。途で妖怪に襲われれば、すぐに掴まってしまう。弱いというよりも、まるで自己防衛の本能がないのだ。この意気地のない三蔵法師に、我々三人が斉しく惹かれているというのは、いったいどういうわけだろう?...我々は師父のあの弱さの中に見られるある悲劇的なものに惹かれるのではないか。
師父はいつも永遠を見ていられる。それから、その永遠と対比された地上のなべてのものの運命をもはっきりと見ておられる。いつかは来る滅亡の前に、それでも可憐に花開こうとする叡智や愛情や、そうした数々の善きものの上に、師父は絶えず凝乎(じっ)と愍(あわ)れみの眼差を注いでおられるのではなかろうか。三蔵法師と悟空の共通する点について、
二人がその生き方において、ともに、所与を必然と考え、必然を完全と感じていることだ。さらには、その必然を自由と看做していることだ。金剛石と炭とは同じ物質からでき上がっているのだそうだが、その金剛石と炭よりももっと違い方のはなはだしいこの二人の生き方が、ともにこうした現実の受取り方の上に立っているのはおもしろい。そして、この「必然と自由の等置」こそ、彼らが天才であることの徴(しるし)でなくてなんであろうか?そして、彼らと対比した悟浄自身について、
燃え盛る火は、みずからの燃えていることを知るまい。自分は燃えているな、などと考えているうちは、まだほんとうに燃えていないのだ。
悟空の闊達無碍の働きを見ながら俺はいつも思う。「自由な行為とは、どうしてもそれをせずにはいられないものが内に熟してきて、おのずと外に現われる行為の謂だ。」
俺が比較的彼を怒らせないのは、今まで彼と一定の距離を保っていて彼の前にあまりボロを出さないようにしていたからだ。こんなことではいつまで経たっても学べるわけがない。もっと悟空に近づき、いかに彼の荒さが神経にこたえようとも、どんどん叱られ殴られ罵しられ、こちらからも罵り返して、身をもってあの猿からすべてを学び取らねばならぬ。遠方から眺めて感嘆しているだけではなんにもならない。まったくもって、悟浄の観察と分析は正しいように思う。
そして、程度の差はあれ、我々が住む娑婆においても、上記登場人物たちの性格を持った人々は少なからずおり、私たちはこの物語を通して、悟浄の分析に共感を覚え、我が身や周りの人々を顧みたりするのだ。
最初にこの物語を読んだとき「わが西遊記の中」という副題を見て、他にも作品があるのではないかという期待を持ったが、残念ながら「悟浄出世」とこの「悟浄歎異」だけだったことを知り、とても残念な気持ちになったのを覚えている。
2020年8月1日土曜日
悟浄出世/中島敦
三蔵法師と出会う前、流沙河の河底で鬱々と過ごしていた時期の沙悟浄が描かれている。
彼には、自分の首の周りに食ってしまった僧侶九人の髑髏が見えるが、他の妖怪には見えない。自分の前世が天界の捲簾大将であったことにも懐疑的で、自分というものがただ厭わしく、信じることができなくなっていた。
悩んだ末に、妖怪世界に居る数多の賢人、医者、占星師に教えを乞いに旅に出る。
ある者には幻術を使った実用的な話をされ、ある者には無常観を説かれ、ある者には時の長さは相対的であると説かれ、ある者には神を恐れよと警告され、ある者には自分の醜い姿を肯定され、ある本能主義者には喰われそうになり、隣人愛を説く聖人には講演中に実子を食べる姿をみせられ、ある者には自然に教えを乞うべきであると説かれ、ある者には性行為で楽しむことこそ徳であると説かれる。
それらの教えを受け、ますます自分が分からなくなった悟浄は最後に会った仙人に諭される。
月光が差す静かな河底で眠りから覚め、体が軽くなった悟浄に、観世音菩薩が訪れ、三蔵法師との旅に付き従うよう告げられる。...という物語だ。
悩みに悩んだ悟浄が完全ではないが倦怠と自己不信という病(精神的危機)を克服する過程は、一種の教養小説と言ってもいいかもしれない。
これを私小説風にやると相当鬱陶しい印象を受けるかもしれないが、西遊記という古典娯楽小説を舞台にしているせいか、物語からは明るい印象を受ける。
なお、日本では河童のイメージでお馴染みだが、中国では僧形をしているという。
彼には、自分の首の周りに食ってしまった僧侶九人の髑髏が見えるが、他の妖怪には見えない。自分の前世が天界の捲簾大将であったことにも懐疑的で、自分というものがただ厭わしく、信じることができなくなっていた。
悩んだ末に、妖怪世界に居る数多の賢人、医者、占星師に教えを乞いに旅に出る。
ある者には幻術を使った実用的な話をされ、ある者には無常観を説かれ、ある者には時の長さは相対的であると説かれ、ある者には神を恐れよと警告され、ある者には自分の醜い姿を肯定され、ある本能主義者には喰われそうになり、隣人愛を説く聖人には講演中に実子を食べる姿をみせられ、ある者には自然に教えを乞うべきであると説かれ、ある者には性行為で楽しむことこそ徳であると説かれる。
それらの教えを受け、ますます自分が分からなくなった悟浄は最後に会った仙人に諭される。
臆病な悟浄よ。お前は渦巻きつつ落ちて行く者どもを恐れと憐みとをもって眺めながら、自分も思い切って飛込もうか、どうしようかと躊躇しているのだな。...物凄い生の渦巻の中で喘いでいる連中が、案外、はたで見るほど不幸ではないということを、愚かな悟浄よ、お前は知らないのか。悟浄はそれでも釈然としなかったが、自分の中にあった卑しい功利性に気づく。そして、遂には疲れ切って何日も眠り続けてしまう。
月光が差す静かな河底で眠りから覚め、体が軽くなった悟浄に、観世音菩薩が訪れ、三蔵法師との旅に付き従うよう告げられる。...という物語だ。
悩みに悩んだ悟浄が完全ではないが倦怠と自己不信という病(精神的危機)を克服する過程は、一種の教養小説と言ってもいいかもしれない。
これを私小説風にやると相当鬱陶しい印象を受けるかもしれないが、西遊記という古典娯楽小説を舞台にしているせいか、物語からは明るい印象を受ける。
なお、日本では河童のイメージでお馴染みだが、中国では僧形をしているという。
登録:
コメント (Atom)