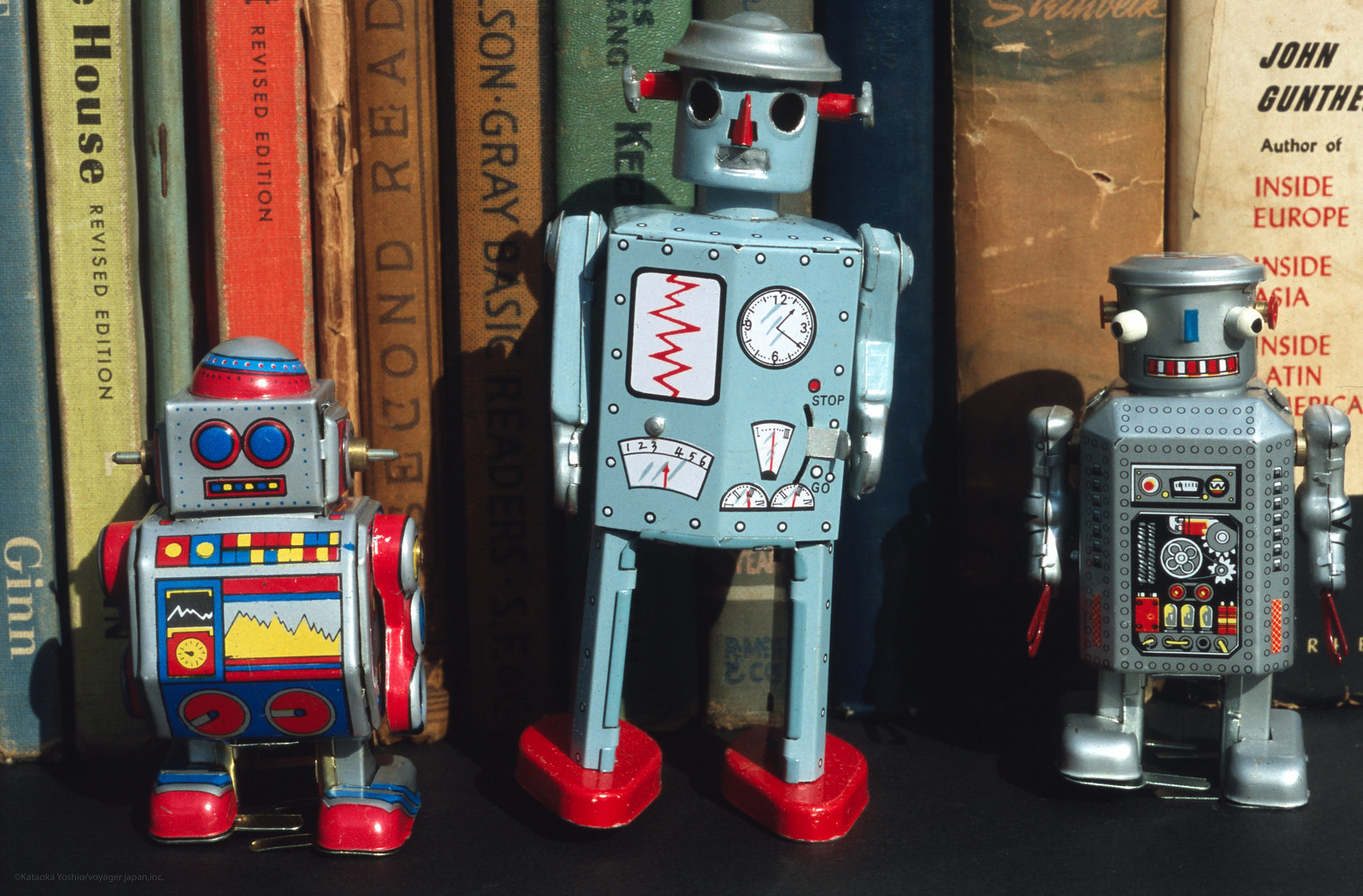広大無辺な可能性の世界があるこのドン・ファン・マトスという人物、北メキシコのヤキ・インディアンの呪術師ということらしいが、その存在が確認できるのは、彼の弟子と称する人類学者カルロス・カスタネダが書いた著書のなかだけである。
そこへ飛び立つ
別の時間 別の世界
ドン・ファン・マトス
しかし、この「幻魔大戦deepトルテック」という平井和正の最後の作品は、ほとんど、このドン・ファン・マトスが弟子のカスタネダに語ったという呪術師(トルテック)の世界観がベースとなっており、従来の幻魔大戦の過去の記憶を若干残しつつも、その根本的な世界観は、すべて捨て去ったと言い切っていいだろう。
悪魔(幻魔) → 捕食者、外来装置
フロイ → 無限
超能力者 → 呪術師(トルテック)
超能力 → 精霊(ナワール)、内的沈黙
GENKEN、光のネットワーク→ 女トルテック
と、キーワードを置き換えること自体、無意味なのかもしれないが、重要なのは、なぜ、平井和正が、こんな世界観の転換を図ったかということだ。
おそらく、彼は既存の宗教に幻滅していた。
それは、自身が関わっていた新興宗教が契機だったかもしれないが、オウム真理教、イスラム教をめぐる様々な争いや事件が決定打となったのかもしれない。
そして、もっと深いところで、既存宗教、特にキリスト教、イスラム教という一神教に対して嫌悪した。
実際、 この物語の主人公 雛崎みちるは、こんなことを言っている。
わたしはトルテックのものの考え方がとても好きなの。専制的な宗教の示す教えがほとんど見て取れない。地獄とか極楽とか神の怒りとか神の与える罰とか、強迫観念を人間に与えるものの考え方などだけど。本当に自由な人間とはどんなものか、想像ができるから既存の宗教は、人間の持つ自由を拘束し、強迫観念を植え付け、狭い世界に閉じ込める役割しか果たさない、と彼は感じたのかもしれない。
彼の同様な嫌悪は、おそらく同様の理由で、中国(中国共産党に支配される中国)に対しても向かう。この世界のハルマゲドン(十五億人の消失)が中国で起きるという想定にも表れている。
平井和正が ドン・ファン・マトスの世界観のどこに「人間の自由」を感じ取ったのかは、カスタネダの著書をちゃんと読んだことのない私にはわからない。しかし、冒頭の文言にも関連するように、この物語では、雛崎みちるに対して、トルテックのマエストロの一人であるセタがこう言い含める。
呪術師たちは人間だ。そして失敗は人間にはつきものなのだ。ひとつのことで失敗しても、別のことで成功する。可能性の世界(現実)は実に広大だ。...人間の自由とは、無限の可能性に挑戦することなのだ。人間の生きる目的はそこにある。喜びもそこにある。新幻魔・幻魔・真幻魔、ウルフガイ、アダルトウルフガイといった平井和正の主要な作品にも見られたパラレル・ワールドという概念が肯定される世界観。おそらく、 平井和正はドン・ファン・マトスのトルテックの世界にそれを感じたのだろう。
十代の若い雛崎みちるにトルテックの力を与え、並行世界を、異なる時間を、自由に移動させ、アブダクション、ウルフガイという別の作品をも取り込み、総体として、無限の可能性に満ちた世界に“仕上げ”をさせる。
かつて、人類の暴力と悪辣さに苛まれた犬神明と青鹿晶子のこの物語における幸福な結末は、その好例なのかもしれない。
平井和正は、七十歳を迎えた最後の作品で、自らの世界観をこれだけ大きく変えることができたのだ。
そして、およそ終わりを迎えることができないと言われていた幻魔大戦の物語は、二月の雪の日、中学生の雛崎みちるの意識の中でひっそりと終わる。
誰も予想だにしていなかった結末、こんな終わり方があり得るとは。