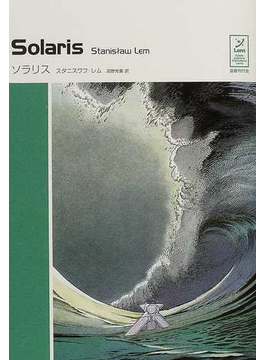1961年にポーランドのワルシャワで最初に出版されたスタニスワフ・レムの「ソラリス」は、ポーランド語で書かれており、従来、日本語訳されたハヤカワ文庫の「ソラリスの陽のもとに」は、ロシア語版からの重訳だったらしい。ロシア語版は、ポーランド語の意味を取り間違えていたり、検閲によって削除された部分がかなりあったらしく、日本語訳ですべて修復・復元されたバージョンはなかった。
これらの理由から、ロシア・ポーランド文学者である沼野充義が、オリジナルのポーランド語から新訳した「ソラリス」が出版されたので読んでみた。
この新訳を読んで、改めて思ったが、「ソラリス」は、普通のSF小説とは、全く異質な内容になっている。
人類の善悪・進化・社会を鏡のように対照化した異星人との接触ではなく、全く想定外の未知なものとの接触を描いている。言わば、スター・ウォーズ的な物語とは完全に相反した作品だと思う。
従来の「ソラリスの陽のもとに」との比較で言えば、復元された記述によって、圧倒的に、ソラリスの海が存在感を増している。ソラリスの海が作り出す様々な形態、擬態形成体(ミモイド)の緻密でグロテスクな描写は、生物としてのソラリスの海を強く感じさせる。
また、私にとっての「ソラリス」は、原作を読む前に見たタルコフスキー監督が撮った「惑星ソラリス」に影響されているところが多く、今回、改めてその違いを面白いと思った。
以下、「惑星ソラリス」との違いという視点で、興味深いものを取り上げてみる。
・スナウトの闇
ソラリス観測のステーションにおいて、好人物であるスナウト。
しかし、最後まで彼の「客」は何なのか、明かされていない。
(映画では、柔らかそうな耳たぶの映像が、女性か子供を暗示している)
スナウトの発言や、クリスが目撃した彼の両手の指の関節に凝固していた血が、彼の闇の部分を暗示している。
・ギバリャンの「客」
映画では、ロシア人風の少女であったが、小説では巨体の半裸の黒人の女が描かれており、スナウトが「客」について語る「人間のうちにひそむ何かが勝手に考え、湧き出てきたこと」が実証されたような印象を強く感じる。
・ステーションの気温
映画では、どちらかというと寒々とした印象だったが、小説では、冷房装置が動いでいないと耐え難い暑さであるところも意外な印象を受けた。
・狂っていないことの検証
クリスが「客」のハリーを見て、自分が狂っていないことを確認するために、小型人工衛星の描く円の位置を手計算し、大型コンピュータが計算した数字と比較して誤差を確認するあたりは、いかにも科学者的なふるまいである。映画では、このようなクールな場面はなかった。
・ソラリスに降り立ったクリス
映画では、クリスが地球にある父の家に帰還し、すがりつくように父にひざまずく印象的なシーンが描かれるのだが、実はそれはクリスの内面的精神を読み取ったソラリスの海が作り出したものだったという、ある意味、ショッキングなラストで終わる。しかし、小説では、クリスが降り立った岸辺でソラリスの海と静かに接触を交わす場面で終わる。ここは好みの問題と思うが、小説の方が、クリスが、理解不能なソラリスの海と最後まで誠実に接触し、理解しようと努めていたことがより伝わってくる。
あとがきにある、作品の解釈をめぐって、レムがタルコフスキーに対して「あんたは馬鹿だよ」とロシア語で言って別れたというエピソードが面白い。