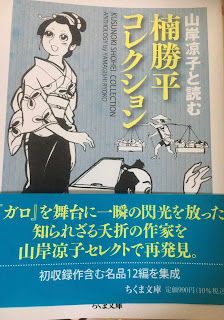この小説も読み方によっていろいろな解釈ができる。
登場人物は、会社に勤めている私と、アルバイトに来た大学生の川村綾子を軸に、二人が好きな作家 山野秋奈と、綾子が高校時代美術部の担任であった秋奈の夫 山野稜一郎、さらに私の別れた男 萩のいとこで稜一郎とも交友関係がある杉本が加わる。
綾子が秋奈の講演会で声を掛けられ、稜一郎の個展の初日のパーティーに誘われることを聞いた私は、綾子と秋奈と稜一郎を「三人関係」に仕立てあげるための物語を妄想していく。
私の思っている「三人関係」とは、「つかみどころがなく、ゆったりとした関係。誰が誰と結びついているのか、わからないような関係」をいうのだが、綾子が山野夫妻との交流を深めていくにつれ、綾子と秋奈と稜一郎の関係は、次第にそれに近いものになっていく。
ただ、それが本当に綾子が私に語ったことなのか、私の妄想なのかは曖昧模糊としていてわからない。
そして、ある日、綾子がバイトを辞めてしまい、「三人関係」の物語を作れなくなった私は、杉本と稜一郎の関係をつてに、自分が秋奈の講演会に行き、山野夫妻と「三人関係」を持つことを想像するのだが、それは綾子の「三人関係」の物語を繰り返すことになることを避けられないと、ぼんやり思うところで物語は終わる。
物語には、謎が多い。
秋奈がどういった内容の著書を書く作家なのかも分からないし、夫 稜一郎との関係もよくわからない。
二人の住む家もどこにあるのかも分からない。東京の北西部を走る古い私鉄 葉芹(はせり)線の貝割礼駅という奇妙な名前も印象的だ。
綾子から聞いた「三人関係」の物語は、私のすべて妄想だったのか、私が山野秋奈を私が作った「三人関係」の物語の中に絡めとりたかったのか。