この小説は、数年前だったら、主人公がこんな心持ちになったのは、ツヴァイクの特別な個性によるところだろうと片づけてしまった気もするが、今の日本において読むと、戦争になるとは、こういう風に国家に追い詰められていくのだなという現実(リアリティ)を強く感じた。
1920年の作品だから、おそらく第一次世界大戦のさなか。画家である主人公フェルディナントと妻パウラは、ドイツからスイスのチューリッヒに亡命している。
しかし、フェルディナントは故国からの呼び出しに怯え、自分の本来の意思に反するように、徴兵の兵役能力再検査のために領事館に出頭することを命じる紙を受け取ってしまう。
冷静で賢明なパウラに、自分の生命と自由を守るためには、絶対には行ってならないと説得されるが、フェルディナントは領事館に行ってしまい、これまた、自分の意思に反するような形で入隊の手続きをしてしまう。
絶望するフェルディナントに気づいたパウラは、度重なる説得と妨害を行うが、フェルディナントは故国へ向かう汽車に乗ってしまう…という物語だ。
フェルディナントは、知識人であり、戦争とそれを起こす政治家の蒙昧さを理解し、理性的に反抗できる資質があるにも関わらず、まるで自分の運命が国家からの命令書に記載された通りであり、これに抗うことはできないような心的状況に陥っている。
「まるで学校の生徒が先生の言葉で立上がるように立上がって…ぶるぶる慄えながら命令に従う」
「自分のものではない意志の鉄のぜんまいが身うちに動き、あらゆる神経を緊張させ関節までも引締めはじめた」
例えば、ロシアの善良な国民が(いや、ウクライナの善良な国民でさえ)、こうした目に見えない「圧迫」に押しつぶされ、戦地に向かっているかと思うと気が滅入る。
こんなことはかつての日本でも起きたことなのだ。
そして、その空気感が凍結された地面から死臭のように漏れ出しているのを、今の日本の時代の雰囲気から感じるからこそ、この作品のリアリティを感じるのだろう。
P.S. 石川淳の「マルスの歌」と似ている。この作品も2018年に読んだが、今読んだら、もっと刺さったような気がする。

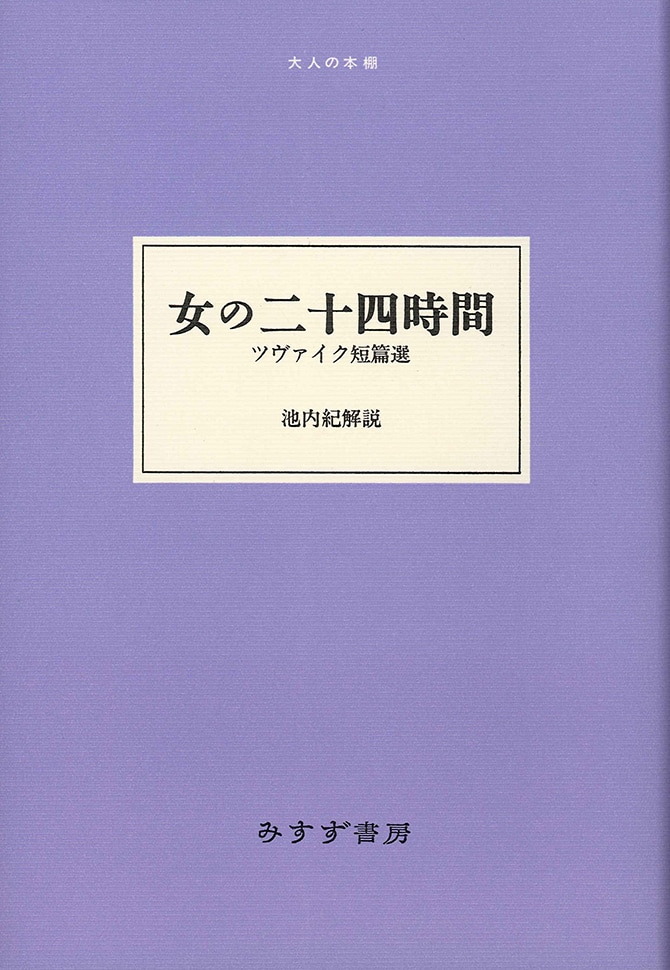
0 件のコメント:
コメントを投稿