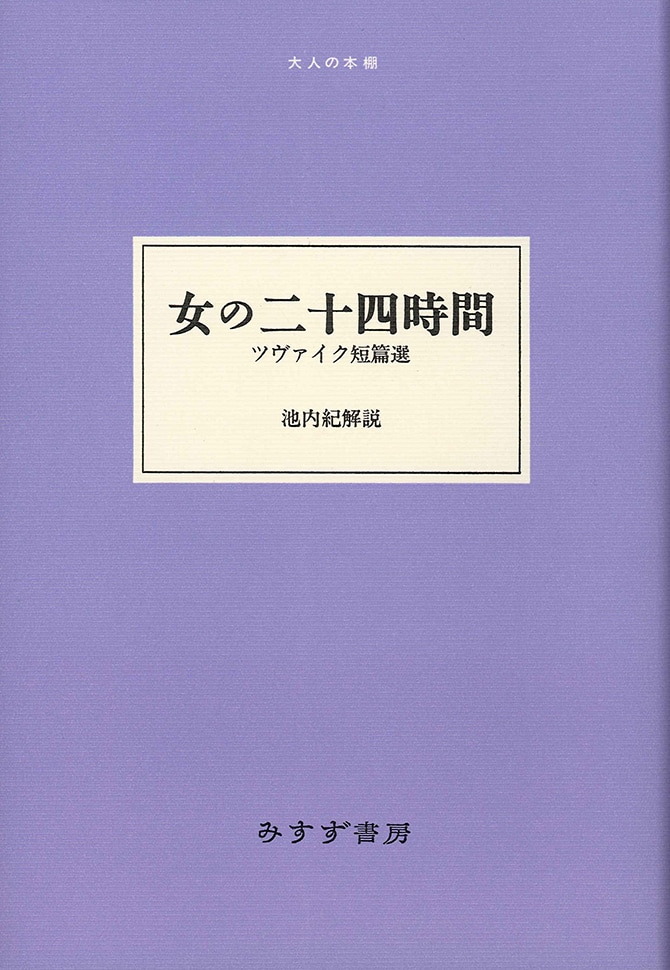クライストの小説は、多和田葉子の新聞連載で「ロカルノの女乞食」を一読しただけだったが、ツヴァイクの書いたクライスト論を読んで、その小説を改めて読みたくなった。
ツヴァイクは、クライストの両極端の二面性を取り上げ、彼の過剰な狂気のような自我は劇作のほうに反映される一方、小説については彼自身の影は一切映さず、完璧な文体で堅牢な物語を提供したと述べている。
「チリの地震」は、こんなあらすじだ。
修道院で密通を犯した二人のカップル、ジェロニモとジョゼフェが、その罪で首吊りの刑に処せられる。しかし、刑を執行しようとしたその刹那、大地震が発生し、多くの人々が命を落とす中、二人は命が救われ、二人の子供も助かる。
ジェロニモとジョゼフェは、当初スペインに逃げることを考えるが、避難生活の中、軍司令官のドン・フェルナンドと遭遇し、彼の家族と親しくなり、二人の罪は震災で許されたような感覚を覚え、チリに残ることにする。
震災後、教会がこれ以上の禍を避けるために祝祭ミサを開くことになり、ジェロニモとジョゼフェは、フェルナンド一家と教会に行くことになるが、聖職者たちは、今回の地震でさえ、ソドムとゴモラで起きたような道徳的退廃、蛮行が根絶できなかったことを述べ、ジェロニモとジョゼフェの冒涜行為を非難する。
取り囲まれた聴衆から暴力を振るわれる危険を、ドン・フェルナンドと彼の知人であるドン・アロンソの機転で一時免れるが、教会を出た後、荒れ狂う群衆を止められず、ジェロニモとジョゼフェは棍棒で殴り殺される。そして、罪のないフェルナンドの子供と義妹も命を落とす。
ドン・フェルナンドと妻は、ジェロニモとジョゼフェの赤ちゃんを自分たちの子供として育てていく決心をする…という物語だ。
一読して、全く隙のない短編小説に仕上がっていることに驚いた。
ある意味、老成した短編小説家が、冒険せず自身のテリトリーで腕をふるって書いたとさえ思うほどだ(この作品を書いた時、クライストは三十三歳)。
作者であるクライスト、物語中、この悲劇に対して自分の考えや思いを全く表明していないようにも思える。
ただ、わたしにはやはりクライストが背徳の罪を犯した二人の側に立っている印象を受ける。そして罪人でありながら、暴徒と化した世間から逃げず、堂々と立ち向かった二人の姿は、自分を理解し受け入れようとしない世間に対するクライストの思いを具現化した姿だったのではないだろうか。