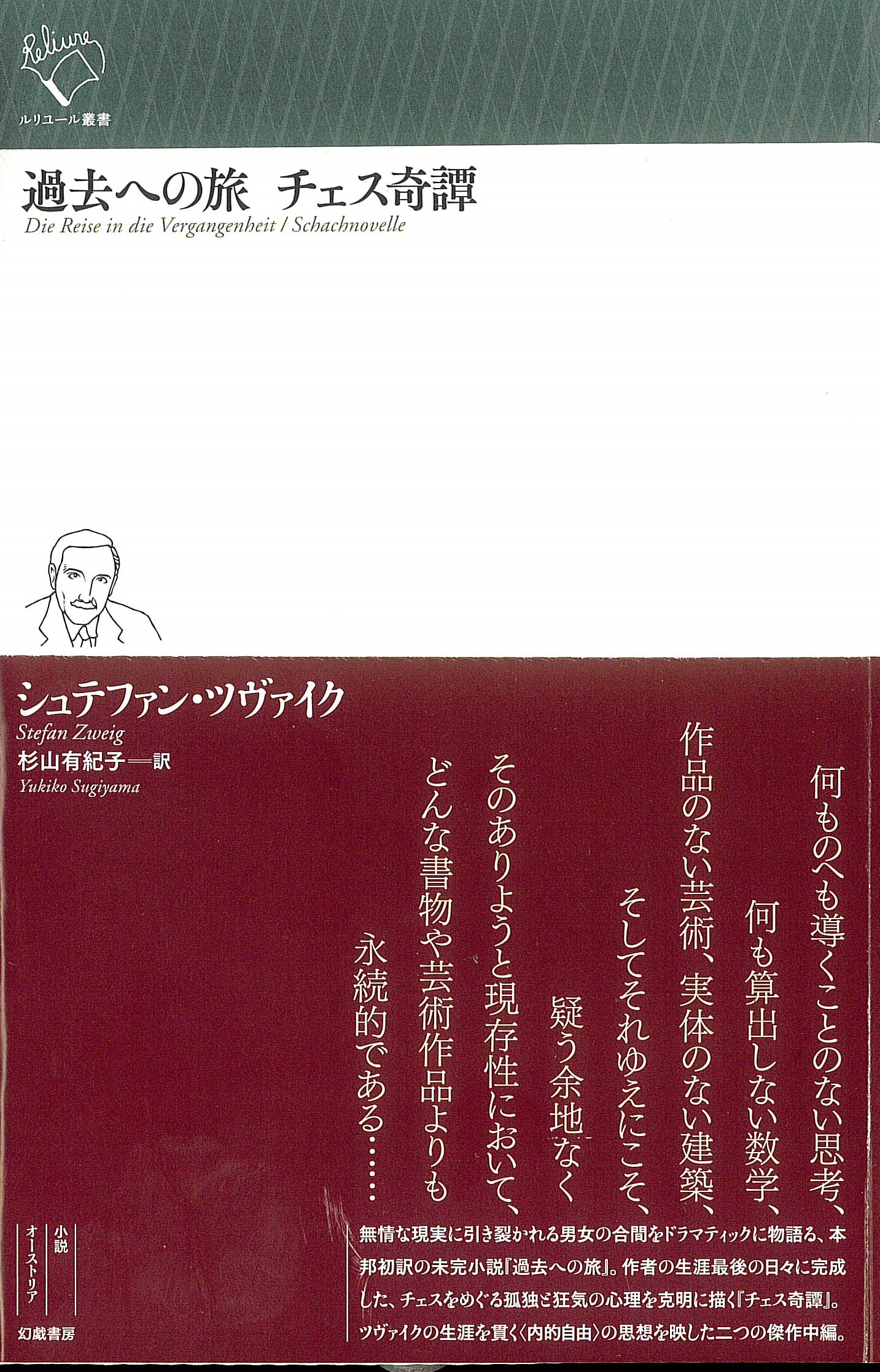ツヴァイクが死ぬ直前に書き上げた最後の作品だが、非常に面白い小説である。
物語は、チェントヴィッチという田舎町出身の愚鈍そうな少年が驚異的なチェスの名人になる話から始まる。
彼には文字通りチェスを指すしか能がなく、文章もろくに書けない知性の持ち主でもあった。
そして最も特徴的なのは、常に目の前にチェス盤と駒を置かないと、チェスのプレイが出来ず、自分の頭の中でチェス盤を想像しチェス駒を動かしてゲームを諳んじることができないことだった。
そんなチェントヴィッチを、作品の中の”私”は、こんな風に評しているのだが、チェスという競技の特質を一面で正しく捉えていると思う。
人間は自分を限定すればするほど、他方でそれだけ無限へと近づくことになる。そのような一見世間離れした人々こそがそのきわめて特異な素材の中で、完全に唯一無二の奇妙な世界の縮図を白蟻のように作り上げるのだ。
その私が、チェントヴィッチと同じ十二日間のリオまでの船旅の間に、いかに彼に接近して、その特異な知性を観察しようかと企む。
私は、マッコナーという羽振りのよい財産家の男とチェスを行うことで、チェントヴィッチの関心を惹こうとし、紆余曲折の末、マッコナーがチェントヴィッチとチェスの試合を行うことになる。
一試合目でマッコナーがあっという間に負け、二試合目も、マッコナーがチェントヴィッチが巧妙に仕掛けた罠に嵌ろうとした刹那、一人の紳士、B博士がストップをかける…という物語だ。
とりわけこの小説で興味深かったのは、作品の中の”私”に語ったB博士がチェスを覚える特別なきっかけと特別な環境なのだが、読んでいて息をつかせないほどの面白さだった。
チェスの作品で思い浮かぶのは、ナボコフが書いた「ディフェンス」という小説だが、個人的な好みとしては、この「チェス奇譚」のほうがはるかに面白いと思う。
*翻訳された杉山有紀子さんの文章も読みやすかった。